お役立ち情報
COLUMN
クラブATO会報誌でおなじみの読み物
「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!
日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、
その時々の時勢を分析していたりと、
中々興味深くお読み頂けることと思います。
絞り込み:
-

東京六大学野球
9月になると、神宮球場は東京六大学野球秋季リーグ戦の真っ盛り。もっとも昨今では、野球人気はもっぱら米国大リーグ(MLB)の日本人選手の活躍に移ってしまい、その次が日本のプロ野球と甲子園の高校野球。六大学野球と都市対抗の社会人野球なんぞはすっかり地味な存在になってしまった。が、選手の技量はプロ野球の予備軍と言ってもよいし、以下に述べる独特の応援様式などを見ると、やはり東京六大学野球にはよき伝統の美しさもあると思うので、今日はそのことを中心に述べたい。
東京六大学野球連盟が結成され、リーグ戦が慶應、早稲田、明治、法政、立教、東京帝国の六校で行われるようになったのは大正14年(1925年)。翌大正15年(1926年)には、六大学野球を開催する「ために」明治神宮野球場が完成した、と、連盟の発行しているガイドブックにはある。当時はまだプロ野球もなく、六大学野球は大相撲に次ぐ国民の人気スポーツであり、まだ普及したばかりのラジオによる実況中継とも相まって、今日では考えられない程の大衆の注目を集める存在であった。
さて、この稿の筆者が初めて六大学野球に触れたのは、今から約半世紀前。1971年慶應義塾に入学した直後の春季リーグ戦、法政大学対慶應義塾大学の試合であった。日吉にキャンパスから当日の午後の試合を先輩に連れられて見に行った記憶があるから、たぶん5月の月曜日の試合(土、日が一勝一敗になると月曜日に勝ち点をめぐって第三試合が行われる)であったろうと思う。 法政横山晴久投手に対するに慶應義塾の四番打者は松下勝美の対決。連盟の公表している記録を調べてみるとこの春季リーグ戦は、法政が優勝した(その後の71年秋季から三季連続で慶應が優勝)とあるから、多分この試合も法政が勝ったのであろう。ともあれ、初夏のさわやかな風が吹く神宮球場、試合が終了したのは暮れなずむ頃、一塁側慶應義塾の応援席から、三塁側法政の応援席を眺めれば、傾く夕日を受けて輝く紺オレンジ紺三色縦縞の法政大学の大きな校旗がさっと上がるとともに、校歌の演奏が始まる。筆者は当時慶應、早稲田、明治の校歌くらいしか知らなかったが、初めて聴く法政の校歌は荘重でいかにも校風をよくあらわしており、三塁側内野学生応援席をほぼ埋めた学生たちの合唱が夕べの球場に響くのであった。ついで法政から慶應に向けたエールの後、今度はわれら慶應の塾旗が上がり、長い歌詞の塾歌の一番が合唱され、「フレー、フレー法政」のエール。そして、校旗と塾旗がお互いに礼をするように一度相手に向けて静かに倒されて、また上がる。これら儀式の間およそ15分。なにより、慶應の塾生となったことを実感する瞬間であった。筆者は、その伝統の様式美にうたれ、その後「神宮通い」をするようになったのである。慶早戦に至っては、実に在学中六年間全試合(たぶん30試合くらい)を完全にフォローしている。
2025年9月30日
-

公開鍵暗号
先月は、暗号の共通鍵をどうしたら安全に更新できるかという課題を書いた。
AさんとBさんが定期的にリアルの世界で面会する機会があるならば、その都度封筒に入れて紙に印刷された共通鍵の数列を渡せばすむのだろうが、暗号文を交換する者同士が距離の離れたところに存在する場合、インターネットや無線通信などでも安全に共通鍵の更新を行えるようにしなければならない。そこで発明されたのが公開鍵暗号という別のジャンルに属する暗号方式である。公開鍵暗号とは、ひと言で言えば、「暗号文を封筒に入れて中身を推定できないようにして、インターネットや無線通信で離れたところに送る」暗号方式である。
たとえば、新しい共通鍵をBさんと共有したいAさんがいたとする。Aさんはまず自分が持っている新しい共通鍵をさらに公開鍵暗号(たとえばRSAとかECCとかいう)という特殊なアルゴリズム(数式)に乗じて、別の数列に変換する。その別の数列はインターネットや無線通信上で第三者にみられても、元の数列(共通鍵)に復号できない特殊な数列である。ところがBさんがこの特殊な数列を受け取るとなぜか自分だけは(まるで封筒を開くように)復号することができて、元の共通鍵を取り出すことができるのである。もちろん公開鍵暗号はただの封筒ではない。Aさんが共通鍵を公開鍵暗号に変換するときには自分のパスワードを入力する。Bさんが公開鍵暗号を復号するときには自分のパスワードを入力する。だが優れものなのは、AさんのパスワードをBさんは知らない。BさんのパスワードをAさんは知らない。つまり公開鍵暗号方式とは「封筒の開け方は自分しか知らない」のにAさんとBさんとの間で暗号通信のやりとりができる方式だということなのである。
世間で公開鍵暗号がどのように使われているかというと、多くの場合は共通鍵の更新と共有のために使われている。が、用途はそればかりではなく、公開鍵暗号そのものを用いて暗号文のやりとりをすることもできる。但し、公開鍵暗号は共通鍵を用いた暗号よりも複雑なアルゴリズムを用いるので、計算量も多く、コンピュータにかかる負荷が大きい。このことがIoTの世界で組込機器を使用する場合には、大きな問題となる。先に述べた基本は共通鍵暗号を用いながら、共通鍵の更新に公開鍵暗号を用いるという、共通鍵と公開鍵の併用方式が多く用いられているのは、じつはこのIoTと組込機器の分野なのである。
本稿の最後に、共通鍵、公開鍵の暗号方式として具体的にはどのようなものがあるかについて、少しだけ紹介しよう。共通鍵暗号では、DES(Data Encryption Standard)が1976年11月に米国政府規格として標準化され、改良されながら長く使われてきた。しかし、さすがに長い時間を経て学会などでこの暗号を破る実績が多く出てきたので、米国政府は新たな公募を行い、2001年からAES(Advanced Encryption Standard)が規格化され、実市場においても次第にDESと交代するようになっている。現在では、AESの共通鍵256ビットを用いた方式であれば当分の間はほぼ安全に運用できるとされている。公開鍵暗号では、民間のRSA社が開発したRSA方式と、米国政府が規格化したECC(楕円曲線暗号)方式が実市場で併用されている。2025年8月29日
-

共通鍵暗号
これから二回にわたって、この稿の筆者の専門分野である暗号の話を書きたい。
世の中には、暗号は大きく分けて二種類、共通鍵暗号というのと公開鍵暗号というのがあって、前者は簡単でシンプル、後者は複雑。どちらが安全かと言えば後者の方、ということが比較的知られている。が、それらがどう違うかと言うことは一般にはあまり理解されていない。そこで今月と来月は、両者の違いについて、すこし解説したい。
まず、今日の社会では、暗号化される前の通信文はほとんどコンピュータとかワープロなどの機械で書かれており、平文をソフトウェアで数列に転換したものが元のデータであるという前提から出発したい。(もちろん手書きの平文や画で描かれた通信文というのもないことはないが、これらも今日では、一度pdfなどの機械ソフトでスキャンして数列データに置き換えられて交信されている)さて平文を数列に置き換えたものを素データと呼ぶことにしよう。素データに一定の別の数列(暗号鍵と呼ぶ)を一定の暗号式(アルゴリズム)で乗じたものが暗号文である。この場合、AさんとBさんの間で暗号文が交換されるとすると、AさんとBさんの間では三つのことが了解されていなければならない。
一つ目は、素データを人間が読める平文に還元するためのソフトウェア(ワードとかテキストとか)がなんであるかという了解。二つ目は、上記の一定の暗号式
(アルゴリズム)がなんであるか(暗号アルゴリズムの名前。AESとかDESとか・・)という了解。そして三つ目は、その暗号文を復号するための暗号鍵がなんであるかという了解。
AさんとBさんの間でこの三つの了解があって初めて、Aさんは平文を暗号化してBさんに送り、Bさんは受け取った暗号文を平文に還元して読むことができるのである。
さて、上記の了解のうち一つ目は世間で一般に使われているソフトウェアであることが多いし、二つ目も、世間で認められている安全な暗号アルゴリズムの種類がそう多くあるわけではないので、実質的に外部の人に知られていない秘密の情報というのは、三つ目の暗号鍵ということになる。このAさんとBさんが共通で持っている秘密の暗号鍵のことを「共通鍵」と呼んでいる。暗号鍵の数列は長ければ長いほど外部から推定しにくい(共通鍵を知らないCさんが、AさんとBさんの間で交換されている暗号文の中身を知ろうとすれば、力業でコンピュータに数列をつくらせて次々と試してみなければならない)。が、あまり長いと実用的ではないので、現在では、128ビットとか256ビットくらいのランダムな数の列が共通鍵として用いられている。
もっとも、AさんとBさんの間であまり長い間、同じ暗号の共通鍵を使っていると、不慮のことから外部に共通鍵を知られてしまう危険が増すことになる。上記のCさんが偶然力業で共通鍵を推定してしまうかもしれないし、AさんとBさんのどちらかのコンピュータが悪意ある他者に(ハッキングされて)見られてしまうかもしれない。なので、AさんとBさんの間では、時々共通鍵をちがうものに改める(更新する)ほうがより安全なのである。
それでは、AさんとBさんの間でどうすれば共通鍵を更新することができるのだろうか。
次号では、離れていても共通鍵を更新する別の暗号方式を紹介しよう。2025年7月31日
-

アスパラガス
私事であるが、その昔この稿の筆者の自宅の庭に、ポショポショした平たい、見た目クリスマスツリーのような格好をした草が生えていた。母親が、「これはアスパラガスなの」というのだが、食卓に上る幹の太い緑色の野菜とこの草とがどうにもつながらなかった。それでも戦後まだ間もないころで、アスパラガスは高価ななかなか家庭で食べるのが難しい野菜だったから、筆者はこの草がいつかあのアスパラガスに成長するのではないかと期待していたのだが、残念ながら草はいつの間にか芝生の間にまぎれてしまい、庭のアスパラガスを家庭で食する夢はかなわなかった。この稿の筆者がはじめて親許を離れて、自炊体制に入った日につくった料理というのが、アスパラガスとベーコンの炒め物、スクランブルエッグとトースト、コーヒーというもので、心のどこかでアスパラガスへの執着が残っていたのかもしれない。
アスパラガスは学名Asparagus officinalis、和名はオランダキジカクシ(和蘭雉隠)。原産地はヨーロッパの地中海沿岸のどこか。ローマ時代の紀元前2000年ごろには栽培されていた記録があるとのこと。その後ヨーロッパ各地で栽培が広がった。北米には1620年の移民とともにもたらされ、東部地区やカリフォルニアで栽培されるようになり、一大産地となった。i 日本には江戸時代中頃にオランダ船によってもたらされたが、当初は観賞用で、食用として利用、栽培されるようになったのは、明治期、北海道開拓使が導入してからのこととされる。
さて、ご承知のようにアスパラガスには、緑色のものと白いのと二種類がある。同じアスパラガスなのだが、前者は自然に太陽の光を浴びて育ったもの。後者はわざと生育中に土をかけて直射日光が当たらないようにしたものである。現在でもそうかもしれないが、ホワイトアスパラガスを水煮して缶詰にしたものは、自然に生育して野菜として店頭に並べられているものに比較して、かなり高価なもので、子供のころはなんとなくカニ缶などと並んで贅沢品という印象が強かった。
欧州とくにドイツ、オーストリア辺りではこのホワイトアスパラガスをSpargel(シュパーゲル)と呼び、日本の筍同様春の味覚として珍重する。この稿の筆者は5月連休にウィーンに滞在したことがあるが、郊外のホイリゲ(新酒という意味だが、それを供する居酒屋もホイリゲと呼ばれる)の野外のテーブルでさわやかな春の風に吹かれながら、ホワイトアスパラガスのサラダにオランデーズソース(卵の黄味とバターでつくったマヨネーズのようなソース)をかけたものを肴に、冷えた白ワインを飲んだのは、筆者生涯の思い出の一つである。
一方、緑のアスパラガスについては、ベーコンやソーセージなどの豚肉類と相性が良い。
同じウィーンには、ウインナー・シュニッツェルという紙のように薄いカツレツ料理があり、これなどもアスパラガスを添えていただくと、なかなか乙にいただける。(このカツレツには、濃い味のソースはかけずに、塩とレモンだけをかけていただくのがよろしい)
緑アスパラガスは、茹でる、炒めるももちろん良いが、この稿の筆者は、油を一切使わずにトースターか炭火で少し炙った緑アスパラガスに、削り節と醤油をパラパラとかけていただくのがおいしいと思っている。生ビールのつまみとしても最適なので、読者の方にもぜひお試しいただきたい。
アスパラガスの産地は、北海道、長野、福島などが知られている。国内では北海道が第1位の収穫量で、全国の16%を占めている。本稿が出る頃には道産品が最盛期を迎える。
i Wikipedia
2025年6月30日
-

OSO18
人間どもが、俺にOSO18という記号みたいな名前をつけて呼ぶようになったのは、2019年7月のこと。人間界ではこういう名付け方をコードネームとか言うらしいが、せめて「於曽重八」とかそれらしい名前にして欲しかったものだ。命名の由来は、俺が人間界で個体の熊として認識されるようになった場所が、北海道の標茶町オソツベツという所だったことと、俺の足跡が雑な測り方で18cmあったことによる。
さて、その年の7月16日、俺にしては不覚なことに、一頭の乳牛を牧場の近くの沢に引きずって行き、腹を割きかけたところを、牧場主の息子に見られてしまった。まさに「藪から棒」の出会いで、俺の方もかなり慌てていたのだが、見られてしまったものは仕方がない。そこでカモフラージュというわけでもないが、その夏8月にかけて、28頭の牛を襲った。なかには、襲うだけで食べずに怪我を与えて赦してしまうこともあった。ほんとうは牛を食べたいわけではなく、俺にしてみれば人間界に対するゲリラ戦というか、人間界に「神出鬼没の熊」というイメージを与えて威嚇したかったのだ。
その俺の試みは半ば成功し、半ば失敗した。たしかに俺は「神出鬼没の熊」というイメージをつくることに成功し、OSO18は人間界から畏怖を持って見られるようになった。が、一方で人間界に俺様専門の討伐隊が編成され、各所の牧場近くに俺を捕獲するための罠が仕掛けられるようにもなり、いわば俺と人間界との関係は、「全面戦争」にエスカレートしてしまったのだ。俺の18cm前後の足跡と、俺が鉄条網などに残してきた体毛をDNA鑑定することを通じて、人間どもは俺の攻撃実績と他の熊の移動とを的確に区別し、俺の跡を追跡するようになった。他の熊の場合、よほど腹が空いたりしなければ人間界の牧場を襲うことはしないし、野生動物であれ、家畜であれ動物蛋白はそもそも熊の主食ではない。山に笹の実やドングリが豊富にあれば、わざわざ危険を冒して人間界に下りてくることはない。
だが俺の場合はちょっと違う。後に俺の死後のことになるが、人間どもが俺の遺伝子分析を行って調べたところ、俺は若い頃からこの方、動物蛋白ばかりを食べてきたことが分かってしまった。俺はいわば熊界のマイノリティ。偏食者、いや偏食熊であったのだ。俺がなぜそうなったか、は、自分にも、人間にもよくわからない。が、若い頃に偶然食べた鹿か何かの野生動物の肉に「味をしめて」動物偏食の道に入ったということなのだろう。ほかにも俺と一般のヒグマとは行動の様式が違っている。ほかのヒグマは、一度仕留めた獲物を土の中に隠して取りに戻ってくるのに対し、俺は、そうした行動を見せず、獲物に執着しなかった。そのために、人間界では俺のことを「食べるためではなく、快楽のために動物を襲う変質者」なのではないかという噂すら出たほどだ。が、実際の所は、俺が人間に対して、異様なほど研ぎすまされた鋭敏な感覚をもっていて、襲撃の途中でも、すこしでも何か人間の気配を感じると、あっさりと襲撃をあきらめて撤退していたのだということ他ならない。
俺の襲撃実績は、標茶町とその南の厚岸町にまたがり、2019年から2022年で31件、牛65頭にのぼった。が、2023年7月30日、釧路町オタクパウシで老いて食欲をなくし、胃の中も空っぽで牧草地にただ腰を下ろしていた俺は、まったく無抵抗で、討伐隊ではなく近くの牧場のハンターに撃たれて死んだ。しばらくは俺がOSO18であったということすら分からなかった。なので、俺の死骸は、人間の解体業者に渡され、肉の一部はジビエとして都会で食べられてしまった。
2025年5月30日
-
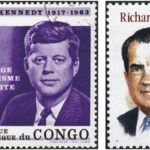
アメリカの大義(続)
アメリカ合衆国は子供たちに、どのように民主主義を刷り込んでいるかという話である。
この稿の筆者が生まれた日に、合衆国では大統領選挙があり、共和党のドワイト・アイゼンハワーが民主党のアドレイ・スチーブンソンを破り、大統領に当選した。アイゼンハワーはそれから2期8年務めた。次に共和党リチャード・ニクソン副大統領対民主党のジョン・F・ケネディマサチューセツ州選出上院議員が戦った1960年の大統領選挙の際、筆者は合衆国インディアナ州の公立小学校の2年生であった。
アメリカの公立小学校の教室では、児童たちによる大統領選挙の模擬投票がある。担任の先生が、共和・民主の正副大統領選挙候補者の応援演説をする児童を教室の中から募って本格的な討論をさせるのだが、当時この学校の家庭では共和党支持が多く、ニクソンとヘンリー・ロッジJR.共和党副大統領候補の応援者は容易に決まった。民主党もテキサス出身の児童がリンドン・ジョンソン副大統領候補の応援に立つことになり、だれも手を挙げなかったのはケネディひとり。すると担任はなぜか日本から来た筆者にケネディの応援演説を指名したのである。数日の余裕を与えられて筆者は、同じ大学構内の住宅に住む日本人の博士課程のお兄さんの所に、応援演説の知恵を借りに行った。その内容は「ニクソンは次に金門・馬祖両島が攻撃を受けたら、米国は直ちに国共内戦に軍事介入すると言っているが、ケネディはより慎重だ。自分の国日本は台湾の隣にあり、第三次世界大戦につながる衝突は避けてほしいのでケネディを応援したい」といったものだったように記憶している。現代の台湾情勢を思うにつけても、忘れがたい思い出である。
ちなみに教室の模擬選挙では共和党が圧勝したが、大人たちの大統領選挙では民主党の辛勝だったのは周知のとおりである。さて、上記の経験を通じて筆者が言いたいのは、日本の教室では公職選挙の模擬投票を実名で、しかも各党の主張を生で戦わせることなどまずない。それは日本の教員も教育委員会も、大人たちの政治に忖度してしまうからなのだろうが、民主主義の本場の国では、そんな忖度などしないということなのだ。
さて、話は少し変わるが、この1960年は南北戦争開戦百年にあたり、教室や家庭ではその話で盛り上がった記憶もある。こちらのほうもインディアナ州が北軍側であったこともあり、学校は南部への忖度なしで「北軍が正しい」と教えていたような気がする。実際には教室には黒人の児童一人と東洋人の筆者が一人いるだけであとはみな白人の児童ばかり。しかも黒人の児童は子供たちの間ではいじめにあったりはしなかったが、保護者たちの間ではやや差別的扱いを受けていた(たとえば彼の誕生会の送迎にあたり、親の迎えの車は黒人居住区の中には入らない)記憶もある。だが、教室内ではともかく「リンカーンは黒人奴隷を解放した偉い大統領」ということになっていた。筆者はといえば、当時南北戦争への認識は「戦争ごっこ」の域を出ず、家庭内のトレイや北軍の兵隊人形、砲車の玩具などを動員して、ミシシッピ川に浮かんだ北軍側のモニター砲艦を模擬して遊んでいた記憶があるくらいである。しかし、「ゲティスバーグの演説」というのはなんとなく耳に残っていて、帰国後いずれかの頃に「人民の人民による人民のための政治」というのが民主主義の本質であると教えられ「そうかあれがそうだったのか」と、気が付いた次第である。
2025年4月30日
-

アメリカの大義
I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
私はアメリカ合衆国国旗と、それが象徴する、万民のための自由と正義を備えた、神の下の分割すべからざる一国家である共和国に、忠誠を誓います
この稿の筆者が、客船氷川丸に乗ってアメリカ合衆国に渡ったのは、1959年の夏。小学校1年生の2学期が始まる頃であった。父はフルブライト奨学金のシニアスカラー(学生ではなく、日本人の若手の学者を米国に招聘する)で中西部の大学に赴任。私たち家族は父の後についての渡米で、大学の家族寮暮らし。筆者はと言えば、英語など一言も知らずに地元の公立の小学校に入学することになって、毎朝唱えさせられたのが、上記「合衆国旗への忠誠の誓い」であった。
日本の公立学校とは違い、各教室の黒板の横には必ず星条旗が立っていて、子供達は朝その旗に正対して右手を胸に当て、先生の音頭の下「アイプレジョリージェンスムニャムニャア・・」という意味不明の呪文を称えるわけである。いくら小学校1年生だと言っても、筆者だってその儀式が、米国民が国家に忠誠を誓っているらしいことくらいはよくわかる。なので、自分は日本人だから、この呪文は称えなくてもよいのかと思っていたら、担任の先生から、「あんたもやるんだよ」と言われて、有無を言わさず儀式に加わることとなった。察するところ、担任の先生に悪意があったわけではなく、米国は移民の国で、各種の民族がさまざまな手続きや枠組みで合衆国の地にやってきているわけであるから、合衆国にやってきて、その地で生活している者は広い意味ではみんな合衆国民というわけで、国旗への忠誠を誓っても別に違和感はなかったのであろう。あるいは、当時は未だ第二次世界大戦が終わって十年と少ししか経っていない頃で、クラスの子供達みんなが戦勝国アメリカの国民である中で、筆者一人敗戦国日本の国民として肩身の狭い思いをさせてはかわいそうだという思いやりがあったのかもしれない。あるいは、アメリカ人には「何でもアメリカが一番」というややお節介がましい思い込みがあるので、敗戦国のアジア人種の子供にも、米国民らしき待遇を用意してあげるのが、彼らの善意の表れであると思ってしまうようなところがあったのかもしれない。
ともあれ、この稿の筆者は、毎朝右手を胸に当て、日本人としてかすかな抵抗を感じながらも、星条旗に正対して「アイプレジョリージェンスムニャムニャア・・」と称えていたわけである。それと同時に、わずか十数年前の戦争でアメリカ合衆国(だけでなく、連合国側が)いかなる大義を持ってわれわれ枢軸側と闘い、そして勝利したかといったような理想も自然と会得し、身についていった。それは、言論や信仰の自由とともに、国家の制度に三権分立や民主主義という権力抑制装置(小学校低学年ではよくわからなかったが)を持ち、さらに「国際紛争において、力による現状変更をしない」という理想であったりもした。今日でも筆者は、上記のような大義は、たとえば日本が「大東亜共栄圏」とともに掲げたアジアの民の白色人種からの解放などというレイシズム的な理想に比較しても魅力のあるもの、そのために生命を賭すべきものであると思っている。
最後に蛇足となるが、日本国憲法の前文を日本語で読むと(当然原作者は米国人なので)、憲法にふさわしくない悪文であるとする意見があるが、この稿の筆者はこれの英文を読んで、涙が出るほどの名文だと思っている。これも「アメリカの大義」をあらわす文章の一つだからなのだろうか。2025年3月31日
-

褌と腰巻
先ず、江戸時代の中頃くらいまで、布というものは今よりはるかに貴重品であったことを書きたい。現代に住む私たちのように、毎年ユニクロあたりで新品の服を買って着るなどという贅沢は許されず、庶民は概ね古着屋で買った二、三着の服で一年を過ごしたようだ。それでも江戸時代になってからは、絹や木綿の布を着物に使う習慣が普及したが、それ以前は着物に用いる布は主として麻であった。その麻の時代に人々はどのような下着を用いていたのか、ということに興味があって、いろいろ調べてみたのだが、どうも正確な知識を提供してくれるサイトが見つからない。以下は、この稿の筆者の想像も交えて、おそらくこうであっただろうという記事と受け取っていただきたい。
絹や木綿が普及する江戸時代まで、日本では明確に下着と言えるものはなかった。男性について言えば、長めの麻の布を腰の周りにぐるぐる巻きにして、それ一枚でパンツとズボンの両方の役割を果たした。女性について言えば、都会では一種の腰巻布を用いる場合もあったが、田舎ではそもそも上衣と下衣の区別はなく、かつ陰部を隠す、あるいは陰部を守るような布の存在はなかったと考えてよいのではないか。男女いずれも「ノーパン」がスタンダードな習俗であったようだ。
さて、木綿の普及と共に、男性では六尺褌、女性では腰巻布という明確に下着の概念を持ったものが用いられるようになった。このうち、六尺褌について言えば、普及の始まりが江戸時代初期、全国の小中学校で用いられなくなったのが東京オリンピック後の1960年代と、首尾が比較的はっきりしている。日本文化の中で、ちょうどこの時期と一致するものに「武士道」というものがあって、この稿の筆者の頭の中では、六尺褌はなんとなく武士道の象徴のような位置を占めている。もちろん六尺褌の用途は武士に限らず広いものがあって、現在でもお祭りの神輿担ぎの折などには、六尺をキリリと締めた若い衆の姿を見ることが出来るし、一部私立学校の海浜学校や海辺の漁師さんなど海にかかわる人が、安全(溺れたときに船の上から救助しやすい、あるいは鱶避け)のために六尺褌を着用することは今日でも行われている。一方、明治の終わり頃徴兵制の日本陸軍の支給品としてより簡易な越中褌(三尺ほどの晒し布の片辺に紐がついているだけの褌)が採用されたことから、六尺褌に有力なライバルが生まれることとなった。たしかに軍服というものは洋装であるから、袴の中で嵩張る六尺褌よりも、ズボンの下でハンドリングが簡便な越中褌の方がより便利であったのであろう。「緊褌一番」を尊ぶ武士道精神の象徴が六尺褌であったとすれば、越中褌は徴兵制下の国民軍の象徴であったということも出来るのではないか。
次に、女性の腰巻について稿を遷したい。腰巻も、はじめは下着ではなく、夏季に上半身部分を省略し下半身部分のみを紐で腰に巻いた衣装であった。が、後に肌に直接触れる布である「湯文字」も、腰巻の類とされるようになった。1932年12月日本橋白木屋において歳末商戦のさなかに火災が発生し、従業員など14名が犠牲となった。その後の記者会見で白木屋幹部が、犠牲者が多く出たのは女性従業員が、下着として腰巻しか身につけておらず、上階から飛び降りるのを躊躇したためではないかとして、今後はズロース着用を推奨すると述べたことから、ズロース、パンティなど洋式の下着を和装の下に着けることが普及したらしい。が、犠牲者は飛び降りることを躊躇したのではなく、煙に追われて窓から飛び降り、犠牲となったのが真実のようである。白木屋が洋式下着普及のために、上記のような伝説を広めたとするうがった見方もある。2025年2月28日
-

学校
学校というものの歴史は古いが、学校教育制度というものが出来て全国津々浦々に学校が配置されるようになった(これを普通教育制度と言ったりもする)のは、概ね近代国民国家の成立と期を一にしている。たとえばヨーロッパ中世の封建制の下では、学校のオーナーは君主か教会なのであって庶民も含めてどこでも誰でもが学べる場所ではなかった。英国革命、フランス革命などを経て国民国家が形成されるに及んで、全国的且つ衆庶も対象とする、学校制度が整備されるようになったのである。初等中等の学校制度の下では、国民の識字率の向上が図られると共に、四則演算や地理、歴史、自然に関する知識など基礎的な学力が等しく国民に授けられた。我が国ではこれらの学力を「読み書き算盤」と言ったりする。こうした基礎的な学力は、先ず男子にあっては国民を徴兵し、兵士として一律に軍に動員し、あるいは平時の工場労働者として勤労にあたらせるための標準的な能力であったし、女子においても、男子が兵営に動員された後に、家庭ではなく社会の隅々で男子の代わりの役割を果たすために必要なものであった。つまり学校制度下で授けられる知識能力は、なべて国民一律同型の「標準的」なものである必要があった。個々人が多様な能力をそれぞれに伸ばしたのでは、上記のシナリオは成立しなかったことを明記しておきたい。
しかし一方で、あらゆる階層の国民に等しく基礎学力を授けるという営みには、きわめて啓蒙的な意味もあった。それまで社会的な知識を持たない故に、不当な労働に縛り付けられていた男子や、家庭において男性である父や夫に縛られてきた女性に、社会と自分との関係を見る目を開かせたのも学校が与えてくれる基礎学力であったと言える。この時代の学校を描いた様々の小説を読むと、貧しい家庭の子弟に知識を授けて自覚を促す教師の話というのが多くみられるのは、こうした学校制度の啓蒙的な意味に起因している。(山本有三「路傍の石」など)
さらに、学校は単なる知識を授与する場であるだけではなく、人格を涵養したり(アミーチス「クオレ・愛の学校」)、あるいは国民としての愛国心を訴求(ド-ディエ「最後の授業」)したりする場でもあった。我が国においては、学校は地域コミュニティーの重要な機関の一つであって、村の諸行事には、村長とならんで小学校長、郵便局長、警察署長が列座するのが通例であった。また、校歌、制帽、部活動などをつうじて、学校は、生徒の将来における兵営や工場のモデル(祖型)としての役割も果たしていたのである。
さて、この稿の筆者は、こうした学校の、国民一律同型の「標準的」な知識授受の機能(今日で言えば、学習指導要領に基づいた標準的な学力の養成)が、インターネットやAIの普及による「知の爆発」(学ぶべき知識の総量が爆発的に拡散する)によって無意味なものとなり、現代においては、従来の学校教育とは別の形の知へのアプローチが求められていることを述べたい。現在求められているのは、学校で知識そのものを授受するのではなく、真偽定かならぬ様々な情報に満ちあふれているインターネット社会の中で、どのように正しい知識に行き着くことが出来るか、その方法を学ぶことである。もちろん、その方法を学ぶために、ある種の知識の授受をモデルとした知へのアプローチの実習や演習というものは必要であろう。が、学ぶべきは知への接近の方法であって、個々人は会得した方法に基づいてそれぞれの知の世界を形成するのが、現代における新しい学校のあり方ではないかと思うのである。2024年12月27日
-

原爆許すまじ
この稿の筆者は、高校生時代の終わり頃「声なき声の会」という市民運動団体に参加していた。この団体の定例の会合は、信濃町駅の裏にある真生会館というキリスト教系の会館で開催されていたが、当時(今から半世紀以上昔)この会館では、ほかの労働組合や市民運動などの会合もよく行われていた。私たちが会合を開いていると、隣の部屋から、「がんばろう!」などの労働歌の声が聞こえてきたりすることもあった。そうした中で、筆者がとくに感銘を受けたのが、「原爆許すまじ」という歌であった。
「ふるさとの街やかれ、身よりの骨うめし焼土(やけつち)に、今は白い花咲く、ああ許すまじ原爆を、三度(みたび)許すまじ原爆を、われらの街に」i
という、どちらかというと暗鬱なメロディの歌であったが、当時は、まだ街に被爆者(ヒバクシャと片仮名で表記されていた)が多数現存されていて、原爆という悲惨な出来事を再び繰り返してはいけないという日本人の決意のようなものがよく伝わる歌であった。
さて、今月は、たとえば、「核兵器廃絶」というとき、海外の人々と我々日本人とでは、少し感覚が違うのではないかということを書きたい。要約していえば、海外の人々にとって核兵器廃絶とは、大量破壊兵器としての核兵器を使えば、人類が滅亡するという判断が根拠になっているように思うのに対して、日本人のそれは、むしろ残虐兵器としての核兵器への強い忌避感が根拠になっているように感じるのである。
以下、核兵器というものが人体にどのような影響を及ぼすものであるかを、簡単にスケッチしたい。
放射線を大量に浴びると身体に重い障害があらわれる。被曝直後には全身の脱力と吐き気、嘔吐が見られ、その後いったん症状は軽快し、約3週から2ヶ月後に脱毛と口内炎が発症する。さらに白血球や赤血球、血小板など血液細胞を作れなくなったり(造血障害)、胃や腸などの消化管の粘膜が傷んだり、脳の機能が障害されてけいれんを起こしたりする。
こうした急性障害の症状が落ち着いて5ヶ月以上たった後、がんをはじめとする晩発性障害が出現する。放射線は、また、身体を構成する細胞に損傷を与える。細胞の中では、遺伝子DNAからメッセンジャーRNAが転写されて、タンパク質が作られている。放射線の標的はDNAである。放射線はDNA二重らせんを切断する。これによって様々の遺伝子障害が惹起される。ii
つまり、放射線の被曝による人体への影響は、核兵器の爆発直後から、(もしそれを生き延びたとしても)その後の人生の長い期間に及ぶものであり、場合によっては、子孫にさえも及ぶ可能性があるのだ。
もちろん、核兵器の大量破壊兵器としての側面に目をつぶって良いということではない。世界には、人類を何回も滅ぼすことが可能なだけの核兵器が蓄積されていて、もしほんとうに核戦争が始まれば、数日を出ずして人類社会は跡形もなく消えてしまうかもしれない。だが、それにしても放射能、放射線の障害がもしなくて、核兵器がただの爆弾に過ぎなかったとするならば、核兵器が飛んできそうな都会を避けて、どこか田舎に穴こもりしていれば、万が一助かるかもしれない。だが、地球規模の核戦争がもたらすものは、地球規模の放射能、放射線障害なのであって、田舎に穴こもりしたくらいでは、避けることは出来ないのである。i 作詞 木下航二 作曲 浅田石二
ii 広島大学放射線災害医療総合支援センター「放射線を浴びたときの身体障害」
https://www.hiroshima-u.ac.jp/gensai_iryo/aboutradiation/about/effects2024年11月29日
-

後宮
今月は先ずアラビアンナイトの話から始めることにしたい。西暦750年頃に成立した、イスラム教主(カリフ)国、アッバース朝は現在のイラクのバクダードを都にした。そのバグダードの王宮に、妻に裏切られて女性不信に陥った王(カリフ)がいて、ハーレム(後宮)の中から夜ごとの相手を選び、だが朝になると口封じのために一夜の相手を殺してしまうことを繰り返していた。それをやめさせるために、大臣の娘が自ら後宮に赴き、王の相手をする際に、面白い話を語って翌朝の命をつなぎ、夜ごとの物語が千夜に及んだ時ついに王は、娘を許して妻として迎えたというのが、千夜一夜物語(アラビアンナイト)の能書きである。
イスラムに限らず、それ以前の古代オリエント、アッシリアやペルシアなどでも、一夫多妻制の文化を持つ国では、王朝にハーレムと宦官がつきものであったらしい。一夫多妻制の考え方は、権力や甲斐性があって、多数の女性を養う能力のあるものだけが多くの妻を持つことが出来るというものであって、おなじ中東由来のキリスト教やユダヤ教のように、階級や社会的立場に限らず、「神と約束した一夫一妻制」をとる宗教というのはむしろ少数派であったようだ。いずれにしても、ハーレムの存在は、一夫多妻制の文化の帰結であり、権力者が「血の純粋性」を維持するために多数の女性を後宮に隔離し、他の男性に接触させないための手段であったと言える。イスラム史上最も有名なハーレムは、テレビドラマ「オスマン帝国外伝~愛と欲望のハレム~」で知られる15~16世紀オスマン帝国のもので、コーカサス出身の美人奴隷を買い入れ、イスタンブールのトプカピ宮殿の奥に一時は千人に及ぶ後宮を形成したと言われている。この女性達を監督したのが、黒人奴隷出身の宦官であり、黒人の宦官長はやがて表の宰相に対する裏の最高権力者となっていったという。
このような、後宮と宦官のセットは、儒教文化に基づく中国の王宮にも存在した。中国においても(儒教の始祖の孔子は春秋時代の人だが、それより前の)周の時代から、一夫多妻制と、後宮への女性隔離はあったようだから、必ずしもこれは儒教文化に基づくものだけとは言えず、広く東洋の一夫多妻制文化の帰結であると言える。いずれにしても、中国の各王朝においても、後宮と宦官はつきもので、また歴史的に見ても、後宮と宦官は権力抗争の主要な要素の一つであったと言える。
ちなみに、儒教思想の下では、後宮と宦官という「裏」のシステムを経ないで、女性が「表」の権力を握ることは強く忌避された。中国史上その禁を犯して「表」の権力を握った女性は、唐の前半期に出現した則天武后(一時ではあるけれども「周」という国号を立てて女帝となった)だけであろう。
則天武后はそれ故に自己の治政下では儒教に替えて仏教を重んじたが、その死後儒教思想が復活すると、武后の世はその斬新な治政にもかかわらず、否定的にしか評価されなかった。
さて、我が国はと言えば、すくなくとも室町時代くらいまで、京都の宮廷に明確な女性隔離の思想はなかった。一夫多妻制ではあったのだが、たとえば源氏物語などを読むと、天皇が「血の純粋性」を維持するための努力を怠っていて、他の貴族が夜ひそかに后や妃の元に通ったりしている。
江戸時代、徳川氏が国内安定のために儒教秩序を導入してから、武家文化の中では「大奥」という一種の疑似後宮が生まれたが、江戸の大奥が他の東洋の国々の後宮やハーレムと決定的に異なるのは、宦官を置かなかったことである。その代わりに大奥には、将軍の妻妾とは異なる役割の女性の「年寄」が存在し、この者がかなりの程度に政治的発言力も持つことになったのである。
2024年10月31日
-

おかずとシリアル
シリアルと言うと、コーンフレークとかオートミールとか、なんだか箱に入っている朝食用の穀類で、西洋人が牛乳を掛けて食べるようなイメージがある。が、シリアルとは本来上記を含む「穀物」「穀類」という意味である。だから、我が国で言えば、白米、ご飯。中華の饅頭や餃子の皮、イタリアのパスタやピザ生地、みんな広義のシリアルである。で、今月はこの稿の筆者が、各国の食物の中では、「おかずとシリアル(穀物)」を一度に食するものが好みであるということを書きたい。以下後述をご覧いただければおわかりのように「おかずとシリアルを一度に食するもの」とは、概念としてはファーストフードにほぼ近い。
先ず我が国では、なんと言っても、おにぎり及び丼ものが「おかずとシリアル」の代表選手である。
おにぎりの起源は古く、奈良時代初期、元明天皇の詔により日本各地で編纂された「風土記」のひとつ「常陸国風土記」に「握飯(にぎりいい)」の記述が残る。また、1221年の承久の乱で、鎌倉方の武士に兵糧として梅干入りのおにぎりが配られ、これをきっかけに梅干が全国に広まったとされる。ⅰ おにぎりには丸い野球ボール型のものと三角形のものがあり、前者は帝国陸軍、後者は帝国海軍に由来するという話もある。丼ものの歴史は比較的浅く、天丼が江戸時代、カツ丼や親子丼は明治以降となる。中華料理においては、(饅頭はただのシリアルに過ぎないので)肉入りや餡入りの饅頭、春巻き、餃子等の点心類が「おかずとシリアル」の代表である。肉まんについては、諸葛孔明が南征の途上、川の氾濫を沈めるための人身御供として生きた人間の首を切り落として川に沈めるという風習を改めさせようと思い、小麦粉で練った皮に羊や豚の肉を詰めて、それを人間の頭に見立てて川に投げ込んだところ、川の氾濫が静まったという起源説話がある。ⅱ
次に西洋に移ろう。英国代表は、サンドイッチとパイ。カード博打好きのサンドイッチ伯爵の話は以前本欄に取り上げた。フランス代表は、カスクートという細長いフランスパンに、ハムやチーズを挟んだものだろうか。意外なのはドイツ代表。ハンバーガーの起源はアメリカではなく、ドイツはハンブルクで船乗りらに売られていた料理“Hamburger Rundstück”(「ハンブルクの丸いもの」という意味で、牛肉のステーキと目玉焼きを半切のパンにのせていた)がアメリカへ伝わり、「ハンバーガー」と略称されるようになったという。ⅲ もう一つのアメリカの国民食ホットドッグもドイツ由来。ホットドッグの発祥は、19世紀中盤。アメリカへやって来たドイツ移民が、フランクフルトで食べられていたソーセージ「フランクフルター」を持ち込んだことが始まりと言われている。
イタリア代表は、パスタとピザ。パスタがいつ歴史に登場したか、はっきりとしたことは分かっていない。古代ローマで主食にされたプルスという食べ物がその元祖と言われている。これは小麦やキビなどの穀物を粗挽きにし、お粥のように煮込んだもの。同じく古代ローマ時代に存在したテスタロイは、その粥を板状にして焼いたもので、ピッツァやラザーニャの原型に近いものと言われている。中世を迎えると、パスタを生のままスープに入れたり、ゆでてソースとあえるようになったと考えられている。13~14世紀のイタリアでは、パスタは一般家庭に普及するようになり、15世紀にはスパゲティの元祖ともいえる棒状の乾燥パスタが作られていたようだ。ⅳ
なお、メキシコ代表としてトウモロコシ粉のタコス、トルティーヤも忘れてはなるまい。ⅰ 一般社団法人おにぎり協会「おにぎりの歴史」 https://www.onigiri.or.jp/history
ⅱ Wikipedia 饅頭(中国) — 『事物紀原』卷九の酒醴飲食部四十六
ⅲ Wikipedia ハンバーガー
ⅳ 日清製粉グループ 小麦粉百科 パスタの起源 https://www.nisshin.com/entertainment/encyclopedia/pasta/pasta_03.html2024年9月30日
