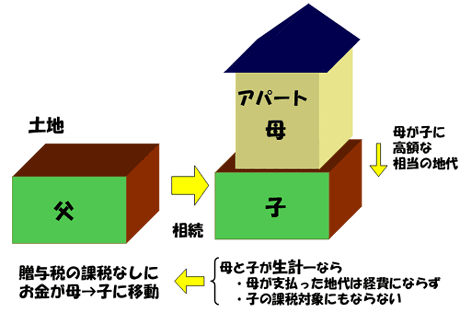「相当の地代」という言葉をご存じでしょうか?
かつて土地が右肩上がりで値上がりした時代に、法人に個人の土地の借地権部分を自然に移してしまう目的の節税策によく使われた高額の地代です。一世を風靡したこの対策もバブルが弾けてお蔵入りと思いきや、子がすでに土地を持っている場合や、二次相続対策にもこんな手法で生かせるのです。
1.かつての節税策とは…
例えば個人の土地上に法人が建物を建てる場合、よほどの田舎でもない限り、税務上は権利金の支払いが前提とされています。したがって、同族関係者間等でその支払いを免除すれば、免除されたことに対し受贈益が課税され(権利金等の認定課税という)、過酷な税負担となってしまいます。それを避ける手法の一つとして「相当の地代」方式があります。路線価等で算出した土地の更地価格の6%相当額を年間の地代とすることにより、上記の認定課税を見合わせるとするものです。当初の高額な6%もの地代を固定することで、右肩上がりの地価が次第にその負担を軽減し、ついには法人に借地権が移行するという優れものだったのです。つまり、負担が重いのは建物を建築し借地権を設定した当初だけで、地価の値上がりにより初期設定の6%は無視できる程度になっていたのです。
2.誰が 6%の地代を払えるか?
さて、地価が下落または横ばいの今の時代に6%もの地代を誰が支払うでしょう。6%ずつ支払えば、10数年で土地が買える計算です。例えば、父の相続後にその財産が母と子に移転していれば、近い将来の母親の二次相続に活用ができるのです。
子の土地に母親がアパートを建設し、その際の地代を相当の地代で支払うのです。建物の建築により、母親の相続時には建物の相続税法上の評価額が建築価格より低いという、いわゆる評価差額を利用した節税はありますが、そんなケチな事がテーマではありません。親子間で地代の支払いがなくても、税務上は法人の場合のように認定課税はありませんが、ここは敢えて母から子へ、高額な地代を支払うことにするのです。
3.同一生計の親子間での地代の取り扱い
母と子が同一生計の場合、親子間で地代を支払っても、支払った母親は必要経費にならず、また受け取った子も収入にはならないのです。実は、子の課税対象となる収入にならないというところがこの話の核心です。必要もないのに母親は子に高額な相当の地代を支払いながら、それは子の収入にはなっていません。つまり、結局は贈与税の課税がないまま合法的にお金が母から子へ移転できるという仕組みになっているのです。
ただし、そもそも必要でもない高額な地代を支払えば、それが贈与税の対象なのではないかという心配があるかも知れません。確かにこの6%の相当の地代は法人の認定課税の可否をめぐっての議論です。一般相場より高いことは紛れもない事実で、無条件には容認されない可能性もあり得る話。実務的には6%を若干下回る程度にしておいた方が無難かも知れません。
4.税務上、生計が別かどうかが判断の鍵
さて、うまい話には注意しなければならない点もありますので、確認をしておきます。その1、親子でも生計が別なら前述のような取り扱いはありません。つまり、母親の子への地代の支払いは経費となり、子は受け取った地代が収入として課税の対象になるということです。なお、税法上、生計が別か否かは、必ずしも物理的な同居かどうかということではありません。経済的にお財布が一緒なら、別居であっても税務的には生計は一。逆に、それぞれに収入がありお財布が別なら同居であっても生計が別ということもあり得ます。
5.”事業的規模”でなければならないか?
注意その2、母親がアパートを経営する場合、所得の種類としては不動産所得になります。実はこの不動産所得、ちょっと曲者でその賃貸業が事業的規模で行われているかどうかで扱いが異なるのです。この判定は、’5棟10室基準’がとりあえずの指針で、戸建てなら5棟、アパートなら10室以上が事業的と言う扱いです。しかし、これも家賃や貸付形態、契約条件等を総合的に勘案して判断する事になっており、一律の規定ではありません。
今回の手法は特に事業的規模か否かを問われることはありませんので、その意味では安心です。結局、生計一が必須の条件。
孝行息子の筆者も、母親との同居作戦でこの手法を活用したいところですが、残念ながら母はすでに他界。ただ、よーく考えてみたら、節税の元になる賃貸用の土地を持っていませんでした。