お役立ち情報
COLUMN
原則として月に一度、
代表 高木康裕が自身で執筆しております。
お客様の立場に立って、
新たな税務の情報や事例をご紹介。
辛口で税務の現場のナマの姿をお伝えして参ります!
年度:
タイトル:
-

5131号
調査にマイナス増差はない!?
相続でも重要!建物の固定資産税評価額またまた相続税調査の話で恐縮です。通常、税務調査があれば、何らかの誤りが発見され、追加の税金を納めるのが一般的。逆に税金が減る場合、調査はなかったことに……何とも理不尽な税務署のお話です。
1.相続税における建物の評価額相続税においては、財産の評価は"時価"で行うのが原則です。その時価、建物については税務署の社内規定である通達で、固定資産税評価額と言う事になっています。
さて、平成13年3月に賃貸住宅が竣工、借り主も埋まったところで5月に亡くなられたNさんのケースです。申告の期限は翌14年3月。ところが固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税です。つまり、13年の1月には竣工していないため評価はなく、14年になって初めて評価も決まり、課税となるわけなのです。結論を言えば、相続税の申告までに評価額は決まらない。こんな時は、建築価額の70%相当で評価すればいいことに。
2.意外に安い固定資産税の評価額!固定資産税の建物評価は、建物の構造や部材等により細かな評点方法が決められており、その総合評点により算出されることになっています。建築価額に比して、鉄筋系で70 ~80%程度、木造系で40~50%程度でしょうか。賃貸の場合はそこから更に3割引の評価です。正に賃貸住宅は相続対策と言われる所以。さて、Nさんの場合、建築価額は約2億円。申告に際しては、これの70%相当、1億4千万円がまずは基準です。ところが14年の5月になって固定資産税の通知が来てみると、なんと申告額との差額が6千万円もあったのです。
これはヒドイと、申告のやり直し、更正の請求と言う手続きを考えている矢先に相続税の調査の通知が。ま、こんな状態なら、万が一調査の過程で何か誤りがあったとしても、6千万円までは保険に入っているみたいなもの、と安心していたのです。が、甘かった。
3.調査にマイナス増差はない!?調査は朝から順調に進み、何事もなく終盤に。申告内容に御納得頂いてお帰りになろうとしていた時です。満を持して言い出しました。『実は建物の固定資産税評価が申告の直後2ケ月経って通知が来たのです。それによると6千万円も差額があったんですよ。更正の請求をしようと思っていたのですが、調査に来るとおっしゃる。それで、ちょうど良い機会だと思い、お待ちしていたのです。これこれの通りですので、この調査で確認して頂き、減額して下さい。』
調査官『???』。ややもして『更正の請求というのは間違った申告をした場合、一定の期間内に税額の軽減をする救済策です。本件の場合、間違った申告ではなく、建築価額の70%相当と言う適正な評価方法で算出をしているわけで、何というか、つまり、その、…』歯切れが悪い。
早い話、誤った申告をしたわけではないので減額はできないとおっしゃるのです。
調査官の気持ちが分からぬ程、こちらも野暮ではないつもりです。しかし、通知が5月になったのは、固定資産税の係の都合。こちらに非はないのです。通知が3月なら6千万も安いのに、5月だったのは運が悪かった、では済まない話ではないでしょうか?
4.仕方なく更正の請求で決着!こうなれば仕方がない。更正の請求という手続きです。ただ、その中で皮肉たっぷりに書かせて頂きました。本来、調査の過程で分かったのだから、調査額として減額すべきではないのですか、と。
当方としても、誤りではないと言われると苦しいものはありますが、どう考えても納得のいかない話。正直、行く末を案じてはおりましたが、遂にご託宣が参りました。満額回答です。6千万円減額で税額として3千万円が戻ったのです。
相続時に固定資産税評価が出ていないケースはよくあるもの。諦めず、交渉をしてご託宣に期待です!2003年4月30日
-

5130号
たまには得する『個人成り』!
新たに事業を始めるに当たり、当初は個人営業でも、ある程度の規模になれば、法人成り(会社組織にすること)はよくある話です。色々な面で有利だからでしょう。珍しいケースでしょうが、その逆、つまり個人成りで得した事例のご紹介です。
1.何故、"法人成り"が有利なのか?一般論で言えば、最大の理由は体裁というか、社会的信用とでも言うものでしょうか? 個人事業では、いかにも頼りない存在に見える点は否定できません。法人にすれば税務の面でも特典は様々です。例えば、家族を役員にして、所得の分散を図るのは国民的常識です。理論的なことは別にして、実績以上の役員報酬が支払われるのも実務ではよく見られるもの。交際費だって個人より法人の方が、限度計算はあるもののずっと認めて貰い易いのが事実です。最後に、お客様も法人のお金は何となく自分のものではないのでしょう。下世話な話で恐縮ですが、我々税理士も個人からより報酬を頂き易い。
2.会社役員Αさんの事例Αさんは都内で釣り堀とバッティングセンターを経営する会社の代表者です。事業自体は昨今の不況もあってジリ貧の大赤字。近年は満足な役員報酬も取れない程の有様でした。土地は大地主であるお父様から賃借しているものの、場所柄、有効活用とはとても言えない状況です。一時は廃業も考えたのですが、熱狂的な固定客の声援もあり、規模を半分に縮小しての営業継続となりました。残り半分にはお父様の相続対策も踏まえ、お父様名義の賃貸マンションを建設したのです。法人名義での建設も考えたのですが、所得・法人・相続税等総合的な判断からお父様個人での建設を選ばれました。
さて、地の利にも恵まれ、マンションは満室。大地主であるお父様の不動産所得は益々増え、嬉しい悲鳴の一方で、所得・住民税負担に喘ぐ結果に!
3."個人成り"でお父様の所得にすれば…ここでΑ社は赤字でお父様は大黒字の状況に一計を案じ、逆転の発想をしてみました。
それはΑ社をお父様の個人事業にしてしまうことなのです。所得状況を下記の場合で考えてみましょう。お父様の不動産所得
Αさんの会社の所得40,000千円
△10,000千円言うまでもなく、このままでは両者は別々の人格。利益と損失を通算できるはずもありません。しかし、話を非常に単純に割り切って、Αさんの会社の所得をお父様個人の事業所得と考えてみましょう。
お父様の不動産所得
お父様の事業所得40,000千円
△10,000千円これならお父様の所得として通算ができ、差し引き30,000千円の所得です。しかも、事業の部分は実質的にΑさんが専属で行うわけで、お父様の青色事業専従者と言う立場も可能です。つまり、お父様から給料を貰い、その分が経費になると言う仕組みです。仮にΑさんの給料を年間で12,000千円とすれば、お父様の所得は30,000千円-12,000千円で18,000千円と激減し、全体でうまく所得の分散ができることになるのです。今までΑ社から満足な役員報酬も取れなかったΑさんも大喜び、次代への所得の移転が意外な形で実現できました。
4.やっかいな借地権の存在実は個人なりに当たり、一つ避けて通れない問題がありました。お父様から賃借している土地の一部にΑ社の借地権が存在していることです。こうなると、不用意に会社を清算すると、清算所得という課税があり得るのです。そこで、会社の存続を前提に借地部分の底地をお父様から取得することに。但しΑ社にお金はないためお父様から無償で贈与を受けました。ただ、これは受贈益と言って、本来はΑ社に法人税がかかるのですが、累積赤字と通算です。つまり、法人税の課税はなく、同時にお父様の底地という財産が減少することで相続対策にも寄与することになったのです。尤もお父様は法人に無償で贈与した場合、詳細は省きますがみなし譲渡と言う譲渡課税がなされます。しかし、相続税の最高税率に比較して約半分、不利な話ではないのです。これでΑ社は建物と借地権でない完全な所有権である土地を有する会社にはなったものの、実態実業がありません。Αさんの奥様が主催する陶芸教室運営のB社と合併し(Α社はB社に吸収)B社が土地建物の所有者としてお父様に建物を賃貸したのです。
この結果、お父様は地主であると共に釣り堀とバッティングセンターを個人営業で主催。これで前述のように赤字と黒字の通算ができ、更にB社に家賃を払うことで経費が増大。その家賃はB社に入り、Αさんの奥様の役員報酬の原資になっているわけです。何ともでき過ぎな個人成り。いつでも会社さえ作れば良いと言う単純なものではないものの、この日本、会社があればやっぱり色々便利です。2003年3月28日
-

5129号
えっ!年明けに相続税調査?
今年は何という年なのでしょう?年明け早々、税務署から立て続けに3件も相続税調査の連絡が入ったのです。確定申告が目前という時期に、です。
税務署の恨みを買い、狙い撃ちにあう程悪いことはしていない筈なのですが…
1.特官部門は例外です以前にも税務署の調査のスケジュールはお話したと思います。東京局の場合、相続税は8月までの申告期限分について、通常は9月から年末までが調査の時期。例えば10月が申告期限なら、調査はその年はなく、翌年の9月以降となるわけです。逆に言えば、昨年8月末までの分は、年が明けた今は調査は無しと考えて差し支えないのです。が、しかし、一つの例外あり!通称、特官部門がそれで、特別国税調査官とそれを補佐する調査官から構成されます。資産税だけでなく、法人税にも所得税にもありますが、要は大口事案や困難事案を処理する面々。
相続について言えば、超大口資産家と呼ばれる方々を管理し、調査するのです。一般部門では、年が明ければ譲渡事案の呼び出しや、贈与のチェック等確定申告の準備に大童の季節。が、特官部門はそんな細かな仕事はやりません。ひたすら大口困難事案の追求、調査なのです。
つまり、冒頭の3件の調査は、総て超大口資産家の方々だったのです。
2.短期決戦、急ぐ結論!税務署には事務年度なるものがあります。7月の異動時期を皮切りに、12月末までが最も重要な調査の成果の評価時期なのです。相続に限って言えば、顕著な調査結果が出ると見込まれるものは、当然ながら年内に調査。美味しいものから順に手掛けるのは調査の定石で、年明け後の調査は言ってみればオマケの世界。従って調査も重点を絞り、短期決戦です。中には調査においでになるなり、一枚のメモ用紙を差し出し、『本日の調査の確認事項は別紙の通りです。調べて後日、税理士の先生を通じてご回答下さい。これにて本日の調査終了』と、僅か30分でご帰還になったものまでありました。通常は丸1日かけ、あれこれ質問、家捜しするにも関わらず。そして、当局の見込み違いと判明するや、即刻調査は終了です。
筆者も税務の世界に身を置くこと20数年になります。が、あんな調査は自身やったこともなければ、立ち会ったことも初めてでした。効率的で早く終わることは有り難いけど、何とも拍子抜けの感は否めません。やっぱり手抜き工事かも?
3.保険会社の資料箋は要注意!今回の税務調査で共通の項目、それは保険会社の資料箋です。税務署は個人法人を問わず、納税者に関する様々な税務的、経済的な情報を収集しています。誰がいつどんな事情でお金を支払った、又は収受したと言うことを。これを資料箋と言い、調査の時に活用、資料箋に記載の事項が申告に反映されているかを確認するのです。
昨今、生命保険会社からの資料収集が活発なのでしょうか?今回のいずれの事案も狙い目は生命保険でした。ただ、当局の目の付け所に?マークの付くものも。バブル当時の悪名高き変額保険がそれ。当時、銀行が土地を担保に融資を実行、変額保険を盛んに売った時期がありました。この商品、大半の方が大損をし、リスクについての説明不足で裁判沙汰になったのは周知の事実。興味深いのは、今回の調査で保険会社と銀行相手に訴訟をし、最終的には両者と和解した事例です。和解の条件として、銀行借り入れを実質的に保険会社が低利で肩代わりしたため、お客様口座にその入金がなされました。驚いた事にそれが税務署の知るところに。賠償金だとでも思ったのでしょうか?
お客様にしてみれば、借入先が銀行から低利の保険会社に変わっただけ。債務の欄に計上はあるものの、税務署が期待するように、賠償金ではないので財産としての計上などあるはずもありません。それを不審に思っての調査の選定だったのです。事情を説明し、御納得頂いた上でお引き取り願いました。大体、バブル当時の変額保険で儲かった方などどれ位いるのでしょうか?保険会社から入金あれば直ぐ財産だと考えるのは、あまりに早計。選定理由がこれだけなら、忙しいこの時期、調査でなくて税理士を税務署に呼びつけ、確認させれば済んだのです。
お陰様でいずれの事案も無事、事なきを得、調査は終了でした。が、壁に耳あり障子に目あり。色々な所に税務署の目は光っていることを、改めて感じさせてくれる今日この頃です。2003年2月27日
-

5128号
話題沸騰“変額年金保険”
今や資産を取り巻く環境は、劣悪、極悪、非常に厳しいものがあります。そんな中、考え方、使い方によっては面白い商品が話題です。その名も変額年金保険。【変額保険】と聞いただけで虫ずが走る方もいらっしゃるのでは…しかし、時代は変わりました。誤解の前にしっかり理解、図解で納得、最後にお得は如何でしょう?
1.なかなか増えない低金利まず、今の預貯金を2倍にするのにどれ位の年数が必要か、お分かりでしょうか?《72÷金利》と言う算式で算出ができるのです。
年金利が0.1%で720年、0.5%で144年、1.0%でやっと72年、10年で2倍になった時代もあったのに、です。そうは言っても元本保証の預貯金は一見すると安全確実。問題は、預貯金では"額"を保証はしても、その時代に合った"価値"までをも保証するものではないと言うことです。同じ100万円も今と昔では天と地ほど差があるのです。一方、年金だってこの先当てにはなりません。要は額ではなくて価値なのです。
2.変額年金の仕組みそこで興味深いのが変額年金保険です。仕組みはいたって簡単。契約締結時に一時払保険料を支払い、後は10年以上の期間で自由に積立期間を設定です。積み立てが終了すれば年金として受給ができますが、それはその間の運用実績によって多くも少なくも、まさしく変額年金。もし、積立期間中に死亡した場合には、保険金として初回支払い済みの金額が保証され、その時点での運用実績によってはプラスαも期待が可能。目玉は積み立て終了後の年金の受取り方法で、保証期間付終身年金や期間を定めた確定年金、一括受取り等好みや目的に応じて自在です。
3.税法上のメリット1初回払い込みの保険料は、積立期間中は基本保険金としていわば元本保証。商品は保険ではなく、あくまで年金のため、かなりの高齢者でも購入可能です。例えば当初保険料1億円を預金取り崩しで支払い、1年後に死亡なら、その時点で1億円の保険金。税務上の評価は死亡保険金で、500万円×法定相続人の数に相当する金額は非課税です。預金ならばそのまま1億円の評価、どっちが得かは一目瞭然。
3.税法上のメリット2例えばご本人を年金受取人、被保険者としてご自身が契約者となった場合です。年金原資が1億円、80才で年金受給を開始の20年確定年金を選び、85才で死亡と仮定しましょう。年金額は年519万円を6年受給で3114万円、残り7266万円を遺族が引き続き年金で受給すると、税務上は勿論相続財産扱い。が、遺族が受け取る年金の評価が面白い。下表のように残存年数により、年金総額に一定率を乗じた金額、このケースでは50%、3633万円の評価なのです。早い話半額評価、これらはホンの一例で、まだまだ工夫は色々です。これらの商品、保険会社はもとより、銀行、証券会社等々で扱っており、内容も千差万別、素人判断は危険です。そうか、やっぱり○○○財産相談室で相談か!
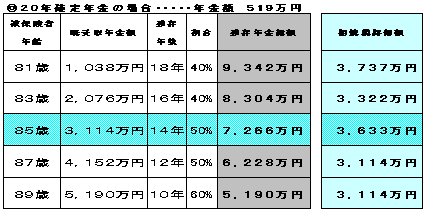
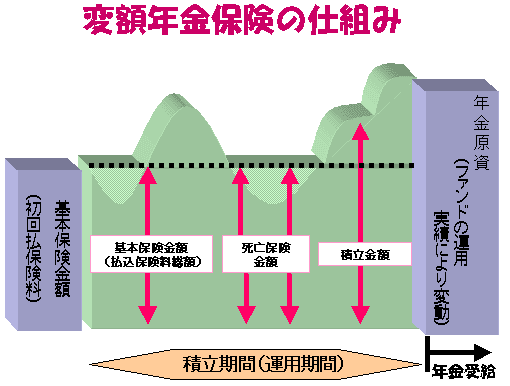
2003年1月30日
-

5127号
新制度の生前贈与、ホントにお得?
平成15年度の税制改正については、先週送信の"え~っと通信"のとおりです。その中で、特に資産家の方からは、相続税と贈与税の一体化にご質問が集中でした。そこで、再びこのテーマ(ATO通信5124号参照)でその損得勘定を検証です。
1.新制度はこんな内容まずは復習ですが制度の概要から。
『相続時精算課税制度』と言う呼称になりそうです。65歳以上の親が20歳以上の子に贈与する場合、2500万円までは非課税(住宅資金については更に1000万円を上乗せで3500万円)です。これを超える贈与についても、一律20%の贈与税だけ。贈与の回数、一回の金額等は無制限で何度でも。贈与をすれば毎年申告が必要ではあるものの、これだけ聞けば何ともお得な税制です。但し、ここで贈与した財産は、相続時にはもう一度相続財産として課税され、相続税を算出です。そして既に納めた20%の贈与税部分はこの相続税から控除される仕組みです。なお、従来からの110万円の基礎控除の贈与税がなくなるわけではありません。新制度との選択制です。
2.価格が上がれば得、下がれば損!さて、この新制度、相続時に相続税として計算される場合、贈与時の価格で計算です。例えば、贈与時には1000万円で評価され非課税枠に収まっていたとします。実際の相続時にこの財産が5000万円になっていたとしても、相続税の計算はあくまで贈与時の1000万円。結果、4000万円は得したことになるわけです。逆に相続時に50万円に下がっていても、やっぱり計算上は1000万円。つまり、贈与時より相続時に価格が上がればお得、下がれば損となるわけです。一般論として、資産家の方にはお勧めできる制度ではなさそうです。価格が一定と仮定すれば、結局はただの前払い、損も得もないからです。つまり、上がるも下がるもギャンブルなのです。
3.確実な従来型贈与それならば、確実に従来型の110万円の基礎控除方式で積み重ねた方が安全かも知れません。従来型の贈与税も税率はかなり負担軽減で最高税率50%。来年からは310万円の贈与で20万円、1000万円で231万円の税額です。
また、極め付きはこの新制度、いったん選択をした場合、二度と従来型の110万円の基礎控除の贈与には戻れません。前述の通り、1万円でも2万円でもその都度申告が必要で、勿論、非課税枠を超えていれば20%相当の贈与税、この場合なら1000円、2000円の贈与税の納税です。ただ、この制度を利用すれば、大規模な賃貸マンション等収益物件を生前贈与して、収益そのものを子に移転させ、納税資金を確保させることは可能です。
さて、ここで一つ心配なことがあります。贈与をした子供が親より先に亡くなった場合はどうなるのでしょう?現時点で税制改正大綱上は明らかになっていませんが、子供の相続人に承継させる方向ではあるようです。なお、贈与を受けるのは、実子に限定されず、孫養子を含む養子も可能です。
4.名義預金への影響相続税の調査で必ず問題になるのが名義預金です。名義預金とは、名義上は被相続人の名義ではなく、妻や子になってはいても、実質的に被相続人の財産と推定される預金を言います。実務上は真実誰のものかの特定は非常に難しく、だからこそ、調査においては常に確認事項とされるのです。
新制度においては、1万円でも2万円でも申告が必要です。となれば、この制度を選択した場合、結局は最期に相続財産として課税されるわけで、実質的に贈与ができないことと同じ結果になってしまいます。
従来型の贈与税は5年で時効が完成、成立です。だからこそ、前述の相続税調査において、名義預金が誰の預金かについては、贈与の有無を含め議論沸騰です。正に喧々囂々、侃々諤々(けんけんごうごう,かんかんがくがく)税務署とやり合うことに!実務的な話をすれば、極端な例は別として、一定額については名義預金は認められ、相続財産からは外れる事も多いもの。新制度なら、贈与と申告すれば勿論最終的に相続財産。贈与と申告しなければ、当初より相続財産。税務署は調査がやり易くなることだけは確実です。2002年12月27日
-

5126号
最新物納事情
相続税の納税方法として、物納は今も昔もその重要性に変わりはありません。が、こんな物納もあり?と言う珍しい事例のご紹介、題して最新物納事情、です。
1.駐車場を物納すると…お客様の中には、収益性は多少悪くても、将来の納税用のために駐車場を経営しておられる方も多いもの。駐車場なら物納するも良し、売却だっていつでもできる、こう考えての選択です。勿論、これはこれで正しい考え方、準備の仕方です。
さて、実際に駐車場を物納すると、どういう手続きになるのでしょう?通常は現地の確認調査で、契約車両を2~3ケ月以内に解約する指示が出されます。また、隣地境界、道路査定等々細かな指示も同時です。いずれにせよ、契約の解除で収入はストップです。
2.地域の特性、駐車場不足今回の駐車場物納は、ちょっと様子が違っていました。実はこの物納で一番困るのは地域住民。何故なら駐車場が極端に不足している地域だったのです。通常、物納が許可され収納されれば、国はその土地を売却します。一方、その土地の購入者、普通は建物を建築した上での有効活用を考えるでしょう。駐車場経営などしないと考えて間違いありません。となれば、物納イコール駐車場が無くなることを意味するのです。物納申請のお客様、自らこの窮状を当局に訴えました。何とか駐車場を残せるよう、かなり大きな声で当局と交渉をしたのです。世の中、駄目もとで何でもやってみるものなのでしょう。何と、物納許可にあたり、次のような条件提示が…
3.有り難き、物納許可条件土地は収納し国有地とするが、一定の条件で従前の土地所有者に賃貸する。その上で、駐車場経営を継続してよいと言うものなのです。その条件とは路線価による更地評価の1.85%の年間地代、金額にしておよそ月20万円の支払いです。ただ、従来の駐車場収入は総数30台弱で月25万円のため、この利ざやでは旨みはありません。そこで、駐車場顧客とも再契約の条件提示をし、4割アップ月35万円の引き上げに成功。これで1億円以上の納税が物納で完結し、しかも、駐車場収入まで確保です。
それにしても、お役所と言うところ、本当に商売には無縁の所のようです。私なら、管理は業者に任せるとして、国営駐車場を経営します。上記の例で、本来35万円の駐車場収入が見込めるにも関わらず、20万円の地代で良しとするのですから。
もっとも土地の収納価格については、更地評価ではあるものの、[短期賃借権]が付着するため2.5%は控除するとのこと。結構、細かなところはしっかりしています。
4.長期間放置の物納案件はウヤムヤで収納こんな物納申請もありました。隣接する2つの土地がその候補です。1つはアパート敷地の底地部分、もう1つは駐車場です。当局から指摘された事項は総て整理し、後はアパート敷地をどこまでで線引きするかの指示待ち状況。そして、許可を待つこと、何と7年が経過です。前任の担当者が忘れていたのでしょうか?真相は定かではないものの、今年になって担当者が変わり、突然お詫びの電話が。年内に処理をするので、もう一度図面をと言われ、上記線引きの指示を再度求めたのです。その結果、建ぺい率と容積率さえ充足していれば、とりあえず認めるとのお達し。当初は消防法で建物から相当程度離れていなければ、許可するしないでうるさいことを言っていたのにです。
因みにこの7年間、当然ではありますが物納申請前と同様、アパート収入はお客様に。ま、7年でなく、100年でも急ぎはしなかったのですが…尤も物納が却下であれば、その期間の延納金利を負担することにはなります。それでも家賃収入は入るわけで、やっぱりのんびりやって頂いた方が有り難い。お役所と言う所、何ともおうよう鷹揚と言うか、ふところ懐が広いというか、文字通り親方日の丸です。普通のビジネス感覚で仕事をする筆者には理解ができません。2002年11月29日
-

5125号
良い人に出会えれば、評価は下がります!
相続税の土地評価が、一般論としては路線価を基に行われることは、広く知られていることでしょう。しかし、路線価によらず鑑定評価を利用することもよくあること。そこで今回は、路線価評価の限界と、どんな時に鑑定を利用すべきか、実務の世界のご紹介です。
1.路線価は法律に非ず財産の評価は『時価』で行うこと、これは相続税法という法律です。しかし、路線価で行うべきとは規定していません。税務職員が遵守すべき、いわゆる社内規定である通達の中で、路線価が時価だと言っているに過ぎません。つまり、他に時価であることを立証できるものがあれば、当然それも認められ、鑑定もその手段の一つなのです。
2.路線価評価の限界路線価評価と言うより、正しくは財産評価基本通達と言うべきでしょう。財産の細かな評価方法の規定集が税務署には用意されています。その中で土地については、間口、奥行き、形状、接道状況等により評価額が増減される仕組みです。なかなか工夫はしてあるものの、個別事情によっては実態と合わないものがいくつかあるのが現実。その場合には、この評価通達を採用せず、鑑定を利用する方が得策なのです。いくつか具体例を挙げてみましょう。
①無道路地図Aの斜線部分土地イのように、道路に接してないような状況です。他人の土地を通らなければ、利用ができない土地が何と土地ロの6割以上の評価とされてしまうのです。道路に接していなければ、単独では建物も建てられないにもかかわらず、です。
実際には売れもしない価額で評価され、税金まで課税されるのに、最大4割引で我慢すべきなのでしょうか?
②がけ地これは説明するまでもないでしょう。基本的には使えない、がけ地部分の面積割合やがけ地の向きにより、最小で53%評価。 がけ地部分はほとんど使えないのに、です。
③不整形地図Bのように使い難い変形した土地のこと。点線のような本来あるべき整形な土地を想定し、斜線の部分の割合により、これも頑張って60%評価。でもこんな土地、どうやって使ったらいいのでしょう?くどいようですが、評価されればそれに課税されるのです。
④接道義務を満たさない土地極め付けが図Cです。土地というのは最低2mは道路に接していないと、法律上、建物が建てられないのです。つまり、1.5mの接道状況では、利用価値はほとんどなく、売却できるとすれば、隣地の所有者くらいでしょうか?ところが税務署はこの実態を理解していません。1.5mなら、差額50㎝分を購入するのに必要な資金分を評価額から控除すれば済むと言うのです。何たる無知!差額50㎝分を必ず買えるかどうかも解らないのに… あまりに殺生です!
3.難しい"鑑定士"選び!上記のような状況なら、場合によっては鑑定評価で限りなくゼロに近い価額も夢ではありません。それが鑑定の魅力です。が、この鑑定士選びが難しい。ある事案で鑑定士A氏に相談したら評価通達と大差なく、鑑定士B氏は大幅に下がると!基より唯一無二の評価額など存在せず、鑑定の考え方も色々です。 また、鑑定に基づく申告に対しては税務署も鑑定を取り、その適否を判定です。迷った挙げ句、否認されるリスクを承知でB氏の鑑定で申告をし、事なきを得ました。もしも、A氏を信用して高い税金を払っていたら…人との出会いが人生の総て。そう言えば、医者、弁護士、そして税理士、みな然り。『あなたに出会えて良かった』と若い女性のみならず、総てのお客様から言われる事が筆者の願いです。
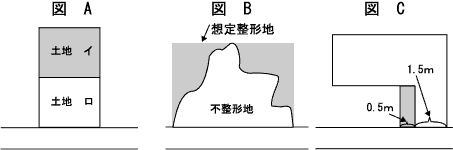
2002年10月30日
-

5124号
実現するか、相続税・贈与税の一体化
今、資産家の間で話題の中心になっているのは、相続税と贈与税の一体化でしょう。税制改正がどういう形になるか、現時点では未定ですが、概ね以下のような方向になりそうです。しかし、意外な問題点もありそうで……
1.現行制度の概要現行の相続税と贈与税、基本的には別々の課税体系です。生前に贈与税が課税された財産は相続税の対象にはなりません。但し、これを無制限に許すと、死亡直前に過度の贈与により相続税の回避が可能になることも。そこで、相続開始前3年以内の贈与は、いったん贈与がなかったことにして相続税を課税し、相続税額から既に納めた贈与税額を控除する方法(通称、3年内加算)をとっています。
2.新税制は選択制新制度では従来どおりの方法も残る見込みです。ただ、新たにいわば無期限の3年内加算に似た制度を選択できるようにしようとしています。つまり、生前の贈与時には贈与税額を軽減して贈与を促進。相続時には生前の贈与財産も総て相続財産として取り込んで相続税額を算出します。そこから、それまでに納めた贈与税を控除した額が最終的な相続税というもので、いわば3年内加算の拡大版。(下図参照)
制度の選択は納税者ごとに別々にする事も可能で、贈与の金額や回数も制限しない方向とか。但し、贈与者は65歳以上に限定されそうです。
3.新制度の問題点この新制度、あくまでも相続税と贈与税は一体化で、生前贈与を相続時に精算するという立場に立っています。つまり、いくら生前に贈与を行っても、結局は相続時に課税するわけで、従前のように生前に色々な工夫で贈与をしても、結果は同じだと言わんばかりなのです。
しかし、65歳以上の贈与という限定はあっても、贈与から実際の相続までに何十年もの間隔が空くことだってあり得ます。その間に時の経過による資産価値の変化、税率や基礎控除額の変更、インフレ・デフレの影響等々をどのように調整するのでしょうか?
贈与時に100万円で評価された財産は、何十年後に実質1000万円に高騰していても、逆に1万円に暴落していても、相続財産としては当初の100万円で課税する事になってしまいます。
正にギャンブル、吉と出るか凶と出るか、各自の責任と判断に委ねられることに。
更に議論を進めれば、生前贈与時の財産の評価額やその時の税率にもよるでしょうが、生前贈与の税額の合計額が相続税額を超えることもあるでしょう。その場合には、相続時にその超過額が還付される結果もあるのです。相続税は苦労して納めるもの、こんな常識が通用しない日が来ることも夢ではありません。
4.注意すべき、『伝家の宝刀』昔から節税と課税強化はいたちごっこです。
税理士がお客様のために悪知恵(?)を働かせれば、そうはさせじと課税当局が税法、通達を改正する、こんな事の繰り返しです。
ただ、従来は何とか工夫して低い価額で贈与をすれば、後々の相続で課税されることは原則的にはありませんでした。相続税と贈与税は基本的には別々の課税体系ですから。しかし、今後はそう簡単な割り切りは禁物です。贈与も最後の相続で精算が基本なのです。当局の得意技、"課税上弊害のある場合には、原則的な課税計算をしないこともできる"と言う包括規定が働くのです。当局にとっては伝家の宝刀。税調資料にも、『租税回避防止措置を確保する』ことが強く謳われています。まじめに納税、少しは節税、これが庶民の処世術と心得ましょう!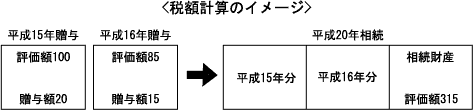
課税される財産 100+85+315=500 相続税額 500に対する税額-(20+15) 2002年9月30日
-

5123号
誰が何を相続すれば良いのか?
相続で最も難しいことは、昔も今も財産の分割方法です。つまり、誰が何を相続するかです。各人に明確な希望がある場合は、相続人の方々の話し合い次第。まとまるかどうかは別として、ある意味では単純明快、解りやすいのです。逆に結構難しいのは、どう分けたらいいか、と言う根本的な問題をご相談賜る場合です。皆さんの財産ですからご自由に、と突き放してはお叱りを受ける事に。で、税務の立場からご参考までに二つ三つ。
1.居住用土地は奥様に!相続税の大きな特例に、小規模宅地等の評価減の特例と言うものがあります。一定の条件を満たした居住用、事業用等の土地の評価について、最大で8割引の減額をするものです。例えば本来1億円のご自宅の評価が、最大で2千万円にまで引き下げられるわけで、誰がどういう風に適用するかは各人の納税プランに大きく影響してきます。
そこで、この特例、居住用の土地で適用するなら、ご主人の相続時には奥様が相続することをお勧めです。次回、奥様の相続時にも、居住用として再度お子様がこの特例を適用できるからです。
2.不動産か預金か?賃貸アパートやマンションと現金預金と、どちらを相続する方が有利か、もよくお尋ね頂く質問です。賃貸物件は維持管理に手間暇がかかる代わりに、収益が得られます。片や現預金はそのものズバリ、手間いらず。
筆者の個人的な好みから言えば、賃貸不動産でしょうか。理由は簡単、利回りです。預金の利息は無いに等しく、ペイオフ対策と言う考え方だって成り立ちます。ただ、事業にリスクはつきもので、賃料の値下がりや空室リスク、建物建築時の借り入れまでセットの相続なら、なおさら面倒な側面も。そんな状況から、跡継ぎの長男が不動産を、嫁いだ娘が現預金を、と言うパターンはよくある話。
さて、相続税の計算は相続財産の総額を基にいったん法定相続分で税額の総額計算をします。その上で、実際の相続割合により、その総額を按分して負担することになっています。ただ、この按分計算がくせ者で、相続税法上の評価額で計算です。つまり、現預金の評価は正にその金額ですが、建物については建築価額よりはるかに安い固定資産税の評価額。しかも賃貸物件は更にその7割評価になるのです。現預金より評価上は得をして、税負担が少なく、その後の収益までをもゲット。物件にもよりますが、私ならリスクは覚悟でやっぱり不動産です。
3.底地は本当に不良資産か?借地人のいる土地、つまり底地は自由に処分もできません。絵に描いた餅とまでは言わないまでも、昔から一般的には不良資産と言われています。 そのため、相続時には物納の最有力候補。
しかし、本当に不良資産なのでしょうか? ものは考えようで、こんな地主さんがいらっしゃいました。相続税の納税に底地の物納をお勧めしたのです。相続財産としては底地が大半で、駐車場やアパートが若干あり、納税手段としては底地の物納が常識的、かつ、安全、妥当な方法だからです。
が、この地主さんは物納を拒否し、20年の延納を選んだのです。底地は毎月確実な地代と言う現金収入を生む大切な財産。利回りを考えれば預金利息より有利、とのお考えなのです。そして何より、何年かに一度は、まとまった更新料なるおまけまでが付いてくると言うのです。この地主さんの場合、地代も決して低くはありませんでした。 滞納のない借地人であれば、確かにこの地主さんの主張も頷けます。その意味では底地もあながちバカにはできない財産です。また、そもそも地代水準が低過ぎると、物納だって認められません。物納のためではなくても、地代引上げは必須です。
4.解決手段はお金だけ!結論として、財産の種類による有利不利は税務上の問題より、好みの問題と言うに尽きます。
そして何より真に公平で相続人全員が100%満足する分割方法など、存在し得ません。結局、不満の穴埋めは代償分割を含め、お金で解決するより方法はないのです。そのためには、評価上多少不利ではあっても、相続人のため、現預金をなるべく多く残すこと。それができなければ、換金化できる状態にしておくことが、相続人への思いやりというものです。残念ながら娑婆(しゃば)の世界は最後の最後まで、金、金、金で解決のようですから。2002年8月29日
-

5122号
毛利元就に見る相続対策の是非
-相続における会社株式の分割方法-毛利元就と言えば、『3本の矢』の話があまりに有名。1人では不足でも、兄弟3人力を合わせれば、強力になることを3本の矢に例えて協力せよとの教えです。この教え、一般論としては勿論疑いのない真実でも、相続対策として見た時は、実はちょっと気に掛かることもあるのです。
とりわけ、上場していない会社の株式を、子のうち誰が相続するか、誰が経営権を握るかは、3本の矢ほど純粋な協力論だけでは片づきません。大所高所からではなく、世間によくある実例(お客様のご了解済み)から税務の立場で検討してみることにしましょう。
1.不採算部門の切り離しKさんは自動車整備工場に併設して、ガソリンスタンドを経営しています。二人の息子のうち、長男が整備を次男がスタンドを担当しています。整備部門はそこそこの利益が維持できるものの、ご多分に漏れずスタンド経営は非常に厳しい状況です。スタンドの赤字を整備で埋めているのが実態と言ってもいいでしょう。Kさんが全株式を持っていますが、将来の相続を考えると心配なことが二つあります。一つはKさん亡き後、二人が本当に協力しあって会社を盛り立てていけるか、とりわけスタンドは整備部門にオンブにダッコの状況です。もう一点は事業規模に比較して会社保有の賃貸不動産がかなりあり、株価が評価上はかなり高額となる相続税法上の心配です。
このケース、税務上の見地だけから見た場合はその解決策もいたって簡単。採算の悪いスタンドは閉鎖です。道路沿いで立地も良いことから、貸店舗とすればかなりの家賃収入が見込めます。その上で整備と賃貸の両部門を会社分割の手法で別会社に。税法上の要件はありますが、昨今は大きな税負担もなく2社への分割が可能なのです。ただ、株式は従前通り両社とも全株を現社長が保有することが条件です。そして、万一の時は整備会社を長男、賃貸不動産会社を次男が相続し、それぞれが独立して経営を掌握していけばよいのです。また、ここでは詳述いたしませんが、会社分割により全体としての株価の引き下げも可能なのです。
実際にはこのプラン、次男が大反対で宙に浮いたままの状態です。長年手塩にかけてきたスタンドを閉鎖し、従業員を解雇するのは身を切るよりも辛いというのが理由です。仮に閉鎖はしなくても、整備と切り離されれば経営上は早晩衰退も目に見えているのです。次男の気持ちも分かります。
理屈としては理解できても、現実の閉鎖は気持ちの上ではそれ程容易ではありません。ただ、実際の相続税額を直視してみれば、このままで良いはずはありません。しばし時間が必要と言うことでしょうか?
2.株式は集中、原則通りの分割に見る美談!Fさんは80歳の高齢ながら、建設資材製造業を営む現役の社長です。将来の相続をも視野に入れ、自社株式を後継者たる息子に贈与を繰り返し、凡そ1/3程を移転済みの状況でした。そんなある日、息子が急死してしまったのです。息子夫婦には子が無く、相続人は妻とFさんら両親の計3人。Fさんの援助もあり、息子にも上記株式の他、それなりの蓄財ができてはいました。ただ、将来を託していた子を亡くしたFさんの悲しみは、想像するだに胸を締め付けられるものがあります。そんな中、財産の分割について、Fさんは毅然とした態度で息子の嫁にこう言ったのです。『息子亡き後、お前が経済的に困らないよう、親として会社として、最大限のことはさせて貰う。不動産はじめ預金に至るまで私達は何ら相続するつもりなどない。但し、株式だけは社長として私が相続したい。』と。これでいいのです。いや、会社の社長としては、本来こうしなければならないのです。株式は絶対に分散させてはならないのです。娘婿も会社経営に従事しており、息子に子が無い以上、ひとまずF家に集中させ、徒に分散させないことが肝要です。表面的な公平など無用です。また、お嫁さんとて経営に興味もなく株式など関心外。現実面で今後の生活を配慮してくれるFさんに対し、感謝の気持ちは大きいことでしょう。
もとより兄弟は力を合わせて協力すべきです。が、会社経営はそれ程単純ではなく、兄弟は他人の始まりくらいの認識で当たるべきもの。権力と株式は集中させた方がうまくいく事が多いのかも知れません。3本の矢も元就の真意は協力の勧めではなく、毛利家衰退の危機に対する警鐘であったとか。両雄並び立たず、寂しくとも、辛くとも、トップは一人で奮闘、決断すべきなのです。2002年7月29日
-

5121号
青色専従者給与の是正!
-管理会社否認の悪夢再び・・・-古い話で恐縮です。筆者が税務職員だった20年位前のことでしょうか、当時、所得税の節税策の花形だった方式を一斉に否認、是正指導した項目があります。個人の不動産について、名ばかりの管理をする同族会社への管理料の支払です。
それをほうふつ彷彿とさせる事態が昨今、税務署に起こっているようです。ただ、今回の当局のテーマは同じ個人の不動産所得でも、『青色専従者給与』の否認。事態は結構と言うか相当に深刻です。
1.不文律の20%基準当時、目に余る不動産管理会社方式に税務署は一定の歯止めを掛けようと、管理の実態の把握に懸命でした。一言に管理と言っても内容は多岐にわたり、清掃業務からエレベーターの保守、入居者の賃料回収等々。外部に依頼した場合の管理料も千差万別。結論として概ね収入の10%を実数とはじき、余裕を持たせて20%基準を打ち出しました。そして、20%を超える管理料を次々と是正させていったのです。但し、法律ではないため強制力はなく、あくまで"指導"の名の下に。
2.青色専従者給与の実態さて、個人の不動産所得において、同居の親族等に給与を支払っても、原則的には必要経費になりません。但し、事業的規模の家賃・地代等の収入がある場合、青色申告を選択していれば特例的にそれらの親族への給与の支払いが経費計上を認められるのです。青色専従者給与と言って、青色申告の大きな特典の一つとなっています。
この青色専従者給与、本来の趣旨は学生以外の15歳以上の家族従業員に、専らその事業に従事した労働の対価として支払われるべきもの。単に家族名義で給与を支給すれば、それで経費として認められるものでは勿論ありません。が、実態として、特に不動産所得については、何もしない妻や子に給与を支給しているケースは多いもの。
税務署もこの事に気づいてはいたものの、従来はあまり極端なもの以外は黙認の状況でした。それが昨今、会計検査院からの指摘を受け、かなりの勢いで是正をさせるようになっているようです。
3.調査で聞かれることは…現場の調査でこれを確認するのは、いたって簡単です。専従者給与を誰に支給しているかは、決算書に明示されています。各人がどういう業務をどれ程の頻度で、いかなる方法で行っているかを聴取すればよいのです。どんな理屈を並べても、所詮は同族会社の不動産管理、それ程実際の作業があるとも思えません。まして妻や子、何人もの家族従業員に高給を払ってまでやる作業量は、常識的には考えられないでしょう。税務職員も最後は決まって、『もし、同じ作業を奥さんやお子さん以外の第三者が行う場合、今と同じ高い給料を支払いますか?』との質問。たいていの方はこの質問でトドメを刺され、高過ぎることを認めてしまうのです。
4.専従者給与否認の回避策はあるのか?地代収入が大半の場合、高額なものは基本的には否認されてもやむを得ないでしょう。回避する方策は筆者にも思いつきません。多くの場合、地代の回収に専ら従事するだけの実務作業はないでしょうから。ただ、アパート等の賃貸収入が多い場合なら、建物を法人所有とし、青色専従者でなく役員報酬とする方策も一法でしょう。何度かご紹介した、いわゆる所有型法人の形態です。
ここで教科書には書いていない税務署への対応策のご紹介!まず、税務署の基本姿勢として、専従者を否認する場合、具体的な適正額の明示は困難である事を知っておくべきなのです。月額50万円が高く、30万円なら妥当であることなど、理論的な根拠はほとんどないのです。従って、税務署にしても、この手の理論的な妥当性があまりない項目で争いたくはありません。彼らの論拠は、せいぜい同一地域における同規模、同業種との比較です。そのため、否認する場合は全額否認がやり易く、当初はその姿勢を貫きます。ただ、相手が専従者給与否認に対し、徹底抗戦する場合、着地点をそして妥協線を模索してくるのです。修正申告に応じなければ更正する、などの強硬な手段は通常はとりません。何よりの証拠に、かつての調査官である筆者、冒頭の不動産管理料の否認のケースで、うるさい納税者は"そのまま"でしたから。そして何より、腕のいい税理士の援護射撃も不可欠で……いやいや、決して当社が腕のいい税理士だと言っている訳では………珍しく歯切れの悪い締めくくりです。2002年6月28日
-

5120号
相続後でも工夫はできる!
今月は、本業であれ、不動産所得の節税目的であれ、会社を所有されている中小企業オーナー向けのお話です。相続対策は事前の準備が何より大切。ただ、相続後でもこんな工夫ができる場合も…
1.会社への貸付金は要注意!中小企業の場合、懐勘定は個人も法人もなく、会社に資金が不足すれば、個人のお金を投入するのは日常茶飯事。筆者も偉そうなことは申しあげられません。当社自身、その例に漏れずです。
さて、税務上、法人が借りる側であれば、利息を支払わなくても特に問題はありません。いや、利息どころか、元金だって返ってこないことも多いはず。
注意すべきは、相続財産への影響です。例えば、個人から法人に1億円の貸付金がある状態で相続を迎えたとします。この貸付金はまさしく相続財産。いくらで評価するのかと言えば、回収できる金額です。通常のケースでは1億円でしょう。法人として活動もし、少しずつでも返済の可能性があれば、貸付金として1億円で評価されても仕方ありません。しかし、実質的にはあまり機能せず、休眠状態の会社も多いはず。
そんな時は若干の工夫も可能です。
2.回収できなければ、評価はゼロ!回収ができると想定されるから、1億円の評価になるのです。回収できない状態ならば、当然に評価はゼロ。早い話、相続後に貸付金を回収できない状態にしてしまえばよいのです。
一つの手法は、会社の解散。ただ、会社は解散だけで法律的に終了はできません。解散の後、会社財産を総てきれいな形で清算し、利益があれば清算所得の課税。そして株主へ出資額を超える残余財産の分配があれば、配当所得の課税です。
3.税務署も財産なければ追求無し!話は元に戻ります。会社側から見ると、オーナーに対する借入れが1億円あるのですが、借金だけがある状態では債務超過。実は債務超過の場合、特別清算と言って通常の方法より面倒な手続きが必要なのです。
そこで、実務的には清算をせず、解散の状態に留めておきます。具体的には、解散年度の法人税の申告書を税務署に提出。これで、税務署に対してはこの会社が今後、機能しないことは解ってもらえます。その上で貸付金については、解散と言う事由が回収できない事の補強となるため、評価はゼロとできるのです。
税務署は会社に財産が残っている状況で、解散だけしても放っておいてはくれません。前述の清算所得で課税できるチャンスがあるからです。しかし、債務超過の会社なら、旨みはないので、清算までしなくても、それ以上の追求がないのが実態です。
また、解散時に会社に借入金額に相当する赤字があれば、話はもっと簡単です。会社に対し、債権放棄をするのです。会社は債務を免除されたため、贈与されたものとして課税されますが、赤字でその分を補填し課税無し。
いずれにせよ、この様な手続きをしなければ、原則に戻って1億円で貸付金を計上です。
4.会社に土地が残っていたら…こんな事案がありました。亡くなったご主人が生前作った会社が有り、その株式を相続財産として評価です。この会社、大分前から実質的には休眠で、何年にも亘って申告すらしていない有様でした。通常ならば無視してもいいのですが、面倒なことに若干(評価額にして1億5千万円)の土地が残っていたのです。 株価評価の方法に、純資産価額方式と言って、プラスマイナス両財産の差し引き計算で算出する方法があります。この方法による場合、土地の時価を反映した株価となってしまいます。また、従前の申告状況も不明で、欠損金があるや否やも解らず、 な方法は採れません。そこで、この土地の評価額相当の死亡退職金を支給することにしたのです。これにより、この会社のプラスの財産は土地の1億5千万円、一方、マイナスの財産は未払いの退職金1億5千万円。つまり、差し引き株価の評価はゼロ円とする事ができるのです。
因みに、原則的には申告済みの最終期の決算書を基に算出します。しかし、相続後に独自に決算を組むことも可能で、今回は申告もないため、この方法による申告です。基本的には相続準備は生前に、用意周到にお進め頂くに越したことはありません。が、相続後でも、あれやこれや、工夫をすれば何とかいい知恵もでてくるものです。2002年5月31日