お役立ち情報
COLUMN
クラブATO会報誌でおなじみの読み物
「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!
日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、
その時々の時勢を分析していたりと、
中々興味深くお読み頂けることと思います。
絞り込み:
-

リベラリズムの行方
20世紀世界は三回、全人類を巻き込んだ争闘を経験した。第一次、第二次世界大戦と米ソ冷戦がそれである。そしてその三回とも、勝者はリベラリズムを標榜する国々であった。この稿の筆者は、第一次、第二次世界大戦の頃にはまだ生を享けていなかったが、1989年11月のベルリンの壁崩壊とそれに伴う冷戦終結、自由主義陣営の勝利の瞬間は、鮮明に記憶している。東欧の多くの国々の市民が、社会主義専制政治の軛から解放されたその瞬間の、心からの歓喜に満ちた顔を忘れることは出来ない。そのとき、この稿の筆者は、20世紀の三回の試練を経て、自由主義と専制主義の優劣についての問題は、「ケリがついた」のだと思った。経済成長の途上で一時的な開発独裁などの政体を必要とする途上国があっても、経済発展が一定の水準に到達すれば、市民の側からの自然な欲求によって、自由主義的な政体に移行するだろうと予想したのである。
ところが、21世紀に入って、勝利したはずのリベラリズムは、またも試練にさらされている。
2019年、スウェーデンの調査機関VーDemは、世界の民主主義国・地域が87カ国であるのに対し、非民主主義国は92カ国となり、18年ぶりに非民主主義国が多数派になったという報告を発表したi。また、ロシア、中国を筆頭とする専制諸国ばかりではなく、トランプの米国、フランスやドイツの右派勢力など、リベラリズムの本家のはずの欧米諸国においても、自由を揺るがしかねない勢力が台頭し政権に近づいており、もはや「リベラル」は、少数派の代名詞に堕ちた感もある。20世紀の三度の試練を通じて確立されたはずの国際的なコモンセンス、たとえば武力による領土拡張の禁止、言論の自由と人権の保護などのリベラリズム的な価値について、21世紀の専制諸国はどう考えているのだろうか。ロシアは、第二次世界大戦後、旧ポーランド領の約半分をロシア領土とし、その代償に旧ドイツ領の東部のほぼ同面積を新生ポーランドに与えた。つまりロシアに関する限り、第二次世界大戦後の国境線の変更は、2700万人と言われる独ソ戦犠牲者の代償として当然の分け前であり、「武力による領土拡張の禁止」などという国際法的な原則など薬にしたくもないであろう。中国はと言えば、世界において近代社会が始まってからこの方、リベラリズムを標榜する欧米や日本に侵略を受けたことはあっても、リベラリズム的価値の恩恵を受けたことはない。リベラリズムの徳目なんぞは、中国を侵略した国々の、国内的な言い訳に過ぎず、そんな徳目を「コモンセンス」として自らの国作りの役に立てる筋合いはないと考えているのではないだろうか。つまり、20世紀の三度の試練を経て確立されたはずの、国際的なコモンセンスなるものは、残念ながらまだ「世界の常識」にはなり得ていないと考えざるを得ない。
さらに、第一次世界大戦後のワイマール共和国が合法的な選挙によってナチズムを生んだのと似た様な現象が、21世紀の米、英、仏、独などのリベラリズム先進諸国において起きている事実をわれわれはどのように考えるべきだろうか。この稿の筆者の考えは、悲観的であり且つ楽観的である。
すなわち、21世紀、リベラリズムに四度目の試練が来ることはあるかもしれない。だが最終的には「リベラルが勝つ」。その理由は、リベラリズム的な価値が国家や民族に基礎を置くものではなく、個人に基礎を置くものだからである。四度目の試練の後、世界はさらに近代国民国家を超えた枠組みを求めることであろう。そのときにこそ、1989年のあの日の人々の笑顔が、国家や民族の歓喜ではなく、市民個人の歓喜の姿であったことを思いたいのだ。
i 東洋経済オンライン 薬師寺克行 2021.06.30
2023年3月2日
-

慶喜恭順
近世、近代日本史には三つの大きな「謎」がある。第一は、明智光秀は何故織田信長に叛いたのか。第二は、浅野内匠頭は何故吉良上野介に刃傷に及んだのか。そして第三は、徳川慶喜は何故軍事的に優位だったのに薩長(西軍)にひたすら恭順したのか。
今月は、このうち第三の謎について書きたい。
まず初めに、徳川慶喜という人物が幕府制度や将軍職にあまり魅力を感じておらず、天皇を頂点とする国家の下で、徳川氏の行政能力、経済力、軍事力などを背景に中枢の地位を得たいと思っていたであろうことを書く。これについては慶喜の生家である水戸徳川家の遠祖光圀が私淑していた明からの亡命学者朱舜水の影響を指摘したい。朱舜水は、清に滅ぼされた明の復興運動に幾度も挫折した後、日本に亡命してきたのだが、日本のありようを見て何故か感激してしまった。日本の歴史には放伐革命による王朝交代がなく、萬世一系の皇室というものが継続していたからである。そのことはとくに王朝の交代によって前王朝の遺臣となってしまった朱舜水の胸を打ち、「日本こそが中華の国だ」とすら思わせた。彼の思想的影響が水戸藩の代々に及び、当初は徳川幕府に忠節を尽くすことが、ひいては天皇(君)に対する忠義であるという見解であったものが、次第に後期水戸学になるにつれて、徳川幕府を脇に置いて、天皇に対する直接の忠義という考え方が出てきた。慶喜はまさにそのような思想的環境の中で育てられた。
次に、慶喜が一方の主人公であった、十三代将軍家定の後継争い。この一橋派(慶喜を担ぐ)と南紀派(紀州藩主徳川慶福を担ぐ)の争いは、単なる幕府内の宮廷闘争ではなく、薩摩、越前など有力な列藩藩主と協議をしながら政治を進めるのか、あるいは従来通り譜代専制の幕閣が政治の主導権を握るのかという考え方のちがいがあったのである。つまり慶喜には、十四代将軍家茂(慶福のこと)の急死によってやむをえず征夷大将軍に就任する遙か前から、列藩協議による政治運営の構想があったことになる。そして孝明天皇の信頼が厚かった慶喜にとっては、この構想の中で自らが中心となって政治を進めていくことはけっして夢ではなかった。
ところが、わずか半年後その孝明天皇までが急死してしまう(暗殺説もある)。やむをえず慶喜は、幕府と言うよりは徳川氏の軍事力を刷新強化し、政治の主導権を持ち続けようとする。これに最も脅威を感じたのが薩摩藩である。何故ならば、徳川主導であれ、後の明治政府であれ、新しく天皇の下で発足する国民国家日本には、早急に解決しなければならない課題があったからである。
それは「廃藩置県」による中央集権化であった。そして慶喜主導で廃藩置県が為されると言うことは、おそらく薩摩の滅亡を意味する。長州、そして薩摩という軍事力で徳川氏と対抗しうる大藩は、武装を解除され、(実際に初期明治政府における徳川氏がそうであったように)完全に権力の中枢から排除されるだろう。ここから薩摩の一部藩士による挑発と武力倒幕という陰謀が開始されたのだとこの稿の筆者は考えている。その後大政奉還と倒幕の偽勅が同日に起きる話から、小御所会議のクーデター、薩摩の挑発、鳥羽伏見の戦いまでの経緯はよく知られるとおりである。慶喜はまんまと天皇の下での国家運営の主導権を「偽錦旗」を掲げる薩長に奪われてしまった。幕府というものに魅力を感じていなかった慶喜にとって、そのことは痛恨事ではあったが、それでも朝敵となって武力抵抗を続けるという選択肢はなかった。慶喜は恭順するしかなかったのである。
2022年12月12日
-

伯夷叔斉
紀元前1000年頃(といわれているが、定かではない)中国全体を支配していた殷(最近の考古学の成果から実在したことが確認されている)王朝は終焉を迎えようとしていた。第30代の王は紂王と言って、たいへんな暴君であったと言われるが、とりあえず本稿の主題ではない。
その殷の中に孤竹国という小国があって、国を治める伯に、伯夷、仲馮、叔斉という三人の兄弟がいた。その当時の中国に、長子相続という習俗があったのかどうかは、これもよく分からないのだが、孤竹国の人々は、伯夷が後継者となるだろうと思っていたらしい。ところが、伯の愛情は末子の叔斉に注がれ、叔斉を後継とするようにと遺言して亡くなった。伯夷は、自分が孤竹国に居たのでは叔斉が後継者としてやりにくかろうと思って、国を去った。一方、叔斉の方も、伯夷を差し置いて後継者となることをよしとせず、自分も伯夷の後を追って孤竹国を出て行ってしまった。困った孤竹国の人々は、仕方がないので真ん中の仲馮を立てて後継者としたというお話し。父の遺言を尊重した伯夷は「孝」という徳目を重んじ、兄を差し置いて君主に立つことを肯わなかった叔斉は「長幼の序」という徳目を守ったと言うことになる。
後世漢の時代の歴史家司馬遷が、この二人の伝説を「史記」の冒頭に掲げたのは、有名な話。さらに、本朝の徳川光圀(水戸黄門、事情があって兄を差し置いて水戸徳川家の後継者となった)が、自分のコンプレックスに重ね合わせて、伯夷叔斉の伝説に感応且つ感激してしまい、それが「史記」を真似て「大日本史」を編纂する端緒をつくったというのもよく知られている。
さて、伯夷叔斉の話には後日談がある。孤竹国を出た二人は、流浪の末に周国の西伯昌が仁に厚い名君だという評判を聞いて、仕えようと周に向かった。しかし残念ながら彼らが周の首都に着いたときには昌はすでに亡くなっており、昌の後を継いだ子の発(後の武王)が、諸侯の支持を得て、殷の紂王に対する放伐革命に決起する直前であった。そこで伯夷叔斉の兄弟は、西伯発の馬の前に立ち塞がり、紂王にどのような暴虐や非行があっても臣下たるものは、これに背いて謀反を行ってはならず、あくまで君主を諫めることに徹するべきだと説得する。徳目としては「忠」を貫くことをよしとしたということになる。が、当時の事情を言えば、世論はすでに紂王の上にはなく、諸侯はこぞって西伯を立てて殷王朝を倒そうという勢いにあった。中国の歴史の中では、前王朝の天命が尽きれば、これに代わる者の上に天命が下って命が革まる(革命)ことになっており、発にしてみれば、伯夷叔斉の言は、タイミングを失した無用の止め立てとうつったかもしれない。
発は諸侯を率いて殷王朝を倒し、周王朝の武王として中華に君臨することになった。伯夷叔斉の兄弟は、周(西伯の支配域ではなく、中華一帯)の粟米を食うことを潔しとせず、(比喩として周に仕えなかったということではなく、ほんとうに志の汚れた周で耕作されたものは口に入れないことにしたらしい)、首陽山というところにこもって、自生する蕨を採取して暮らしたが、やがて餓死した。
彼らが餓死する直前に作ったとされる「采薇の歌」(蕨をとる歌)が残っている。紙数の関係で全て採録できないが、「暴ヲ以テ暴ニ易ヘソノ非ヲ知ラズ」と痛烈に武王の革命を批判している。
司馬遷は、史記の冒頭にこの伯夷叔斉の物語を掲げ、「天道是か非か」、つまり中華民族が尊ぶ徳目を墨守したこの兄弟を置き去りにして、殷から周へと流れゆく歴史の大河(天道)が、果たして是であったのか、否であったのかを問い、以て自著「史記」全体のメインテーマとしている。
2022年11月1日
-
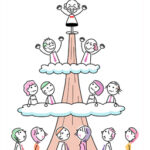
先輩後輩
2021年8月24日夜、東京メトロ南北線白金高輪駅のエスカレーターで、通勤帰りの会社員が、尾行してきた男に、突然振り向きざまに硫酸を掛けられるという事件が起きた。犯人は被害者の大学サークルの先輩。それほど親しくはなかったようだが、要するところ被害者が「後輩のくせに先輩である自分にタメ口で話した」ことが犯行の動機らしい。犯人は、はじめ自分の学年年齢を明かさず後輩達と交わってフラットに話していたが、途中から「自分は先輩だ」と言い出し、後輩達が口のききかたを改めなかったために、深甚な恨みを抱いたのだとか。
先輩はエライ。先輩がどんな人でも、後輩は先輩をたてなければならない、なんていう文化は、かなりの程度に日本特有のものではないかと思う。先輩というのは、あるコミュニティに時間的に以前から、長くいる人のことであるから、王侯貴族がエライ、お代官様がエライ、社長がエライ、党官僚がエライ等というのとはちょっと違うような気がする。
戦前の帝国陸軍には「星の数より飯の数」ということわざがあって、古兵殿とかいう、長い期間軍隊の飯を食べてきた兵員は、制度上の分隊長、小隊長よりも隠然たる力を持っていた。帝国海軍では軍令承行令という規則が公式にあって、全海軍の兵科士官の序列が一律に決まっていた。軍令承行令は戦闘中の軍艦で艦長などが戦死した際に、次に指揮権を受け継ぐ者の順序を予め決めておくものであったが、この序列は、任官順、つまり先輩が後輩よりエライように出来ていた。(任官順が同じ時は兵学校の成績順)。これは実際に戦争が起きてみるとかなり不都合なもので、とくにハワイ攻撃の不徹底やミッドウェーの敗北で評価の低い南雲忠一提督が、なぜ帝国海軍虎の子の機動艦隊(第一航空艦隊)を率い、航空戦に識見が深く空母機動部隊生みの親であった小沢治三郎提督がなぜ水上部隊(南遣艦隊)の指揮官に回ったのかというような、戦争の帰趨を決めるような将官人事についても、「先輩が後輩よりエライ」原理が適用されてしまった。因みに米国の軍隊の人事は、もっと柔軟で、第一次世界大戦中、米陸軍の佐官級の若手の秀才ダグラス・マッカーサーが、あっという間に代将、少将と「戦時中だけの」将官に抜擢されたことはよく知られている。
ついでに言えば、ある組織の中で先輩でも後輩でもない「同期」という存在は、組織の構成員がストレスを感じないで済む希少で大切な仲間であり、多少の出世の度合いが違っても一生「タメ口」で語り合う「同期の桜」となるのである。
こうした日本の先輩後輩秩序はなぜ生じたのか。いくつか理由はあろうが、先ずは儒教による「長幼の序」の影響。兄弟に才能の優劣があっても、先に生まれてきた方が必ず家を継ぐというルール(承行令)によって、家督相続争いを避けようとした。農民の世界では、日々の農耕には才能の優劣はあまり影響しないので、年齢秩序が優先された。いまは後輩である若者も、いずれ年をとれば先輩になれるので、「先輩が後輩よりエライ」ムラ秩序は、理不尽なようで、意外と公平と言えないこともなかった。江戸時代の職人や商人の世界でも、駆け出し初めの十年くらいは先輩の言うことをご無理ごもっともと耐えて聞くことが「修行」であり、才能の発揮はあくまでも年季が明けた後のことであった。こうして見ると、先輩後輩秩序とは、労働市場に流動性がない社会を円滑に運営するための知恵であったことが分かる。日本の労働市場が、流動化の時代を迎えようとしている現代には、働き方改革と共に「先輩が後輩よりエライ」という秩序も見直すべきではないだろうか。
2022年10月1日
-

民主主義その2
先月に続き民主主義に関するキーワードから「民主主義とは何か」を考える。
「トーリーとホイッグ」
近代市民革命前後の英国において、王権神授説を唱える国王に随身する保守貴族勢力がトーリー、議会に拠って政治を行おうとする開明的貴族と大商人達の勢力がホイッグである。前者がアリストクラシー、後者がデモクラシーの系譜を継いだ。
英国では、一時国王を倒して議会が主権を把握し、議会が任命した「護民卿」という者が統治を行ったが、うまく行かず、後に国王が復帰した。トーリーは議会の存在を認めて議員を送り、ホイッグは国王の統治を認めて、議会を通じ国王統治の抑制を図った。
アメリカ独立戦争にもトーリーとホイッグは存在した。トーリーは英国国王派なので概ね植民地維持を唱え、ホイッグは民主派なので「代表なければ課税なし」を唱えて英国からの独立を志向した。「自由な政治と独裁政治」
イギリス、アメリカ、フランスなどで近代市民革命が一応成功すると、行政を担う統治者から、相対的に自立した議会という存在が重要視されるようになった。議会は人民の選挙によって選ばれるので、統治者の恣意をチェックすることが出来、場合によっては革命などの手段によらず合法的に統治者を解任できるようにもなった。そうした、選挙権の行使によって人民が統治者からの自由(主には統治者の意にそまない言動によって拘束を受けたりすることからの自由)を獲得することを以て民主主義の勝利と呼んだのである。一方で、こうした選挙による抑制を受けない統治者を独裁者、独裁者が行う政治を独裁政治「ディクテーターシップ」と呼ぶようになった。「ポピュリズム」「衆愚政治」
ところが近代後期に入ると、選挙民たちが政治的な熱狂によって独裁者を選挙してしまうという例が発生するようになる。典型的な例はナチスドイツのヒトラー(合法的な選挙によって政権を獲得した)だが、最近もアメリカの前大統領トランプなどは、一種の衆愚政治をみずから演出し、大衆を扇動して大統領に選出された例として記憶に新しい。「プロレタリア独裁とブルジョア独裁」
マルキシズムの世界では、民主主義の判定基準を「どのような制度によって政治が行われているか」ではなく、「どのような勢力が実権を握っているか」に求める。近代社会の英国議会は実質貴族と大商人が実権を握っていたから「ブルジョア独裁」であり、革命後のロシアは工場労働者が実権を握っていたから「プロレタリア独裁」なのでより民主主義に近いというような見方をする。昨今の中国も共産党の独裁政治によって人民が食べられ、外国から侵略を受けない強い国になったのだから、それが民主主義であるという見方をしているようだ。が、現代中国のような独裁政治は、明治初期日本の大久保利通や少し前のインドネシアのスハルト等が行った開発独裁という政治形態の一種であり、一時的に有効であっても、長い目で見れば民主主義の常態とは言えない。結論として、民主主義とは、統治者の権力行使に対して、それを抑制する政治のメカニズムがあり、人民による選挙を通じて抑制のメカニズムが適切に行使される状態であると思う。愚かな民が愚かな政治家を選ぶことがあったとしても上記の抑制機構を維持できれば、いずれは回復できる。
2022年9月1日
-

民主主義その1
今月は、「民主主義とは何か」ということを書こうとしている。
世に「我田引水」という言葉があるが、この世の大半の国々は自らが民主主義であることを標榜している。本来民主主義とは相容れないはずの君主制国家、たとえばイギリス、オランダ、ベルギー、スウェーデン、ノルウェーそして日本やタイなども皆、自らの政体は民主主義であると主張し、さらに言えば、自らは民主主義の卸元であるとさえ思っている。一方で、○○民主主義人民共和国の類の共産主義諸国も、あるいは独裁者を戴く全体主義諸国も、「自分が民主主義の極みだ」と主張している。そこでいくつかのキーワードを探りながら、「民主主義とは何か」ということを探っていきたい。
「デモクラティアとアリストクラティア」
デモクラシー(英語)の語源は、ギリシア語のデモクラティアである。この語は人民(デモス)と権力(クラティア)を併せた造語である。これの反対語は貴族(アリスト)と権力(クラティア)を併せたアリストクラティアである。まあ、市民政治と貴族政治とでも訳せばわかりが良い。都市国家の広場に市民権を持つ市民(男性のしかも全部ではなく資格制限があるのが常態であった)が集まって政治を議し投票で物事を決めるのがデモクラティアで、最初から政治を取り仕切る資格のある家族(貴族)が決まっていて、それら貴族の合議で決め事をするのがアリストクラティアであった。「ビューロクラシー」
前記造語の発展型として「ビューロクラシー」(英語、「官僚政治」のこと)という言葉もある。ビューロは官僚、役人の意味があり、一定の規範を持つ官僚集団が政治を取り仕切る形態を「ビューロクラシー」と呼んだ。たとえば、古代東アジアの科挙を基盤とした官僚政治などもデモクラシーの反対語として扱われる場合がある。さらに官僚政治の発展型として20世紀社会主義諸国の「ノーメンクラツーラ」(党官僚)による政治も、実態は党官僚という名の「赤い貴族」の政治に近く、デモクラシーの反対語としても良いかもしれない。「代議制民主主義と直接民主主義」
デモスクラティアは、はじめ都市国家の広場における民会が決定機関であったので、やりかたとしては直接民主主義に近かった。が、だんだん市民権を持つものの範囲が拡充されると、民会や直接投票ではものごとを決める手段として不便になってきたので、議会乃至は類似の代議機関をつくって、「市民の意志」を反映させるようになった。これを以て代議制民主主義と呼ぶ。たしかに、議会は市民権を持つものの選挙によって成り立つので、貴族政治や官僚政治に比べると「市民の意志」には近い判断ができるように見える。が、常設の議会は時間が経つとそれ自身が特権(あるいは利権)集団に堕ちる場合があり、必ずしも民主主義の守り神とは言えなくなってしまう場合もある。なお、社会科の授業風に言えば、今日世界の民主主義の大半が代議制で運用されているが、国家レベルではスイスがかろうじて民会、直接民主主義の残滓を保っているらしい。また、各国憲法に内蔵されている国民投票のメカニズムも、やや直接民主主義の要素が代議制の中に残っている証拠とも考えられる。
上記は、民主主義の種類や発展の形態に関する、「おさらい」であって、まだ「民主主義とは何か」の考察に行き着かない。そこで来月号も引き続き本題を続けることにする。
2022年8月1日
-

パンとサーカス
…iam pridem, ex quo suffragia nulli
uendimus, effudit curas; nam qui dabat olim
imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se
continet atque duas tantum res anxius optat,
panem et circenses…
…我々民衆は、投票権を失って票の売買ができなくなって以来、
国政に対する関心を失って久しい。
かつては政治と軍事の全てにおいて権威の源泉だった民衆は、
今では一心不乱に、専ら二つのものだけを熱心に求めるようになっている―
すなわちパンと見世物を…(ユウェナリス『風刺詩集』第10篇77-81行)ⅰ古代ローマの話である。但し、ローマ史を語るのが本稿の意図ではないので、いくつか要点だけを説明すると、「パンとサーカス」は、ローマの実質的な支配者である貴族(後には皇帝)が、ローマ市民権を有する平民(ローマ市内に住んで、恒産や生業を持たずに属州から入ってくる食糧を徒食している無産市民)を接待しなければならなかったという話である。
パンについて言えば、ローマ帝国を構成する穀倉地帯から流入してくる小麦粉などを、貴族の負担において市民に配った。これは社会福祉と言うよりは、文字通り支配階級の人民に対する「施し」乃至は「接待」であり、この配給食糧こそが、無産市民の徒食を可能にする原材料であった。
サーカスについて言えば、サーカスとは、戦車競技をするためのcircuit(サーキット)のことであり、貴族はサーキットのある円形競技場において、戦車競技を主催して人民をもてなした。戦車競技を知りたい方は、映画「ベンハー」を見られると良い。やがて、サーカスは狭義の戦車競技にとどまらず、円形競技場で行われる様々なスポーツイベント、たとえばライオン対人間の戦いだとか、後には人間対人間の武器を持った闘技(映画「スパルタクス」をご覧になると良い)などへとエスカレートしていった。観衆は、興奮の上に興奮を求め、恍惚として「殺せ、殺せ」と叫んだのだという。
さて、2021年に開催した東京オリンピック、パラリンピックについて、疾病疫病の最中、過半数の国民の開催中止の与論をものともせず、国家の要路に立つ者が、この世界規模のスポーツイベント開催に突き進んだ理由は、ギリシアに由来するオリンピックの理想の故ではなく、市民に「サーカス」を与えなければ、自らの支配が保てないという強迫観念によるものだと思わざるを得ない。ついでに言えば、当のオリンピックのための時代錯誤のインフラ整備や、巨額の財政支出を国債でまかなった経済運営も、いわば「民の金で民を買収する」営みに等しい。政府の営みによって、人民は後世の借金返済の義務を負わされるのであるが、「そんなことは知らない」。何故ならば、負担を負うのは子々孫々の世代であり、また要路者からは何の説明もないので、「きっとなんとかなるのだろう」。ローマが愚民政策によって滅びたのかどうかはよく分からないが、我々も「パンとサーカス」を続けていると、ろくなことにはならないような気がする。
ⅰ Wikipedia パンとサーカスより引用
2022年7月1日
-

兼 業
昭和の頃、普通の会社の就業規則には、「職務専念の義務」とかいう条項があって、正社員(ホワイトカラーだけでなく、ブルーカラーや特殊技能者でも)は他所でアルバイトをしてはいけないものとされていた。この規則は結構厳しいもので、厳密に言えば休日に少年野球の審判をやってもお金を貰ってはいけない、終業後、夜の飲食店の仕事をするのも、音楽バンドや劇団に参加して金を貰うのももちろんいけないというもので、いわば労働者をまるごと会社に囲い込もうというような規則であった。
なぜ、こんな制度であったかというと、おそらく「終身雇用・年功序列」制下の企業というものは、いわばムラ社会、あるいは江戸時代の藩のような存在で、コミュニティーの構成員は全人格的に共同体に帰属するのがあたりまえだという感性が根底にあったからだろうと思われる。この稿の筆者は、その頃、北九州市にある日本一の製鉄メーカーの工場が、構内に社宅のみならず理・美容室や風呂屋、ちょっとしたスーパーマーケットまで備えていて、その気になれば、工場構内から出ずに殆ど生活が成り立ってしまうのを見て驚いたことがある。
だが、昨今では、政府が働き方改革の一環として、労働者の兼業を大いに推進しようとしている。厚生労働省の出している文書を見るとⅰ「副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる、様々な分野の人とつながりができる、時間のゆとりがある、現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる等さまざまであり、また、副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである。」「副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり・・」と述べている。
では、なぜ世の中の風潮が変ったのか。第一には、2000年頃からのいわゆる小泉改革によって、社会における非正規労働者の比率が増え、終身雇用・年功序列の企業ムラ社会が解体されてしまったこと。第二には、企業そのものが右肩上がりの永続的なものでなくなり、正規雇用の労働者といえども、いつ企業の外に放り出されるか知れたものではなくなったことが挙げられる。
つまり、労働者はおしなべて会社に全人格的に帰属する存在ではなく、自分のスキルを会社に売って生活を立てる個人事業者になったのである。個人事業者であるからには、一社だけと取引する義務はないわけだし、また自分の未来を考えて、スキルを伸ばしたり、拡げたりすることも自らの責任で行わなければならない。日本の人口が減少し市場が縮小することで、かつての「24時間働けますか」のような過酷な労働が必要でなくなる一方で、収入も相対的に減少し、労働者が会社の外で収入の道を求めることをむしろ奨励しなければならなくなったという事情もある。
さて、最後に上記に関連して、「この道一筋」という道徳が、次第に世の中に通用しなくなりつつあることを述べたい。昭和の時代には、たとえば子供の頃から野球に精進し、高校野球で活躍し、プロの野球選手になれたらば、引退後も球団のフロントに雇ってもらい、あわよくば監督、コーチの道をめざす「この道一筋」が良しとされたのである。が、今の世の中は、引退する日本代表のラグビー選手が大学の医学部に進学し直すことが良しとされる時代となったのである。
ⅰ 2018年1月策定(2020年9月改定)厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
2022年6月1日
-

豆
本稿が掲載される頃には、季節はすっかりビールの美味い時期になっていることだろう。この稿の筆者がかつて在籍したビール会社で、「家庭で食べるビールのつまみには、何が良いか」という議論があって、各自故郷の味自慢、嫁さんの味自慢などが出た末に、結論としては、セロリ、胡瓜、にんじん、大根などの生野菜に塩を掛けて食べるか、空豆、枝豆などをただ塩茹でして食べるのが、いかなる手を掛けた料理よりもビールに合うということになった。結局、素材そのままが良いということなのであろう。
そこで、生野菜は置いて、今月は豆のお話し。
まず、世界六大食用豆というものがあるそうだ。大豆、落花生、えんどう豆、隠元豆、ひよこ豆、そして空豆。なかでも空豆は、チグリスユーフラテス河流域からエジプトで4000年以上も前から食用として栽培されていたそうで我ら人類とは、長いつきあいのある豆だ。日本でも、奈良時代には既にインドの僧侶が中国を経て持ち込んだと考えられている。名前の由来は、実が空に向いて成るからと言う大変おめでたいものでもあるが、蚕豆、天豆、野良豆、四月豆、夏豆等の異名もある由。
野菜として未熟な若い豆を茹でるなどして食べるほか、完熟させた豆を乾燥させたものはフライビーンズ(いかり豆)や菓子の原料に使われる。豆板醤に使われるのも、この乾燥豆の方だそうだ。
日本における主産地は鹿児島、千葉、茨城など。国内の市場に出回っているもののほとんどは一寸そら豆と呼ばれるタイプで、一つのサヤに二、三粒のものが主流となっている。空豆料理の王道は塩茹でに尽きるが、さやごと焼いて、中で蒸し上がった空豆を食するのも乙なものである。
次に、ビールと言えば、枝豆。あの緑色鮮やかな枝豆が、大豆の若い時の姿であることは、知らない方もけっこうおられる。枝豆とは未成熟な大豆を収穫したもので、枝付きのまま扱われる事が多かったために「枝豆」と呼ばれるようになったとか。言葉の意味としては、枝付きの豆はみんな枝豆なのだが、なかでもとくに大豆の枝付き豆が「あの」枝豆なのである。国産の普通の枝豆以外にも、山形特産の「だだちゃ豆」(だだちゃは親爺の意)や、丹波地方特産の黒豆品種の「丹波黒大豆枝豆」などのブランドものもある。さらに「ずんだ」という異称もある。これは緑色の枝豆を潰してペースト状にしたもののこと。これをまぶして「ずんだ餅」などをつくる。枝豆選びのこつは、スーパーマーケットなどで、枝から切り離されて袋に詰められているもの(その方が手はかからない)は避け、必ず枝についたままのものを買うこと。枝に残っている葉っぱが新鮮な緑であるものを選ぶと良い。ⅱ
最後にグリーンピース、えんどう豆。調べてみると「エンドウ豆には、豆を食べる"実えんどう"と豆が大きくなる前に若取りし、さやごと食べる絹さやなどの"さやえんどう"とがある」と書かれていて、前者の代表がグリーピース、後者の代表が絹さやということになろうか。この関係は、大豆と枝豆の関係に等しい。ただしグリーンピースは、未成熟の若い豆の時にさやごと食べることも出来る。料理法は、グリーンピースなら、サラダ、メインディッシュの付け合わせ野菜としても、あるいはベーコン等と炒めてもよい。絹さや、スナップ豌豆、砂糖豌豆など若豆をさやごと食べるものも、煮物のお供、味噌汁の具など和食に使うイメージがあるが、緑の豆をちょっと炒めるか、さやごとサッと茹でて、塩味だけで食べるのが、ビールのつまみとしては望ましい。ⅲ
豆は、芋類と比較して糖質も少なく、栄養価のバランスがよい。健康的な食品である。
ⅰ https://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/soramame.htm
ⅱ https://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/edamame.htm
ⅲ https://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/endou.htm
本稿は、「旬の食材百科」サイトを参考とさせていただき、その一部を引用している。2022年5月1日
-

歴史教育
先月号に続き、歴史教育の話である。今月号では二つのことについて書きたい。
一つは、歴史における教訓主義と実証主義という問題。もう一つは、歴史の教師は、生徒にどれほど影響を及ぼすことが出来るか、という問題である。
一つ目は、「何のために歴史を学ぶ(教える)のか」という目的に帰着する。歴史を学び、その中から今日私たちが生きるための教訓を汲むのが目的であるとする者を、教訓主義者と呼ぶ。それに対して、歴史の事実を詳しく調べ、歴史上の物事がなぜ起こったのかを究めることを目的とするのを、実証主義者と呼ぶ。教訓主義者は、往々にして英雄譚を好む。英雄の身辺の区々たる細事よりも、英雄自身の感動的な振る舞いに目を向け、英雄譚の伝承を通じて、今日の我々が学ぶべきことを問う。たとえば、虐げられた民族の中に、屈せずに支配者に抵抗した英雄がいたとすると、その英雄譚は、今日の支配者への抵抗のよすがとなる。仮にその英雄の私行にいささか問題があったとしても、そういう区々たる問題には目をつぶってしまう。大切なのは、英雄が支配者に立ち向かったという事実だけであり、英雄譚にケチをつけるような研究は、否定されてしまう。一方の実証主義者は、まず現在分かっている限りの事実を掘り出して、それを眼前に並べてみてから考える。この世に残されている歴史の証拠物件、すなわち一次資料の中には相矛盾するものもあるから、「どちらの事実が正しいか」も考える。その際に「どちらがあるべき事実か」などとは問わない。教訓になろうがなるまいが事実は事実である。判定の基準は、一次資料の時系列に矛盾がないかと言った論理的分析であったり、時には、自然科学的手法を用いた紙や筆跡の真贋判定であったりもする。そして、実証主義者の得るべき結論は、「その事実から何を学ぶか」ではなく、「なぜ物事はそのように起こったか」「もし過去にしかじかの物事が○○の理由で起こったのなら、同じ理由で今日の物事はしかじかとなるのではないか」といった分析と予測である。
歴史は英語ではhistoryと言い、story(物語)と同語源である。仏語では歴史も物語もどちらもlhistoireである。だが、歴史を「ものがたり」と考えるのは教訓主義者であって、歴史をscienceと考えるのが実証主義者なのである。
さて、二つ目の話は、我が国の第二次世界大戦後の教育史を彩る文部省対日教組の戦いについて述べることから始めたい。この稿の筆者は、この争いに費やされたエネルギーほど不毛なものはなかったと思っている。日教組は、文部省による歴史教育支配が、戦前の皇国史観への復古を招き、教え子達を再び戦場に送ることにつながると信じた。一方の文部省は、日教組の教育現場支配が、アカ教師によるアカ生徒の育成を企図していると信じ、日本全体が左傾化することを恐れた。だが結果としては、教師が何を教えようが、生徒はさほど右翼にも左翼にもならなかったのである。それはなぜか。この稿の筆者は、それは日教組対文部省の争いが、左右どちらも教訓主義者同士の争いであって、歴史というものを冷徹に見て、実証によって物事が生起する理由を問おうとするものではなかったからだと思うのである。第二次世界大戦後の世界は、情報にあふれ、生徒は教師以外の情報源からも、無数の「物語」を入手することが出来るようになった。学校教育が生徒を戦場に動員したり、社会を左傾化したりする力は、もはや失われていたのだと知るべきである。学校で教えるべきは、歴史に対して実証的にアプローチする態度ではなかったのだろうか。
2022年4月1日
-

豚の歴史
その昔(戦前期)の東京帝国大学に、平泉澄(1895-1984年)という有名な歴史学の教授がいた。
いわゆる皇国史観イデオローグの代表者で、皇室や軍とも通じており、歴史学者の立場から皇国史観教育への啓蒙や、折々の政治・政局への発言も行った。今回本欄はその平泉教授の事績を取り上げるのが目的ではないので詳述は避けるが、平たく言えば戦前の大物右翼学者であった。
さてその平泉教授の所の研究室だか、ゼミナールだかのお弟子が、論文指導を受けに行って、「中世農民の歴史を研究したい」と希望をのべたところ、言下に「君、豚に歴史がありますか」と問われて、許してもらえなかったという話がある。つまり、平泉氏の見解によれば、歴史というものは、楠木正成であっても足利尊氏であっても、正邪はあれども皆「名のある」人々によってつくられるのであり、豚に等しい「名もなき庶民」には歴史などはない、ということになる。昭和初め頃までの歴史学の世界では、唯物史観を掲げるマルクシストもかなり有力であったから、平泉氏は「農民の歴史を研究したい」という弟子の希望に、どことなく大嫌いな左翼歴史学の臭いを嗅いで過剰に反応したというところなのかもしれない。一方でその左翼歴史学はどうであったかというと、歴史にアプローチする方法論としてはたしかに唯物弁証法を掲げてはいたが、スターリンや毛沢東の「歴史学」と称する著作を少し読んでみると、これまでの歴史上の出来事を説明するのにそうした方法論を用いて、自らが「社会科学的なアプローチをしている」と称しているだけで、農民や労働者の中で生じた区々たる歴史そのものを詳しく研究しているわけでもない。スターリンや毛沢東は楠木、トロツキーや劉少奇は足利とアナロジーしてみれば、その正邪を言っているに過ぎないところは、平泉史学とどこか似ていないこともない。
日本の歴史学において、ほんとうに庶民の歴史に分け入って、その中身を研究することから社会の全体像を構築する方法を編み出していったのは戦後になってからである。中でも、平泉から「農民の研究」を拒絶された次の世代、具体的な名を言えば網野善彦(1928-2004年)辺りが出るに及んで、はじめて左翼史学が言うところの括弧付きの「社会科学的アプローチ」を超えて、実証史学的アプローチの実が結ばれるようになったと、この稿の筆者は評価している。
網野義彦は第二次世界大戦直後の左翼運動の出身で、網野史学も、網野義彦本人の直観によって、実証の不足を補っているという批判があり、完全な実証主義に基づいているとは言えないかもしれない。が、少なくとも「名もなき庶民」の遺した一次資料を丹念に発掘し、読み込むことの中から、従来捉えられてきた日本歴史の像を覆す新しい全体像を構築して見せ、それを学界に問うたことは、大きな事績と言わなければならない。それは例えば、南北朝期で言えば、庶民の中に埋もれた一次資料を見いだすことの中から、「足利尊氏は実は忠臣だった」ことを発見して正邪をあらためるのではなく、「楠木正成は武士ではなく悪党というものであった」ことを発見し、各地に存在した悪党と称する人々が、鎌倉武士の(守護地頭)秩序に包摂されない、そして一部は農耕生産にすら依存しない存在であったことを示すようなことであった。網野の中世日本研究の中では、とくに天皇を中心とする荘園秩序vs武士(守護地頭)の支配という対立軸の外に、職人、芸人、陸海の運輸業者など、移動して定住しない人々を、第三勢力として定義したことが顕著な実績として挙げられる。「豚の歴史」の研究は、けっして無意味なことではなかったのである。
2022年3月1日
-

廓 噺
はじめに堅い話を数行。売春という行為について近代以降社会の道徳的指弾が厳しくなった。男が女の性を金銭で購うのは、女性の個人としての尊厳を冒す行為であるというのがその趣旨である。が、一方で売春は世界最古の職業であるとも言われている。売春は時代、地域に限らず歴史上存在し続けてきた行為であり、人類の文化でもある。平たく言えば売る者と買う者の利害が一致するから、長い人類の歴史の中で消滅しなかったのだとも言える。しかし、江戸期の吉原遊郭は、そうした男女の自由な取引の場として存在したとは必ずしも言えない。華やかな吉原文化の陰に、人身売買、年季労働による花魁の拘束等の暗い事実があったことも見逃せない。今月紹介するのは、廓噺、すなわち吉原遊郭を題材にした落語の数々であるが、噺の中にも、遊郭の社会制度的な構造が深く影を落としている。以下はいずれも故三代目古今亭志ん朝の高座から。
【明烏】は、廓噺の中では知名度が最も高く、比較的明るい噺である。書物ばかり読んでいる堅物の息子時次郎を心配した大旦那が、町内の札付きに、息子を吉原に連れて行き遊びを教えることを依頼する。依頼を受けた二人の悪が、如何に若旦那を蕩かしていくかというお話。すったもんだのドタバタがあった翌朝の若旦那の豹変が聞き所である。【五人廻し】は、関東の遊郭特有の慣習であった「廻し」、すなわち一夜で複数の客を花魁が巡回して相手をする(一晩中待たされても花魁がやってこないこともままある)ことを扱った滑稽噺である。ちっともやってこない花魁にいらだつ客の種々相が面白く描かれている。が、白眉は五人目のお大尽客の所で牛太郎に発見された花魁が、四人の客の揚げ代を立て替えてくれるというお大尽に、五人分の金をねだり、当のお大尽もお引き取りいただくという落ちであろう。【お見立て】も花魁にとっての嫌な客の噺。花魁の嘘にほだされて年季が明けたら一緒になると思い込んでいる嫌な客を追い返そうと、牛太郎に「花魁は死んだ」と嘘をつかせたところ、客が墓参りに行くと言い出して大困りするというお話。題のお見立ては、遊郭の籬で客が花魁を見立てる行為を言うが、ここでは客に花魁の墓はどれかと問われて困り果てた牛太郎が、お寺の墓石群を指して、客に「どれでも好きなのをお見立てください」と答える落ちと掛けている。【三枚起請】は、年季が明けたら一緒になるという起請文を三人の客に与えた花魁を、そのことを知った三人がとっちめるという噺。「嘘の起請を書くと熊野で烏が三羽死ぬっていうぜ 罪なことしやがって」、「そうかいだったらもっと起請を書いてカラスを皆殺しにしてやりたいねえ」、「そんなことをしてどうする」、「ゆっくり朝寝がしてみたい」という落ちが、哀感を誘う。【幾代餅】は、年季が明けたら一緒になるという花魁の約束が見事にほんとうになる噺。米屋の奉公人清蔵が、絵草紙で一目惚れした花魁幾代太夫に会おうと、一年働いて十三両と二分の金を貯め、旦那の応援もあって十五両の金を握りしめて吉原に向かう。野田の醤油問屋の若旦那と偽って思いを遂げた清蔵だったが、幾代の後朝の問いに思わずほんとうのことを白状してしまう。清蔵の誠意にほだされた幾代が、ぶじ年季も開けて清蔵の妻になり、両国で餅屋を始め繁盛するという噺。客に誠意があれば、花魁もそれに応える気持ちを持っているという、庶民の願望を噺に仕立てた。【錦の袈裟】は、廓噺の中でも一番馬鹿馬鹿しくて、この稿の筆者が好きな噺。町内の申し合わせで錦の褌を揃えて吉原に繰り出したものの、褌が揃えられなくて坊さんから錦の袈裟を借りて締めてきた与太郎が、袈裟の輪故に殿様と間違えられて、一人だけ大いにもてるというお話。
2022年2月1日
