お役立ち情報
COLUMN
クラブATO会報誌でおなじみの読み物
「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!
日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、
その時々の時勢を分析していたりと、
中々興味深くお読み頂けることと思います。
絞り込み:
-

技術史観
この稿の筆者は、技術史観ともいうべき歴史観を持っている。
人類の歴史を動かすものは何か、というと、偶然か必然かは知らないが、ある一人の人間が発明した技術なのではないかと思うのだ。
たとえば、農業。狩り、漁、あるいは野原の植物を採取して食べていた人類が、あるとき、植物の種を集めて、蒔くという技術を発明する。そこから農業が生まれる。だが、木器や手で土を耕すのはきわめて困難である。その時、誰かが、金属を溶かして鍬や鋤を作ることを発明し、組織的な農業が可能になる。すると、社会の仕組みも、組織的な農業の営みに便利なように、「指示するものと指示されるもの」が生まれ、やがて、王制とか階級制度とかが生まれる。
つまり、道具の発明が初めにあって、社会の組み立てが後からついてくるのだ。けっしてその逆ではない。さらに言えば、人類には身についた「遊び心」「創造心」というものがあって、様々な人が、様々なものを発明する。が、その中から、周囲の人々の折々のニーズに合致し、「これは便利だ!」と言われるような技術だけが、生き残り、歴史を動かす。他の多数の発明は、単なる「遊び」「道楽」の結果として、歴史のかなたに消え去っていくのである。
技術こそが人類の歴史を動かす。深くは説明しないが、近代国民国家とか民主主義とかいう人類が歴史の過程で生み出した概念や思想は、折々の技術革新の産物なのである。
時間的な順序を言えば、まず技術が発明され、それが人々の折々のニーズに合致すると世の中に普及し、技術が世に普及するとそれを上手に使いこなすために、社会制度、ものの考え方、見方(思想や価値観)が変わり、さらには、社会の担い手が変わると、その新しい担い手によって、新しい文化や芸術が生まれるのである。
さて、ここからは、我々にとって身近な、一つの技術革新が、大きく社会を変えた事例を語ることにしよう。それは、避妊具、とりわけコンドームの発明である。
コンドームには、およそ三千年にわたる前史がある。動物の腸や魚の浮袋など天然の素材を用いて、性交の際の避妊や、あるいは性病を避けようとする技術が長く存在したが、一部の階級の遊興目的などに限られ、普及には至らなかった。そもそも、人類の長い歴史の大半では、人口が増えることを(生産力が向上するので)是としていたから、避妊は、不倫など特別な事例を除いては社会の一般的なニーズではなかった。むしろこれら技術の目的は、当初は性病予防の方にあったのかもしれない。ゴム製の工業製品としてのコンドームが本格的に出現したのは1874(明治7)年、現在のコンドームの基礎となるラテックス製コンドームが誕生したのは、1933(昭和8)年のことだそうだ。
さて、この技術が第二次世界大戦後、工業社会が成熟した先進国で、避妊目的で使われるようになるに及んで、社会の性道徳が大きく変わるのである。簡単に言えば、「健全な男女は結婚するまでは、性交しない」という道徳が崩れ、「大人になれば、誰でも好きな相手と性交するのが健全だ」という方向に大きく置き換わった。筆者の若年時代は、まさに嵐のような価値観転換が世界中で起きて、社会の仕組みや道徳が大きく変わっていった時期である。そのことは現在の、先進諸国における少子高齢化といった社会問題に直結している。そして、おそらく避妊具がもたらした新しい問題の解決には、AI、ロボットといった、別の新しい技術革新が求められるのであろう。
註:本稿は、相模ゴム工業のHP「コンドームの歴史」を参考にさせていただいた。
https://www.sagami-gomu.co.jp/condom/history/2020年1月1日
-

安田講堂
2019年1月18-19日は、東大安田講堂事件から数えて50年目にあたる。
だが、年齢の若い一般の読者にとっては、なんだかヘルメットをかぶった薄汚い学生と、警察機動隊が、投石と放水で大喧嘩している映像の印象があるくらいで、その事件がなぜ起こり、当時(1969年-昭和44年)の世相の中でどんな意味があったかをご存じない方も多いのではないか。
事件は、簡単に要約して言えば、当時数多く起きた大学紛争のひとつで、1968年2月に東大医学部で起きた無給医制度をめぐる紛争への大学当局の事態収拾が極めて拙劣であったために東京大学全学の学生たちが怒ってしまい、そのうち最も先鋭的であった東大全共闘の学生たちが本郷や駒場キャンパスの各校舎をバリケード封鎖し、新しく代わった大学執行部の説得もむなしく半年以上も封鎖が継続され、大学入試の実行も危うくなったため、ついに1月になって機動隊による学生排除が行われたが、結局政府の強い意向でその年の東京大学の入学試験は行われなかった。この事件を語った書物は多いが、詳しく知りたい方は、かつて本誌「今月の書棚」が取り上げた、小熊英二「1968若者たちの叛乱とその背景」〈上〉、〈下〉(新曜社刊)あたりをお勧めする。実は、本稿筆者の父親は、この事件の大学新執行部の一員であったので、筆者は比較的身近にこの事件のことを知る立場にいた。当時高校生であった筆者が思ったのは、なぜ(安田講堂などを占拠した)全共闘の学生達は、最後まで事態の収拾に応じなかったのだろうか、という疑問である。
大学新執行部は、全共闘の7項目の要求事項の内6項目と半分くらいは呑むと言っていたのだし、これが普通の労働組合のストライキなどであったなら、展望のない施設占拠を続けるより、さっさと交渉で手を打って「大勝利」の宣伝でもするところであるのに、ということに首を傾げたのである。実際民青系の学生達や無党派層の学生達は、最初の内こそ「東大民主化」とか言っていたが、1968年の冬になると、全共闘を排除して事態を「正常化」する方向に走っていた。
では、なぜ全共闘は展望のない闘争を続けたのか。それは、1968年の秋、東大の旧執行部が辞任する少し前頃から、彼らのこの紛争(闘争)にかける思いが大きく変化していったからである。
それは、一つには「日本の権力構造の上に君臨し、庶民の果てまでがその権威に幻惑されている、東京大学という存在そのものを、どうにかしない限り、個々の交渉事に勝利してもはじまらない」という「帝大解体論」の台頭であり、もう一つは、「自分たち東大生は、その権威の源泉である東京大学の一員であり、近い将来、官僚や有力企業の幹部、あるいは社会に影響を及ぼす学者などとして、このまま世に出て行く、それは自分たちの上で強権を振るってきた大学旧執行部と同質の存在に自分たちもなることなのではないか」という「自己否定論」の高まりである。この極めてナイーヴではあるが、ある意味では正しい思いに、急進派のとくにノンセクトの指導者達がとらわれたことが、どんな理屈をつけてでも「事態の収拾」「紛争解決」を拒むという、全共闘の頑なな姿勢となって現れたのだといえよう。一方で「正常化」派の学生達は、思想は右でも左でも、やはり「東大の権威」を守るために行動したのだといえるだろう。あれから50年が過ぎた現在も、我が国における「東京大学の権威」は、やや陰りが見えてきたとはいえ、あまり変わっていない。
2019年12月1日
-

撮影現場
この稿の筆者が、以前ビール会社に勤務し、広告主の立場で、コマーシャル制作をしていたことは、すでに何度か書いた。
30年前の当時、テレビCMはCFと言った。CFはコマーシャルフィルム、つまり映画の手法でつくられるものであった。今日殆どのテレビCMは ヴィデオとコンピュータグラフィックスの組みあわせで創られているが、筆者の時代は、フィルム映画型CMのちょうど最後の時代にあたる。日活調布、東宝砧などの映画スタジオにも良く通った。監督、制作さん、照明さん、キャメラさん、音声さん、メーク(化粧)さん、スタイリスト(衣装)さん、ヘアさん等々の大一座にさらに広告代理店の制作者と営業。それに広告主である私が加わって、まあ冷静に考えてみれば贅沢三昧の撮影現場の経験は、今では味わえないものがある。
映画の撮影現場というのは、ある一つの虚構を、大のおとなが何十人がかりで、ホントの世界にしてしまおうとする、なんとも不思議な魔術の世界であった。
たとえば、キャメラに写らない大道具の裏側の本棚も、けっしておろそかにせず本物の書籍を詰める、そうしないと「気分が出ない」という世界なのである。
撮影現場では、まず一本何秒というシーンの撮影が開始されるのに、(それが天気に左右されないスタジオ内であっても)、準備に数十分、数時間はざらにかかる。その主たる原因は、照明を決めるのに時間がかかるからである。ヴィデオが進歩する前のことだから、フィルムは基本的に対象物に十分の光が露出されないと、画面が暗くなってしまう。だから室内のシーンでも十分すぎる照明が当たるのだが、その電器の光が、あたかも自然光と同じような自然な陰をつくらないと「照明が決まった」とは言えないのである。照明さんは、そのために周りの都合などお構いなしに器具を右に振ったり左に振ったり、照度を強くしたり弱くしたりしながら一心不乱に調整する。そして照明が決まったと思うとキャメラさんに「どうでしょう」と尋ねる。キャメラさんが納得すると、今度は監督がキャメラを覗く。監督が納得すると今度は私、広告主の番で、キャメラを覗いて情景を確認し、茶道のお手前よろしく「けっこうです」とうなずく。何故広告主が、キャメラを覗くかというと、私が格別エライからではなく、巨額の広告費を掛けてつくるCFに後戻りはきかないからである。すなわち、広告主が試写を見てから「撮り直し」ということになったら、大損害が生じるので、予め現場で広告主の若僧の「うなづき」を得ておこうという、広告代理店の陰謀によるこの数秒間だけが、15秒のCMを撮るのに一日をかけるCF撮影現場における、私の出番なのであった。そして、いよいよタレントさんの登場。衣装、化粧、整髪によって作り上げられた「虚像」が、何秒かのシーンを演じる。「カァット!」という監督の声。OKかNGか一瞬現場に緊張が走る。現在のように撮ったシーンを、その場ですぐに見直すことは出来ないので、OKかNGかは監督の勘だけが頼りなのである。
なにもかもが人間くさい。そんな時代であった。
2019年11月1日
-

二つの日本
話は平安時代にさかのぼる。
平安朝の初め、律令に基づく口分田(人民に一律給わる農地=国有地)は、西日本に偏在していて、関東平野から東の耕地は少なく、未開の原野が広がっていた。京都の朝廷が軍を催し、蝦夷を征伐しながら東進すると共に、西日本の国有農地を逃散した農民や、朝廷の政策で植民された朝鮮半島の人々などが東日本の未開の原野を開拓し農地化していった。開拓地では、すぐに境界争い、水争いなど命がけの暴力沙汰が起きた。現地には、ぬきんでた実力を持つ調停者はいなかった。人々は、やがて京の貴族や寺社などに形式的に開墾地を寄進し、自分の土地を貴族の荘園とすることで保護を求め、境界争い、水争いを有利に導こうとした。東日本の土地はこのように、農民から見れば世を忍ぶ仮の姿として荘園になったのである。京の荘園主は土地を保護する代わりに、農民達を武装させ、京での彼らの警固や、争いごとへの武力サービスを求めた。武士の誕生である。その後京側の過剰なサービス要求に耐えかねた関東の武士達が、天下りの貴種(はじめは平将門、後には源頼朝など)を擁して武装決起し、関東を中心に自力で争いごとの調停役を立てたものが将軍であり、将軍による調停機関が幕府。幕府が荘園に派遣する代理人が守護、地頭である。
(ここまでは以前の本欄でも述べた)
守護や地頭は、鎌倉時代以降西日本の荘園にも派遣された。だが、西日本ではだいぶ事情が異なっていた。そもそも、西日本の荘園は、農民達が自力で開墾したものではなく、平安時代初期の国有農地が次第に京の貴族や寺社によって私領化されたものであって、武装農民が決起して自らの調停機関を立てるような事情にはなかった。守護地頭は鎌倉から派遣されてきたが、新たな権力者である幕府が武力を持っているから農民は彼らを受け入れたのであって、積極的に来てほしいと頼んだのではなかった。むしろ心情的には、旧来の荘園主である京の貴族や寺社、さらにその上に君臨する天皇の方が、西日本では親近感があり、敢えて言えば、幕府は西日本では心理的に遠い存在であったとも言える。
戦国時代の終わり、覇者豊臣秀吉は(偶々出自が低く、将軍にしてもらえなかったという事情はあるが)幕府を立てず、関白として疑似朝廷権力を摂り、その豊臣政権(公儀と呼んだ)を関ヶ原の合戦後微妙に換骨奪胎し実権を握るために、徳川家康は征夷大将軍となり幕府を立てる道を選んだ。秀吉は概して西日本で人気があり、家康は主に東日本で支持された。
さて、以上のことは明治維新の今日での評価を二分するものであることを書きたい。
戦後七十年を経て、もはや明治維新について薩長史観も徳川史観も、どちらが公式の歴史観かを争うような時代ではなくなってきた。にもかかわらず、昨今の時代劇や歴史小説を読むと、「明治維新の時、徳川幕府は因循姑息で新しい時代に耐え得ず、外国勢力と結んで国を危うくするおそれがあったので、薩長が天皇を中心に新しい権力を打ち立てた」説と、「江戸時代を通じて徳川幕府は社会の緩やかな近代化に成功しており、幕末開国後の外交にも大過はなかった。明治維新は外国に使嗾された薩長の権力奪取の陰謀に過ぎない」説が拮抗している。どちらも背後で英仏と手を握りはしたが、日本の独立が破れる直前で手打ちにしたことは周知の通りである。が、上記両説の背景に、西日本と東日本の感じ方の違いを見るのはこの稿の筆者だけだろうか。
2019年10月1日
-
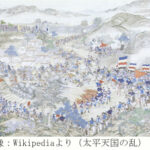
方法論
1960年代の後半、この稿の筆者が高校生だった頃に、我が高校にちょっと変わった、世界史の若い先生がいた。その先生は、東大の大学院のたぶん博士課程くらいの院生だったのだと思う。専攻は東洋史で、中国の農民叛乱の研究をしていた。
で、私たちの教室に来ても、彼は中国の農民叛乱の話しかしないのである。中国の王朝は古今必ずと言ってよいほど農民叛乱で倒れているから、上は秦代末期の陳勝・呉広の乱から、下は清代末期の太平天国や義和団の乱まで、ちょっと詳しく語れば一年はすぐにたってしまう。 先生は涼しい顔で、学年末に「ちょっと中国を詳しくやり過ぎたから、あとは教科書を読んどいて」と言って、狭小な範囲の世界史の講義を閉じたのであった。
彼の講義自体は素晴らしいもので、私たちは中国各王朝の郷村管理のやり方から、専売制、結局何故農民は反乱を起こすのか迄すっかり詳しくなったが、一方で、インドのことも朝鮮のことも殆ど知らない高校生となった。
そして、受験がやってきた。筆者は、世界史が大好きで、得意でもあったので、国立も私立も社会科は世界史を選択することにした。と、言ってもこのままでは、世界史の受験をしようがない。別の事情があって、筆者は高校3年の6月まで学園祭だの何だのにかまけていたので、時間は7-8ヶ月しかない。そこでまず当時中央公論社から刊行されていた堀米庸三編「世界の歴史」全24巻というのを親に買って貰い、全巻読破することにした。これにも訳があって、机に向かって英語だの数学だのほかの受験勉強をしていると程なく飽きてくる。そこでテレビを見たり、漫画を読んだりしてしまうと勉強にならないので、ベッドの上にごろごろしながら、「世界の歴史」各巻を読むのである。これは楽しい営みであるから、勉強を放棄しないでうまい具合に実質休憩することが出来る。全24巻は、だいたい秋頃には読了したのだったと思う。幸い「世界の歴史」には、インドのことも朝鮮のことも書いてあったから、ムガール帝国や李氏朝鮮も頭に入った。最後に王様の名前や歴史上の各事件の起きた年などは、丸暗記するしかないので、1月になって入試が近くなってから、代々木ゼミナールの一日中一週間で全世界史をやる「武井の世界史」というのに通って無理矢理頭に詰め込んだ。(もちろん試験後すぐに暗記したことは忘れてしまったが)
そして、この稿の筆者は無事その世界史で、程々に点を取って、程々の私立大学になんとか潜り込むことができた。
この世の人々は、学校の授業を評価するときに、すぐに「それは受験に役立つか」を問おうとする。その基準で言えば、上記の中国の農民叛乱だけの授業など、受験には、何にも役立たない。だが、この稿の筆者は、「世界の歴史」全24巻がすいすいと頭に入ってきたのは、彼の東洋史の先生が、「歴史にアプローチする方法論」を中国の農民叛乱というサンプルを通じて教えてくれたからだと思っている。人知の範囲は無限であって、その全てを学校教育で教えることは出来ない。ならば、学校が教えるべきなのは、「知にアプローチする方法論」であって、大量の知識ではないのではないか。
2019年9月1日
-

名古屋の嫁入り
今から、約四十年前のこと。この稿の筆者は、ある中堅の飲料メーカーに就職して、名古屋支店に配属された。支店は、市内中心部の栄、独身寮は栄からバスで15分くらい行った鶴舞公園の近くにあった。ある日のこと、独身寮の近くの住宅地を、子供たちが「お嫁さんだ」と叫びながら駆けていく。すると、箪笥などの嫁入り道具を2トントラックに積んで、紅白の帯を掛けたものが、後ろにトヨタの新車を従えてやってくる。花嫁御寮のご実家の前に止まると、そこで花嫁の父に当たるらしい人が、集まった近所の人々や子供たちに簡単な挨拶と道具の披露。そして、2トン車が新郎新婦の新居に向けてスタートすると、子供たちのお目当て、吉例の餅撒きが行われ、子供たちは三々五々菓子袋などを拾って帰るのである。
この道具の披露と道具の移動というものが、当時の名古屋の風俗に於いては、きわめて特徴的であった。新婦の家が金持ちであったら、結納に併せてホテルの部屋を借り、親戚一同に道具の披露をするし、新婦の家が貧乏で、近所にお披露目をするのに十分の道具を調えられなければ、金持ちの家の道具を借りて、「見せ道具」ということを行った。何故新居に運んだはずの道具を、実家が貸すことができるかというと、すでに名古屋でも核家族化は進んでいて、新郎新婦の新居なるものは、社宅、あるいはマンションやアパートであり、要するに金持ちがホテルで披露した道具を全部収納することは不可能だったからである。入りきれない道具は、実家にそっと戻され、それを第三者に貸す商売をする家もあったというのが真相である。当時(昭和50年代)、名古屋地方では、「在所」と呼ばれる嫁側の実家が、生まれてきた孫の七五三までの諸掛かりを負担するという習慣があった。婿側はと言えば、せっせと在所に足を運び、在所の両親が「我が家はこんな立派な婿殿に娘を嫁がせている」と近所に自慢できるようにしなければならない。だから、名古屋大学を出て、東海銀行、中部電力、中日新聞など地元の有力企業に就職している婿殿は価値が高く、いくら有名企業でも日本銀行とかNHKとかは好まれない。何故なら転勤が多く、在所の側が婿殿を自慢する機会を逸失する可能性が高いからである。
名古屋においては、道具の披露も、婿の自慢も、いずれも「在所の近所に対する見栄」によって成り立っている。日頃は、家計をうんと引き締めても、それは近所への見栄を果たすための資金づくりなのであって、いざ嫁入りともなれば、周囲に道具を見せ、披露宴の引き出物も「しーっかりと大きいものでにゃあとよう」という客人のニーズを満たすものを用意しなければならない。
この稿の筆者は、引き出物が出ない披露宴があり、招待された客が怪訝に思いつつ帰宅すると組布団が届いていたという話を知っている。また、名古屋人の仲人と、東京者の新郎新婦という組み合わせで、新居に家具を適当に調達して運び込んだところ、「仲人の立ち会いもなく、勝手に道具を搬入したので、仲人の顔をつぶされた」と怒られ、仲人を降りる、降りないという騒ぎになって、道具搬入をやり直したという例もある。名古屋に於いては、道具の移動こそが、結婚の神髄であったのだ。はたして、今もその習俗は続いているのだろうか。
2019年8月1日
-
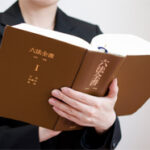
法律の知識
かねて疑問に思っていることがある。中学校、高校で法律をどのくらい教えているか、ということである。たしかに憲法は多かれ少なかれ、教わる。内容はだいたい基本的人権や三権分立(世界の民主主義国家に共通する項目)と、象徴天皇制、戦争放棄、議院内閣制(我が国に特徴的な項目)くらいである。だが、憲法の諸項目は、日本という国家がどう組み立てられているかを知る上では、重要だが、正直に言えば実際の市民生活からは、やや感覚的に遠い。
この稿の筆者が問題にしたいのは、市民生活に密着し、誰もが直接お世話になるような法律が、大人になるまでに教えられているかということである。成人年齢は2022年から18歳ということになるらしいが、市民生活に関係の深い法律を知らないまま成人になる者が増えるのを危惧するのである。
たとえば、以下のような法律の定めは、学校で教えられているのだろうか。
まず、民法。婚姻、出生、死亡の手続き、離婚に関する定め。何歳から自分の判断で結婚できるのか、夫婦間の権利義務、姓に関する法の定め、相続に関する原則、遺言、墓や祭祀に関する定め。
次に、労働三法。大半の国民が成人になると誰かに雇用される社会であるわけだから、労働時間、休暇、残業、定年などに関する法律の基本的な定めは知っておく必要がある。正規雇用と非正規雇用のちがい、契約社員の権利等。世間のブラック企業は、従業員が法律をよく知らないのをよいことに、違法な雇用形態を違法と思わせないで押しつけたりするわけだから、こちらも「市民の常識」として、労働関係の諸法規を知っておかなければならない。
さらに、年金関係の法令。年金のお世話になるのは、何十年も先かも知れないが、社会保険を負担するのは成人になってすぐだから、払う側の立場として年金の仕組みは知っておかなければならない。国民年金、厚生年金と共済年金の区別。年金は、何歳からどれだけ貰えるのか。そして健康保険や介護保険の仕組みなど。年金請求の手続き。そして、お金と言えば、税法も少しは知っておいた方が良い。所得税、住民税、消費税等の税率と徴税のやり方、不動産を所有していれば、固定資産税なども負担するわけだから、それぞれの仕組みがどうなっているのかを知っておく必要がある。
最後に、道路交通法や刑法。これは、市民として「知らないうちに法を犯している」リスクを避けるための、最低限度の知識が必要である。刑法をよく読んでみると、「え?こんなことが犯罪なの?」という条項に遭遇することも多い。道路交通法に至っては、貴方も私も、毎日1回や2回は法律違反を犯しているかもしれないような、現実とかけ離れた法律である。自分では正しい行いをしているつもりでも、知らない法律に違反して、裁判所のお世話になることもあるだろうし、他人から訴訟を起こされることもあるだろうから、刑事、民事の訴訟法(裁判)の知識も少しは必要である。
この稿の筆者の提案は、高校1年か2年頃に、週2時間「市民のための法律知識」というような授業を必修で行うべきではないか、というものである。
2019年7月1日
-

「何をしてでも勝ちに行く」体質
こちらにUPされている記事は会報誌に掲載後の記事であるため、この稿の筆者が原稿を書き上げてATOの編集者に渡してから、このページにUPされるまで、かなりの時間がある。時事問題を取り上げると、話題の鮮度が落ち、その後の展開によっては、筆者の主張がピンボケになってしまうことがありうるので、時事問題は書かないようにしてきた。
ところが、最近「時事問題は書かない」という禁を破っても、書かずには居られない事件が起きた。
それは、日本大学アメリカンフットボール部の悪質タックル事件である。この事件は、「昭和の原風景」にもつながるし、何故日本の優良大企業が数十年間も自己の製品の計測値をごまかして顧客に売るというルール違反を繰り返してきたか、という問いにもつながる根深い問題をはらんでいる。
(世間一般が事実と思っている)この事件の経緯をスケッチする。日本大学アメリカンフットボール部の監督とコーチは、かなり優秀で将来有望な選手が、ルールどおりのスポーツマンシップを信奉し、何が何でもがむしゃらに勝ちに行く姿勢が見えないことに不満を感じていた。監督、コーチの価値観からすれば、スポーツは闘争であり、何をしてでも勝ちに行こうとするような闘志が、この選手には足りないように感じられた。そこで、わざとその選手を干し、日大の試合にも全日本のメンバーにも出られないように仕向けた上で、「当該選手が戦列に復帰するためには、反則をしてでも、相手選手を潰す(怪我をして試合に出られないようにする)行為をやり遂げる必要がある」と(少なくとも当該選手が理解するような言い方で)宣告した。追い詰められた当該選手は、監督、コーチの命令(か示唆かは問わない)を遵守し、試合冒頭反則によって相手選手を怪我させることに成功したが、第二、第三の反則を重ねて退場となると、自らのスポーツマンシップを意図的な反則によって汚したことに気づき、テントの中で号泣していた。一方、監督、コーチは試合直後の時点では、当該選手の行為を「よくやった」と評価し、「反則は監督がやらせたと書いてよい」と報道陣にもコメントしていた。ところが、悪質タックルの画像が世間に流布され、場合によっては刑事事件に発展する可能性も出てくると、監督、コーチはたちまち前言を翻し、「当該選手の行為は監督、コーチの励ましを誤認した結果であり、監督、コーチは反則や相手選手を怪我させる指示はしていない」と居直った。一方で当該選手は、自ら進んで記者会見の場に出て、相手選手に謝罪し、経緯を暴露した。
さて、筆者が先ず思ったのは、BC級の東京裁判で、捕虜の処刑など国際法に反する日本軍の行為を問われたとき、現場で手を下した者は上位者の命令で行ったと言い、上位の司令官や参謀は「そんな命令はしていない」と惚けたという構図である。そして第二次世界大戦中、わが国がなぜ国際法を積極的に守ろうとしなかったかを問えば、「総力戦とは国家間の、食うか食われるかの存亡を賭した闘争であり、ルールに基づいて行うゲームではない」という考えが上級者の中にあったからだと思う。さらに言えば、昭和、平成を通じて企業が体育会出身者を採用したがってきたのは、さわやかなスポーツマンがほしかったからではなく、「何をしてでも勝ちに行こうとする」者がほしかったからではないか。「何をしてでも」の中には、製品検査の計測値をごまかすような反則行為を含んでいたのではないかと思うのである。一方で、本事件の救いは、加害側選手がテントで流した号泣の涙と、後日毅然と真相を世間に語ったその自立性である。ルールを守り、その中で最善を尽くすという本来のスポーツマンシップが、日本の伝統的な体育会体質を超えた、新しいクラブスポーツの可能性を拓くことに期待したい。
2019年6月1日
-

昭和の原風景 その2
昨月は、昭和のはじめ、震災復興とともに、渋谷、新宿、池袋など主に山手線の駅をターミナルとする私鉄が敷かれ、その沿線に住宅地が形づくられ、中産階級上層というべき給与生活者の市民層が形成され、独自の文化、教養、倫理観などを持つようになったことを書いた。
そうした東京の風景を描いた歌謡曲の歌詞を以下に紹介する。
1.花咲き花散る宵も 銀座の柳の下で 待つは君ひとり 君ひとり 逢えば行く ティールーム
楽し都 恋の都 夢の楽園(パラダイス)よ 花の東京
2.うつつに夢見る君の 神田は想い出の街 いまもこの胸に この胸に ニコライの 鐘も鳴る
楽し都 恋の都 夢の楽園よ 花の東京
3.明けても暮れてもうたう ジャズの浅草行けば 恋の踊り子の 踊り子の 黒子さえ 忘られぬ
楽し都 恋の都 夢の楽園よ 花の東京
4.夜更けにひと時寄せて なまめく新宿駅の あの娘はダンサーか ダンサーか 気にかかる
あの指輪 楽し都 恋の都 夢の楽園よ 花の東京
5.花咲く都に住んで 変わらぬ誓ひを交わす 変わる東京の 屋根の下 咲く花も 赤い薔薇
楽し都 恋の都 夢の楽園よ 花の東京
~門田ゆたか作詞 古賀政男作曲 「東京ラプソディ」 歌 藤山一郎~ところが、一方にこの「楽し都」を苦々しく思う人々もいた。
以下は、のちに5・15事件を起こして犬養首相を暗殺した、三上卓が作詞した「青年日本の歌」の二番と三番である。
二.権門上に傲れども 国を憂ふる誠なし 財閥富を誇れども 社稷を思ふ心なし
三.ああ人栄え国亡ぶ 盲たる民世に踊る 治乱興亡夢に似て 世は一局の碁なりけり三上の目には、「楽し都」を謳歌する市民たちの姿は、「盲たる民」にしか見えなかった。
それは何故か。一言でいえば、「変わる東京」は、「変わらぬ農村」を置いて発展していったからである。農村側からは、大都会東京のモダンな姿は、農村の富を収奪した結果にしか思えなかった。
たとえば、カフェのダンサーは、多くは農村から何かの事情で都会に出てきた娘たちであった。
彼女たちは、食べるために都会の紳士たちと「援助交際」をすることもしばしばあった。風俗はモダンにかわっても、それは封建的な枠組みで娘を遊郭に売ってきた、江戸時代以来の長い農村の歴史の延長にしか見えなかっただろう。
つまり、その頃、ものごとは二重の様相を呈していた。都会の先端では、たしかにモダンでリベラルな新しい市民文化と価値観が生まれつつあった。それは、戦後のデモクラシーにもつながる重要な変化であった。が、新しく生まれつつある都会の市民文化の陰では、うわべの風俗だけはモダンでも、農村の大地主制と封建的な価値観がそのまま息づいていたのである。
昭和初期の不況は、その農村を直撃した。その農村を救済しなければならない、というのが血盟団などの右翼テロリスト、5.15事件、2.26事件の陸海軍将校たちの主張であった。
昭和の原風景は「楽し都」と「盲たる民」のせめぎあいの間にあったのである。
※1.2.3.4.5.は門田ゆたか氏作詞「東京ラプソディ」、二.三.は三上卓氏作詞「青年日本の歌」より引用
2019年5月1日
-

昭和の原風景 その1
今上天皇の退位が決まり、元号としての平成は31年4月までとなることになった。
その前の昭和が64年であるから、あわせると略百年となる。百年前のこととなると、たとえば我が家の息子達にとっては気が遠くなる程昔に感じられるらしい。だが、その頃の風景を顧みることで、私達の「今」が見えてくることも多いと思う。そこで、これから数回にわたって、様々なトピックスから昭和の原風景というものを取り上げてみたい。
今月は、相浦忠雄というまったく無名の戦死した若者のことを書きたい。この人は、戦後総理大臣となった宮沢喜一と旧制高校の同期で、宮沢が大蔵省に入った時に、商工省に入って役人となった。が、その後すぐに海軍の主計科短期現役士官となり、客船八幡丸を改造した空母雲鷹に主計長として搭乗している時に、米潜水艦に乗艦が撃沈され戦死した。宮沢が総理に就任した時に「相浦が生きていたら自分より先に総理になっていたかも知れない」と言ったそうだから、相当優秀な人だったのだろう。さて、その相浦のトピックスである。
トピックスのひとつは、昭和16年12月8日開戦が決まった日に、後輩を東大安田講堂の屋上に連れ出して、「この東京の町が火の海になる」と断言したこと。しかし、そう思いながらも、海軍の軍人となり、空母雲鷹が最後の航海に出る時も「この艦は必ず撃沈される」と言い、事実米潜水艦の魚雷を受けて乗艦が傾くと艦橋で主計長の職責を最後まで果たした後で、救命胴衣を持たない便乗者に、自分の救命胴衣を譲って艦と運命を共にしたのだという。 相浦はけっして勇敢な軍人タイプではなかった。彼が残した遺稿集を読むと、戦争という抗い難い運命に直面して様々なことに懊悩し、その悩みを綴っていることがわかる。その悩みは、たとえばほぼ同時期に主計科短期現役士官から乗艦の主計長になって戦死した小泉信吉(小泉信三著「海軍主計大尉小泉信吉」参照)に比べても、かなり屈折しているし、深いものがある。にもかかわらず、彼が人生の最期の場面で、何のとらわれもなく、救命胴衣を便乗者に譲ろうとした心事を、今、思うのである。
飛躍するようだが、この稿の筆者は、それを昭和初期の都市近郊給与生活者のモラルというものではないかと考えている。渋谷、新宿、池袋といった山手線の駅をターミナルとして東京近郊に広がる私鉄沿線の住宅地に住み、都心の会社や役所に通う、当時としては恵まれた人々。だが、華族でもなく資本家でもない、大正の終わり頃から漸く形成され始めた中産階級。昭和初期のその人々の多くには、たとえば吉野源三郎「君たちはどう生きるか」の主人公コペル君に見られるような、深い教養と知性に裏打ちされた教育を子女に与える文化があり、その教育が培ったリベラルなインテリジェンスが、相浦忠雄のモラルの源泉になったのではないか、と、思うのである。武士道でも、Noble obligeでもない、都市中産階級の知性に基づくモラル。だが、それは戦後、その中産階級が大衆化する中で、次第に失われていく。昨今の役所や企業の、組織ぐるみでコンプライアンスに違反する行為を見るに付けても、「相浦忠雄のモラル」への思いは深い。
2019年4月1日
-

部活動
昨今の学校教員は、とにかく忙しい、という話である。
今号では、その中で、一応中学、高校の先生の仕事にフォーカスする。
教員の仕事を洗ってみると、だいたい次のようなものになる。
1 授業とその準備(教員自身の研究・研修も含む)
2 授業以外の(たとえばクラス担任等としての)生徒、保護者との対応
3 部活動の顧問
4 各種の管理事務(成績評価、色々な報告書作り等の事務仕事)
5 会議これらの中で、何か減らせるものはないかと文部科学省が考えた末に、3を誰かほかの教員以外の人に肩代わりしてもらえないか、という話になった。ところが、言うは易くで、これがなかなか難しい。要は、とくに運動部系の練習、試合等の途中で何かの事故が起きた時に「教員がその場に居なかったというのでは、無責任だろう」という社会の風潮があって、社会人コーチなど代わりの人に顧問の仕事を全部任せることを、世間も良しとしない傾向がある。そこで、部活動の日数などを制限して先生を楽にしようということも試みたが、これも運動部の生徒達は隣の学校に勝ちたいと思って部活動をしているのだから、公式練習を減らしても、プロ野球の自主トレ期間みたいな闇練習が出てきてしまい、教員の実質的負担はあまり減らない。
さて、何故こんなことになってしまったのかを考えてみたい。それは、近代社会が成熟するに連れて、教育というものをなんでも学校に押しつける傾向が顕著になってきたからなのではないか。昔(とは言っても近代社会が始まった頃まで)は、教育というものは家庭、地域、学校の三者で担うものとされてきて、実際に躾けや道徳の類は家庭が、体育運動や青少年の精神的な成長については地域が(たとえば薩摩の郷中や各地の青年宿、青年団等の形で)多くを担ってきた。
都市化、核家族化が進み大家族や地域コミュニティが実質的に崩壊する中で、いつの間にか、躾けや道徳、スポーツや精神的な成長についても、学校しか担える機関がなくなってしまい、社会も学校にそれらを全て期待するようになってしまったのだ。この稿の筆者の対策提案は、地域教育の復活。部活動を学校から切り離して、地域のクラブとし、定年後まだ元気な社会人によるNPOをつくって、その法人が生徒達を指導管理するというものである。少子化が進み、一校ではチームが成り立たない時代は、もうすぐそこまで来ているのだから。
2019年3月1日
-

これでいいのだ
我が家の息子達に、将来どんな大人に育ってほしいか、という話である。
息子達には、幸せになってほしい。が、親が描く将来像を、そのままなぞることが、本人の幸せとは限らない。そもそも今の世の中、これぞ立身出世であるというような、明白な出世街道はない。
また、この稿の筆者には、息子に継いでほしい職業があるわけでもない。さらに、本題ではないので詳しくは書かないが、金持ちになる、高給取りになることを人生の目的に生きるような者は、多くの場合はその目的を実現できないし、仮にカネを手に入れることが出来ても、あまり幸せではない。
その中で、筆者が、少数だが、これは幸せな稼業ではないかと思えるものがある。それは、プロスポーツの選手、歌手や俳優、画家、作家、学者等々若年の頃からやりたいと思ってきた何かの「面白いこと」をそのまま職業にできる人々である。これらの人々は、飯を食うために職業を選んだのではなく、自分が面白い、楽しいと思えることをやっている内に、そのことで飯を食えるようになってしまったのである。別に上記のような有名人ではなくても、工員、職人、教師、あるいはただのサラリーマンの中にも、自分が一番面白いと思うことをやっている内に、それが職業になってしまった人がいて、そういう人は周囲の同業の仲間より幸せである。要するところ、自分の好きなことを飯の種に出来る者が幸せなのである。我が家の息子達には、ぜひそうなってほしい。
と、ここで結論が出たように、読者は思われるかも知れない。だが、そうではない。「自分の好きなことを飯の種にする」ためには、いくつか人生の作法のようなものがあって、最近の学校教育では、まずその作法を教えてくれない。親は子供にその作法が身につくように導かなければならない。
まず、若い間に、「自分は何が好きか」を見つけられるようにしなければならない。「好きなこと」は、やりたいことがないから取りあえず行う「暇つぶし」とはちがう。
あるいは、歌が好き、野球が好きな者はこの世に多数いるが、命を掛けてその道を究めたいほど好きかと問われれば、職業ではなく、カラオケや早起き野球でも良しとする人の方が多いのではないか。命を掛けるためには、才能も含めて、自分がその道に惚れぬける何かがなければならない。
世間には、どんな男、あるいは女に惚れたらよいかを説く人はいるが、そもそも、どうしたら相手を惚れることが出来るかを教えてくれる人は、殆どいない。ほんとうに惚れるためには、結局は出会いを繰り返すしかない。恋愛がそうであるように、様々なものに出会わなければ、相性のよい対象に「惚れる」という現象はまず起きない。最初の出会いが一生を決めるというのは、きわめて稀だ。
最後に、世間には何をやっても、何を得ても「これでいいのだ」と思えない大人がいる。そういう人は、他人を惚れることを知らない不感症の美男美女のようなもので、不幸である。他者がよいと支持する「ブランドもの」ばかりを追いかける人も、「これでいいのだ」という自己肯定感を持てない人生の漂泊者である。これからの未来ある子供達には、「ブランドもの」の学校や企業に入ることを勧めるよりも、他はともあれ、自分だけは「これでいいのだ」と思える何かを見つけることができるように、そのための出会いの場を、数多く用意してあげるのが、人生の先達である大人の役目なのではないか。
2019年2月1日
