お役立ち情報
COLUMN
クラブATO会報誌でおなじみの読み物
「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!
日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、
その時々の時勢を分析していたりと、
中々興味深くお読み頂けることと思います。
絞り込み:
-

タンゴ その2
前回は、日本におけるタンゴの風俗史のようなことを漫然と書いたので、今月は、タンゴの音楽史を要約して書くことにする。
タンゴは、1870年頃アルゼンチンは、ブエノスアイレスの港町、「ラ・ボッカ」で生まれた。
タンゴは、(日本の演歌が西洋音楽と民謡との混交であるように)ヨーロッパのクラシック音楽と南米の民族音楽などの混交である。タンゴの父が西洋音楽とすれば、母はミロンガという、ラテンアメリカの田舎のカウボーイ(ガウチョという)の民謡である。延々とした語り、節回しなど、ミロンガは日本の民謡とも共通するところがある。(民謡の歌詞は、恋愛や故郷への慕情などだが、本質に於いては、牧畜、農作業、漁労などの間に歌われる労働歌である)
さらに言えば、ミロンガ自体が、白人とインディオの音楽の混交である。田舎者の民謡ミロンガが、都会ブエノスアイレスのイタリア系船員の街「ラ・ボッカ」で、西洋生まれの楽器や旋律と出会い、船員や沖仲仕の集まる酒場の舞踊の曲として生まれたのがタンゴである。タンゴという言葉は、1880年出版された「バルトール」という曲の楽譜表紙で初めて公に使われたとされている。(この時代音楽配信やCDという便利なものはなかったので、音楽の普及は専ら楽譜の出版によった)
それから、僅か16年後、タンゴは海を渡った。アルゼンチン海軍の練習艦サルミエントが欧州を訪問。艦上の軍楽隊がタンゴ「ラ・モローチャ」を演奏し、欧州人に楽譜を配った。この時代の少し前、日本なども万国博覧会に芸者衆を出演させて日本文化を訴求したりしているが、当時西洋文明の片田舎アルゼンチンとしては、タンゴを自らの文化の象徴として訴求したかったのだろう。ともあれ、この海軍の試みが奏功して、港町の演歌タンゴは、近代世界に知られるようになった。
1911 年 ヴィセンテ・グレコ楽団がオルケスタ・ティピカと称する。この頃、ドイツ生まれの楽器バンドネオンが、オルケスタの主役として定着する。
第一次世界大戦を経て、大戦後のヨーロッパには、アルゼンチンからカルロス・ガルデル(1923年渡欧)、フランシスコ・カナロ(1925年渡欧)などの楽団がやってきて、ポピュラーミュージックとしてのタンゴの一大ブームを巻き起こした。この時代、本場アルゼンチンの上流階級は、下層階級の演歌タンゴを白眼視していたのだが、囚われのない若者達によってタンゴは世界に普及し、それを見た故国の上流階級がやっとタンゴを認めるようになったというのも、日本でもありそうな話しである。
本場の泥臭いアルゼンチン・タンゴから、欧州社交界向けの洗練された、甘い旋律のコンチネンタル・タンゴが生まれた。一方で、タンゴの名曲として今日なお一日24時間世界のどこかで必ず演奏されているという「ラ・クンパルシータ」が歌詞付きで流行するようになったのもこの頃のことである。
紙数が、尽きそうなので、最後にアストル・ピアソラという人についてふれる。ピアソラは、1941年にデビューしたバンドネオン奏者、作曲家である。第一次世界大戦後の、ガルデルやカナロ達がタンゴをポピュラーミュージックとして世界の舞台に上げたとすれば、ピアソラの功績は、第二次世界大戦後の新しい世界で、タンゴを基礎としながら、ジャズやクラシックとフュージョンさせ、現代音楽として羽ばたかせたことにあるだろう。守旧派からは、時に「タンゴの破壊者」と譏られたピアソラだが、今日タンゴを知らなくても、ピアソラを知っている音楽ファンは多い。1992年没。
出典:2009 年11月 16日 松井清治「アルゼンチン・タンゴ歴史年表」他より
http://www009.upp.so-net.ne.jp/fial/activity/data/fial_FTS12_0911b.pdf2017年1月1日
-

タンゴ その1
この稿の筆者が、大学時代放送のクラブに属していたことは以前書いた。
そのクラブは、百数十人も部員がいる、いわゆる「文連大手」のクラブで、六大学野球のアナウンスやら、学園祭のPA(バンドなどの音声調整、ミキシング)、卒業レコードの制作などでしっかりビジネスをしていて、世間のちょっとしたプロダクションみたいな感じであった。そのビジネスの一環で、学内のバンドに司会者を派遣するという業務があった。
クラブのアナウンス部門に所属する男女の部員を、軽音楽だとか、ハワイアン、ジャズ、タンゴなどのバンドに「出向」させるのである。それらのバンドの司会者は、代々放送のクラブの部員がつとめることになっていて、出向者は四年生になると、適当な後輩をみつくろって後継者として育てるのである。数あるバンドの中で、筆者が何故タンゴの司会者に選ばれたのかは、よくわからない。まあ、ライトミュージックとかモダンジャズの素養には欠けていたから、バンドの中でも比較的「堅そうな」イメージのあるタンゴが良さそうだと言うことになったのかもしれない。その時筆者は、全くタンゴなんていう音楽は知らなかったのだが、「来週から本番だから」とかいわれ、先輩がつくった手書きの曲名紹介のノートと音楽之友社刊「タンゴ入門」とか言う本を渡されて、慌ててそれから勉強することになった。
タンゴが生まれたのは、概ね明治維新の頃。筆者が学生であった1970年代でも約百年しか過ぎていない。南米のインディオの音楽と西洋音楽がほどよく混交して出来た、まあブエノスアイレスの港の酒場から生まれた演歌のような音楽である。あまり上品な音楽ではない。バンドネオンというアコーディオンの鍵盤がなくて両サイドがボタンになっている楽器が特徴で、バイオリンやピアノが奏でる甘いメロディーに、このバンドネオンがチャッチャという刻みのリズムを入れていくのである。歌の内容は、殆ど、女に振られた男の未練を歌うもので、本場では、これにほとんどセックスを様式化したと言えるような妖艶な踊りがつくことになっている。
筆者が、タンゴバンドに出向して司会者を務め始めた時代は、いわゆるパーティー券を売るダンスパーティーの最後の時代であった。体育会などの学生のクラブが、部費稼ぎに、同じく学生のバンドを雇ってきて、ダンスパーティーを催すのである。食べ物や飲み物は現代の政治家のパーティー並みにプアであったが、音楽だけはすばらしかった。
当時は、合コンというものはまだない(筆者が大学を卒業する頃、いわゆる合コンが始まった)ので、このダンパが男女の出会いの場を提供したのである。はじめはワルツ、そのうちタンゴなど踊るのに難しい曲が流れ、最後に明かりが暗くなってスローなテンポの曲が流れて、一同チークダンスという場面になる。筆者も、名前を知らない女子学生とぴったりくっついて、ダンパのチークタイムを過ごしたことが何度かある。
タンゴバンドはダンスパーティーの花であった。一年に何回もダンパをこなせば、貧乏な学生の遊ぶ金くらいは稼ぐことが出来た。やがて、ゴーゴーそしてディスコティックの時代が来て、この難しい音楽で踊ろうという学生の数は次第に減っていった。
~この項続く~2016年12月1日
-

裁判員制度
映画TED2を見てきた。
TEDは、魂の入ったテディベアのお話しである。まず、前作TEDを簡単に紹介する。
ボストン郊外に住む少年ジョンは、1985年のクリスマスプレゼントに貰ったテディベアのぬいぐるみを愛し、魂が宿るようにと祈る。その願いが叶って翌朝くまは友達のように口をきく存在になっていた。TEDは一躍町の人気者になり、テレビなどにも出演するがやがて飽きられ、世間も騒がなくなる。それから27年、2012年のボストン。うだつの上がらない中年男ジョンと、親友のTEDは一緒に暮らしている。休日にはマリファナをふかす不良中年の二人。が、ジョンの恋人ローリーに素行不良をとがめられ、出て行ってほしいと言われたTEDはジョンの部屋を離れて、スーパーマーケットに就職、独身生活を始める。そこにTEDを狙う変質者が現れ・・というようなお話し。他愛がないと言えば言えるが、アメリカの中産階級下層のあまり上品でない暮らしや言葉が実によく描かれていて、「あ、これが民主党のアメリカなんだな」と妙に納得させられる。(それに比べれば、本誌「今月の書棚」がしばらく前に取り上げたジャック・ライアンシリーズなどは、明らかに共和党のアメリカの世界である)
さて、TED2では、スーパーのレジ打ちの女の子と結婚したTEDが、ちょっとした夫婦喧嘩が元で、子供を持ちたいと思うところから始まる。ぬいぐるみTEDに生殖能力はないというのが物語上の設定になっていて、TEDはまず人工授精を考える。親友ジョンとの間のヒーロー、フラッシュ・ゴードン(かつてのB級アメリカ映画のスーパーヒーロー)やアメリカンフットボールの有名選手の精子を取得しようとして失敗したり、ジョンの精子を貰おうとして生殖バンクでドタバタ劇を演じたりという場面があった後、TED夫妻は方針を変えて養子を貰おうと斡旋所に行く。人工授精から養子斡旋へというあたりの扱いが、日本ほど深刻かつWETではなく、きわめて「あたりまえ」のこととして推移するのも、いかにも現代のアメリカを感じさせる。ところが、養子斡旋手続きの過程で、TEDが人格を持ち、結婚していること自体が「行政手続きのミスであった」と州政府が言いだし、TEDは戸籍を失い、クレジットカードも、職場も全てを失ってしまう。そこでTEDは、裁判による人格の回復にチャレンジする。(「そこで訴訟」というのも米国の文化だろう)
親友ジョン、アリゾナ州立大出身の若い駆け出し女性弁護士、TED夫妻の4人ティームと、TEDをモノとして扱い、ぬいぐるみの内部を解析して量産しようとする「共和党系の」金持ち企業家+第一話に登場した変質者のコンビが州政府側に加担しての裁判劇が始まる。
この裁判劇について筆者が特筆したいのは、TEDがモノかヒトかという裁判の主題が、150年昔の米国の奴隷解放裁判にすべてアナロジーされていることと、第一審で負けたTED側に、有名な黒人人権弁護士が「陪審員は、理屈ではなく人間的な感情によって裁く」という助言を与えるシーンである。結末に飛べば、TEDはそのヒトの情に訴えて見事勝訴するのだが、「裁判員裁判は理屈じゃない」という言葉が、妙に印象に残る映画であった。
2016年11月1日
-

結界
古代ローマ帝国が存在したのは、だいたいだが紀元前27年(アウグストゥスによる帝制開始)から、紀元476年(西ローマ帝国滅亡)まで。約500年間、そのうち栄えたのは最初の200年くらい。世界史上、そのくらいの長さの国は他にも例がないわけではないが、なんと言ってもローマ帝国が圧倒的な存在感を示すのは、今も帝国の領域各地に、存在を証明する遺跡の数々が残されているからだろう。(その点、モンゴル帝国などは、見事なほどに証跡を残すということに無頓着である)
帝国領各地に残るローマ遺跡は、劇場、浴場、神殿、橋、水道、城壁と多彩だが、みんな石で出来ていることに特徴がある。
天高く石を積み上げ造形を為す技術、土木と建築の業こそが、ローマ人が他民族にぬきんでたものであり、支配力の源泉であったのだと思う。
今日でも、たとえば、南フランスを旅していると突然視界にポン・デュ・ガールの巨大な水道橋が目に飛び込んでくる。日本がまだ国の様態を為していなかった時代に、この巨大な土木工事を成し遂げたことには驚かされるし、現地のガリアの民びとも、これを見たとたんに「ローマには敵わない」と素直に思ったことだろう。同様の水道橋の遺構は、スペインのセゴビアにも、トルコのイスタンブールにも遺っていて、共通の技術がローマから各地に伝搬したことを示している。
さて、ローマ人は優れた土木建築の技術を持っていたから、空間構成を人工的に行うことに秀でていた。ローマ帝国領内に遺る広場を見ると、壁か建築か、とにかく石で出来た背の高い何かに、広場は囲まれている。ローマ風の広場は立方体、乃至直方体の空間なのであって、天井の部分だけが、空に抜けていると考えれば良い。広場の正面には、神殿、教会、市庁舎など人々が出入りする公共建築が配されており、広場自体も正面の建物を中心とする一種の劇場空間であるように構築されている。広場は日常市場として機能する一方で、権力者と人民は身分の差があっても、一つの劇場空間を祝祭によって共有するように設計が為されている。すなわち「パンとサーカス」は、当初円形劇場から始まったのだが、やがて方形の広場がこれに代わるようになったのだと思う。
一方、我が日本では、そのような土木建築の技術を持たなかった。それ故に、幸いと言うべきか、縄一本、盛り塩少々で結界を張るというユニークな文化が発達した。すなわち、空間の境界、あるいは、極端に言えば空間を構成する点に象徴的な何かを配置するだけで、目に見えない結界が張られ、時に祝祭の空間ともなり、時に商業空間ともなったのである。
この稿の筆者は、我が国に、四日市、八日市、十日市など臨時の市場が生まれたにもかかわらず、それらが恒常性を発揮しなかった理由の一つは、市場の縄張りが、恒常的な建築ではなく、注連縄一本の臨時のものであったためではないかと思う。
我が国の人々が結界を張るとき、そこにはハレの空間が出現した。そして、注連縄がほどかれ、あるいは盛り塩が消された瞬間にその場はケの空間に戻ったのではないだろうか。
2016年10月1日
-

広報
この稿の筆者が、あるビール会社の広告宣伝の担当者であったことは、本欄でも折に触れて書いている。時期によって、所属した部門の名前は広報部であったり、マーケティング部であったり、宣伝部であったりしたのだが、とにかく広報部門というものが、宣伝部門の隣にあった時期が長く、隣の部門の仕事を兼務したり、手伝っていたこともある。
宣伝と広報で、仕事の内容はどう違うか。会社経営に詳しくない方のために少し説明する。宣伝と言うのは、スポンサーとしてお金を払い、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、交通広告、屋外看板などの媒体のスペースを買って、これに自社の商品などの広告原稿やコマーシャルをのせる仕事である。広告原稿やテレビ、ラジオのコマーシャルは広告代理店や制作プロダクションに頼んでつくることもあるが、基本的には自社の言いたいことを消費者の皆様に伝えるのが使命である。一方、広報というものは、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのニュース欄に、自社の情報を載せていただくのが仕事である。新聞記者や放送番組の制作者は、スポンサーのお金の力では自由にならないので、広報部門の担当者は日頃から記者や制作者と仲良くして、自社の事業内容、商品情報をよく理解してもらい、少しでも自社に好意的な記事やニュースを発信していただくのが使命であった。筆者の隣の席の広報課長は、よく「マスコミに接待されるのが宣伝部門、マスコミを接待するのが広報部門なのさ」とか、軽口を叩いていたものだ。
さて、今月はその広報部門(英語では宣伝=advertisingに対して、広報はpublicityという)の話を書く。企業広報の仕事(学校や役所にも共通する)を詳しく分析すると「火消しの広報」、「ばらまき広報」、「仕掛けの広報」の三つの段階がある。
「火消しの広報」とは、当該企業の不祥事(たとえば経営者の背任や脱税、製品のクレームやリコール、事故や火災、社員のセクハラ、パワハラ等々、自社が世間にご迷惑を掛け、頭を下げるべき出来事)が生じたときのマスコミ対応である。記者会見をセットし、経営者の出席を手配し、出席の役員に頭の下げ方の角度を指導し、誤解に基づくマイナス情報が発信されないように、的確な説明を行うことを以て「火消し」という。災いは何時やってくるか分からないから、広報部門には、つねに非常事態に備える準備が必要である。
「ばらまき広報」とは、広報部門のもっとも日常的な業務で、広報資料(業界ではレリース=releaseと呼ぶ)という自社が世間に発信したい情報を書いた書類や写真を記者倶楽部に一斉に配布し、マスコミからの取材に応える仕事である。只ばらまいただけでは取り上げてもらえないので、取材する側との日常のコミュニケーションが大切である。時には特定のメディアに大事なニュースをリークし、大きく取り上げてもらうような寝技も使う。
「仕掛けの広報」とは、イベント、コンクールなどを広報部門側で企画し、マスコミに取り上げてもらうニュース自体を創造する仕事である。たとえば新商品の感想文コンテストなど、ニュースの内容はたわいないものも多いが、広報担当者の企画センスが問われる。
広報の仕事は、宣伝に比べると地味だが、時にはコストを掛けずに社名や商品名を情報発信することもできる。企業人の仕事としては魅力的な部門の一つだ。
2016年9月1日
-

稲荷寿司
このところ、歴史認識だとか、科学技術だとか難しい話が続いたので、今月は庶民一般の大好きな食べもの、稲荷寿司の話を書く。
まず、1837年(天保8年)から書き始められて、約30年(ちょうど幕末まで)書きつながれた喜多川守貞という人の著書「守貞漫稿」という本のことを紹介したい。
この人は、関西生まれの商人で江戸へ出てきて東西の風俗の違いに驚き、以来、時勢、地理、家宅、人事から始まって、娼家の習慣から男女髪型、浴場、子供の遊びに至るまで風俗百般を調査し、東西を比較、精細な図と共に35巻にまとめた。残念ながら、当時著作としては出版されなかったが、明治になってから翻刻されて世に出た。現在、近世風俗を調べる人にとってはもっとも基礎的な文献の一つだという。
その「守貞漫稿」に掲載されているものが、この世の文献に稲荷寿司が登場した初めだそうだ。
それによれば、天保の末年、江戸で豆腐を油で揚げたものを裂いて袋の形にして、そのなかに木茸や干瓢を刻んだ飯を詰めて、すしと称して売り歩いたもの。油揚を狐が好む故に稲荷鮨、篠田鮨などという名を付けたと記されている。至って安い、下世話な食べ物だとも書かれている。
別の説には、お稲荷さんは五穀豊穣の神様で、お米を俵形に詰めた稲荷寿司は、お稲荷さんを象徴したもの(供え物として適切であった?)であるというのもある。この場合狐は、お稲荷さんのお使いだから、稲荷寿司が狐の好物である理由は、「狐が、油揚を好きだから」と言うよりは、稲荷寿司は五穀豊穣の象徴だからということになる。どちらでもよいような話だが、この稿の筆者はかねてから、狐という動物は本当に油揚が好きなのだろうか、という疑問を持っていて、一度試してみたいと思いつつその機会を得ないでいるので、あえて、別の説も紹介した次第である。
稲荷寿司を江戸時代に紹介した別の文献にも、「安い」「下世話」という話は大概書かれていて、新鮮な魚を握った握り寿司を高級として、油揚に飯を詰めた稲荷寿司を下世話とする風潮は、稲荷寿司ができた頃からあったらしい。「天言筆記」という本には、飯の他におからを詰めた稲荷寿司をわさび醤油で食べる話が出てくるそうだ。これなど読者の家庭で容易に試すことが可能なので一度是非、挑戦してみられることをお勧めする。
稲荷寿司の形は、俵形が基本だが、土地によっては、三角形のものもある。西日本の稲荷寿司に三角形のものが多いらしい。助六寿司というのは稲荷寿司と切った巻物が一緒に出てくるものだが、これは歌舞伎の登場人物助六の恋人が吉原の花魁揚巻で、「揚げ」と「巻物」であるという江戸っ子流の洒落である。
さて、以前神様の方のお稲荷さんのことを書いたときにもご紹介したかもしれないが、この稿の筆者の愛して止まない稲荷寿司は、東京六本木のホテルアイビス地下にあった「おつな寿司」の、油揚が裏返しになった稲荷寿司。筆者が宣伝マンであった時代に、よくタレントさんの楽屋見舞いに用いたものだ。現在ホテルアイビスは再開発工事中だが、ネットで調べた限りでは「おつな寿司」は近くに移転して営業しているらしい。
「おつな寿司」
東京都 港区 六本木 7-14-16 03-3401-9953 http://www.otsuna-sushi.com/2016年8月1日
-

水素社会
東日本大震災の後、2011年8月号の本欄で「節電、蓄電、自家発電」と題し、地球温暖化防止と脱原子力のための代替エネルギーについて書いた。その続きの話である。
「節電、蓄電、自家発電」の要旨は、電気というものは水の流れのようなもので、貯めておくことが難しい。もし真夏の昼間電力の10-20%程度でも貯めておくことができれば、発電所の数をかなり減らすことが出来る。脱原子力発電も可能かもしれない、というものであった。具体的な例としては、揚水発電と言って、夜間電力で水をポンプで高所に汲み上げ、昼間その水をダムから落として水力発電を行う術などを紹介した。
さて、世間でよく知られる、太陽光発電や風力発電などには、一つの欠点がある。それは、不安定で、要るときに使えるとは限らないということである。真夏の昼間、ものすごく暑い日に太陽光で発電することは出来そうだが、風が吹かなければ風力発電は出来ない。
つまり、代替エネルギーによる発電は、人々が電力を欲しいときに、当てにならないことがあるという訳で、その欠点が原子力発電推進論の一つの論拠になっている。ところが、電気を貯める(電池代わりの)手段として、水素というものが最近有力になってきた。
水素は、地球上に水という形で普く存在している。電力の原料としては木材、石炭、石油などの炭素系の化石燃料や、ウランなどの核燃料に比較しても、入手はきわめて容易である。とくに我が国の様な海洋国家の場合、国の四囲は水だらけである。
さて、よく知られているように水の構成要素は水素原子2個と酸素原子1個である(H2O)。水の分子の水素と酸素は、固く結合しているのだが、電気を与えると分解する。これを水の電気分解という。水が電気分解すると酸素は大気中に放出され、残りは水素ガスになる。その水素ガスをタンクに貯めておいて、電力が欲しいときに大気中の酸素と再び結合させると水になる。水素と酸素が結合して水が出来るときには、電気分解と逆の原理が働いて、電気が放出される。石炭や石油を燃やす(酸素と結合させる)と二酸化炭素が大気中に放出されるのだが、まあ簡単に言えば水素を「燃やして」も水しか出てこない。その上結構なことには、水素と酸素が結合し水となるときに、電気が出てくるのである。一つ問題があるのは、この水素燃料電池の仕組みは、現在の所まだロスが大きい。最大でも、水を電気分解するときに使った電力の60-70%くらいしか、回収できない。
現在の技術では、水から水素をつくるよりも、むしろ天然ガスから水素を取り出す(改質という)方が、効率は良い。既に市販されている「エネファーム」などの水素発電装置は、天然ガス改質法を用いているが、これだと有限の化石燃料を使うし、改質の過程で二酸化炭素も発生する。
やはり、将来の技術の本命は、水の電気分解であるだろう。水の電気分解効率が向上し、且つ水素ガスという一種の危険物を都会の中で安全に管理する技術が進めば、太陽光や風力発電で得た電力を用いて、水を分解して水素を貯め、その水素を電力が欲しいときに水に戻して電力を取り出すという方法が、代替エネルギーの本命となることだろう。
注:本稿は、「東芝が目指す水素社会」のホームページに取材させていただいた。http://www.toshiba.co.jp/newenergy/2016年7月1日
-

無線、暗号、コンピュータ
無線通信というものと、コンピュータ(古い言い方をすれば電子計算機)というものには深い因縁がある。今月は、それについて述べたい。
無線通信は、イタリア人グリエルモ・マルコーニが19世紀の終わり頃に発明したとされる(異説もある)。マルコーニが無線通信の事業化に乗り出してすぐの頃に、タイタニック号の沈没事件(1912年)が起きた。無線通信は、この時初めて実用として活躍した。それから、50年くらいの間、無線通信は電信といって、トン・ツーの組み合わせで綴るモールス符号によって行われてきた。真珠湾奇襲の「トラ・トラ・トラ」(我奇襲に成功せり)の信号もモールス符号である。無線電話は、第二次大戦中に一部で使われてはいたが、一般社会に普及するのは第二次大戦後である。
無線通信というものは一定の周波数帯の受信機を持っていれば誰もが受信できるので、傍受と言うことが基本的に可能である。そこで、人々は暗号を用いて通信の秘密を守ろうとした。異地点間のA(攻撃隊の隊長)とB(航空母艦座乗の司令長官)の間で「トラ・トラ・トラ」という信号は「我奇襲に成功せり」の意味であると予め了解しておいて、発信すると、AとBの間では意味のある会話が成立するが、他人が傍受しても何の意味だかわからない。これが暗号の原理である。暗号の歴史は人類の歴史と同じくらい長い。が、暗号は第二次世界大戦の頃には、かなり高度な数理(アルゴリズム)を用いた複雑なものとなっており、暗号鍵を知らないで解読するのは、かなり困難になった。そこで敵方の暗号を解読するのに二つの技術が生み出された。一つは、窃盗や色仕掛けで暗号鍵が記載されている乱数表や、暗号文を作成するタイプライターに似た機械を盗み出すスパイ術であり、もう一つは力業で、大量の計算をして数理で暗号を解読する技術である。後者の力業はとても人間の手に負えないので、機械に頼ることになる。この暗号解読を力業でやってくれる機械として発明されたのが、電子計算機なのである。電子計算機は、英米で発達し、第二次大戦における連合国側の暗号解読技術は、優れたスパイ術と相まって、枢軸国側を遙かに凌いだ。ミッドウェー海戦にしろ、山本五十六司令長官の機上戦死にしろ、日本がアメリカに負けてしまったかなりの要因は、無線で米軍が傍受した日本海軍の暗号通信文を、米国側に解読されてしまったことにあると言っても過言でない。日本側も、米軍の暗号を解読するためにそれなりにがんばったが、残念ながら人力は電子計算機の能力の及ぶところではなかった。
その後、無線通信とコンピュータは、別れ別れに発達をすることになった。無線技術は、電信から電話(音声)へ、そしてテレビ(画像)放送へと発達した。一方、コンピュータ同士をつないで有線で通信する技術(コンピュータ通信)は後にインターネットへと発達した。そして今、無線とコンピュータの技術は再び出会おうとしている。そう、今貴方が使っているスマホが、その出会いの証である。そしてこの再会の仲立ち役は、暗号技術である。暗号こそが、貴方のスマホの通信秘密を守る、大事な仲人なのだ。
2016年6月1日
-
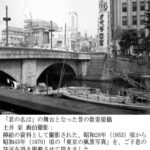
忘却
「忘却とは忘れ去ることなり。忘れ得ずして忘却を誓ふ心の悲しさよ」
菊田一夫の名作、NHKラジオドラマ「君の名は」冒頭の有名なフレーズである。
と、言っても、放送開始は1952年(昭和27年)であるから、すくなくとも現在70歳くらいから上の方でないと、上記の台詞をナマで聴いたのを覚えておられることはないだろう。
このドラマでは、忘れようとしても忘れられない人、というのがテーマであって、忘れることより忘れられないことの方に重点がある。世の中は戦後復興に向かい、国はまだ若く元気であった。封建的な家族制度のくびきにつながれた女性の主人公と、形式上は不倫なのだが純愛を貫く男性の主人公。真知子と春樹は、ともに新しい国、社会、個人の自由の象徴であった。まあ、要するに国民は、エネルギーに満ちて健康であったのだ。
そこには、高齢化、認知症、忘れたくなくても忘れてしまう問題というのはまだなかった。
その次に来るのは、高度成長。「都合の悪いことは、飲んで忘れてしまおう」、という無責任時代。「ちょいと一杯のつもりで飲んで、いつの間にやら、はしご酒」「わかっちゃいるけどやめられねぇ」は、後に都知事となった青島幸男の作詞で植木等が歌ったご存知「スーダラ節」。この時代の日本は、プロジェクトX、「ものづくり日本」の時代でもあった。が、一方で公害垂れ流し、川も空も真っ黒け、手抜き工事もやり放題、後先を顧みず原子力発電に邁進する「行け行けドンドン」の産業優先時代でもあった。忘却について言えば、高度成長期の日本は、深刻な経験や問題を忘れる能力のある者が優者で、過去をいつまでも忘れられない者が負けていく、そんな時代であった。やがて、バブル。忘れちゃいけないことも平気で忘れてしまう。ノリと軽さと無駄遣いの時代が来る。ここで日本は決定的に国を誤る。せっかく豊かになった富を、ストック(広い意味での社会資本、社会インフラ、研究投資、芸術文化や教育教養も含めて)に転換せず、ひたすらフロー(社会における金融の流量)を追求した。不動産投資、金融投資、マネーゲーム。つまりはフローの方が、もの作りや研究開発よりも早く結果が出る。出世につながる。目の前の刺激が、ほんとうに大切なことを忘れさせてしまう。人々はついでに純愛も忘れ、ひたすら欲望の充足に走った。
バブル崩壊。高齢化社会、人口減少。自分で何をして良いのかわからない惚けた経営者が、「若い人に任せる」と言って部門ごと責任を丸投げし、結果責任だけを追及するようになり、日本国中がヒラメ社会化した。「やってみなはれ」でも「だめならクビよ」という社会は、やがて大量の非正規雇用者を生み出した。それは、セーフティネットなんてどこにもない、ひどく危なげで不安な社会でもある。高度成長の戦士は恍惚老人と化し、忘れたくなくても忘れてしまうのは、日常の食事や出来事、身の回りの地図と位置。はいかい、行方不明の老人を社会がどのように守るのか、高齢者の忘却は、社会共通の大問題である。
そして、今、日本の国家自身が、70年前の戦争の死者を忘れ、他国に犯した過ちを忘れ、かつて世界の人々に対してした崇高な約束を忘れようとしているのではないだろうか。
2016年5月1日
-

上座部仏教
縁あって、ミャンマーに出かけた。
この国は、上座部仏教(南インドやスリランカを経てミャンマー、タイ、ラオスなどに伝わったいわゆる南伝仏教)の世界である。5千万人の人口に対して20-30万人の出家僧侶がいるという。ほんとうの僧侶のほかに、男性は一生に一度以上、暫時剃髪出家して寺院の戒律に身を委ねる。僧侶は、厳しい戒律を守って、午前中しか食事をせず、金銭や女性に触れないという暮らしをする。僧侶の生活は、老若男女市民すべての寄進によって賄われる。この国では、寺院に寄進をすることが人生の生きがいである。社会の中で競争し、働いて、富を得ても、その富を寺に寄進してはじめて、働いた実感を得ることができるのである。一方寺院では、僧侶はきわめて禁欲的に生きているので、寄進された富はなんらか社会に還元されるのであろう。上座部仏教は、日本では20世紀の半ば頃まで、小乗仏教と呼ばれた。それに対して、チベット、中国、朝鮮を経て日本に伝わった北伝仏教の方を大乗仏教と自称した。その後、1950年コロンボで開催の世界仏教徒会議において大乗側が南伝仏教を小乗と呼ぶのは蔑称であるということになって、上座部仏教という名前が使われるようになったという。
では、南伝仏教と北伝仏教の教えの違いは何処にあるか。この稿の筆者は、仏教徒の家庭に育ったわけではないので、あくまでも外側から見た筆者の理解を以下に記す。お釈迦様にとっての課題は、輪廻転生を繰り返すこの世の業(カルマ)から解脱することであり、その方法は瞑想と禁欲、修行であった。具体的にどんな修行をなさったのかは諸説あるが、とにかくあるときお釈迦様は悟りを開かれたのである。この時点で、悟りを開いて業から解脱することは誰にでも可能なことではなかった。悟りとは、一部の少数者が厳しい修行を経てはじめて到達できる境地であった。お釈迦様のあと、その跡を慕って自分も悟りの境地に至ろうと努力する人々が生まれ、仏教団が形成されるようになった。
そして仏教が世に伝播していく過程で、戒律を地域の慣習にあわせて緩やかに解釈しようとする派(たとえば、食事は午後にとっても良い、とか)とお釈迦様の方法を細部まで守ろうという派が分裂した。前者は、次第に一部の特別な人だけが悟りを得るのではなく、お釈迦様の教えを広く遍く普及させて多くの衆生を救済しようとする傾向に走り、後者はあくまで厳しく修行をする僧侶達を衆生が支えることを以て、一般人の心の平安が得られるとする傾向を持つようになった。前者が北伝仏教、後者が南伝仏教である。北伝が自らを大乗仏教と呼び、南伝を小乗と蔑んだのは、北伝仏教が大衆も乗れる大きな乗り物であるのに対して、南伝仏教は一部の特別な人しか乗れない小さな乗り物であるとしたからである。一方で、「大乗仏教」が極まれば、南無阿弥陀仏六字の名号を称えるだけで、何の修行をしなくとも救済が得られるという教えにもなる。どちらが正しいと言えないが、ミャンマーの国中に建てられたパゴダや寺院を見ると、人々が寄進という価値観を共有することによって、社会の富が循環するというのも、一つの大きな思想であると思った。
2016年4月1日
-

アジアの近代(続)
前号では、アジアの近代化には、軍事、経済、政治等複数の側面があることを述べた。
この内軍事の近代化、経済の工業化(資本主義化)については今日21世紀の北東アジア諸国は達成の途を歩んでいると言っても差し支えない。これらの近代化は概ね世界共通のものであり、とくにアジア的な特徴があるわけでもない。問題は、政治の近代化である。アジア諸国の内、欧米的な意味での議会制民主主義と自由、平等、博愛原理に基づいた政治制度を完全に達成した国は、日本しかない。東南アジア諸国は概ね欧米モデルの政治制度を標榜してはいるが、実際には、開発独裁であったり、軍部統治であったりで、議会と選挙による政権交代が常態の国はきわめて少ない。韓国あたりがだいぶ欧米モデルに近づいてはいるが、政党政治の内実は、まだ日本の大正期政党政治のレベルくらいに見える。中国や北朝鮮の政治制度がどうなるのかは予断を許さない。
さて、問題は、政治制度の近代化について、欧米と異なるアジア的なモデルが存在しうるか否か、ということである。中国の革命家孫文は、かつて西洋帝国主義の政治を覇道と呼び、対するに東洋的な王道政治の実現を説いた。しかし、その王道政治の思想原理、政治制度のモデルなどを中華民国で具体化することは出来なかった。日本も、かつて満州統治や大東亜共栄圏の制度設計において「東洋的王道」を掲げたことがあるが、それは西洋的な個人主義、競争原理の否定と統制経済、軍部による全体主義的な指導を正当化するに過ぎず、独自の政治原理を提起するには至っていない。また、印度の革命家ガンジーも、非暴力抵抗主義という反権力の方法を提案することは出来たが、その思想を統治(あるいは自治)の原理にまで敷衍することは出来ていない。21世紀国際政治の一つのエポックである、イスラーム原理主義もまた、西洋近代に対置しうるあたらしい政治原理や制度を示すことは出来ず、ただ預言者への回帰を説くだけに見える。
現実社会を離れた思惟や、文化芸術において、東洋は十分西洋に拮抗しうる膨大な歴史的蓄積を有している。だが、要するに、21世紀の今日に至るも、軍事や経済の近代化と同様、政治の近代化について、西洋モデルを超える東洋的なモデルは示されていない。
それは何故か。短い紙数で筆者が感じていることを記すと、政治制度も経済のあり方も、結局は技術革新の産物であるというに尽きる。西洋近代の資本主義の根っこに仮にキリスト教文明があったとしても、西洋近代の政治思想や資本主義経済、さらには帝国主義や植民地支配を生み出したものは、産業革命による技術革新だったのではあるまいか。
東洋の思想は、産業革命に匹敵する技術的な裏付けを持たなかったのだ。
そうであるとすれば、今日、インターネット時代の情報技術の革新こそが、現代社会のあり様を決める根幹である。私たちは、まさに洋の東西を問わず、情報技術の革新が生み出すところの経済制度、政治制度、社会思想の、近代を超えた世界共通モデルをこそ設計すべきなのではないか。もはや、アジアの近代にこだわるべき時代ではない。
2016年3月1日
-

アジアの近代
以前「歴史認識」という題で、日本のアジアにおける侵略や戦争について、日本人が第一次世界大戦後の国際法秩序しか問題にしないのに対して、中国、韓国の人々は日清戦争やさらには江華島事件などに遡って問題にしているということを書いた。
日本の言い分は、第一次世界大戦までは、よかれあしかれ帝国主義の時代。植民地保有も国際法に照らして合法だったというものだ。が、植民地にされた、あるいは侵略された側の言い分は、そもそも近代の初めから西洋諸国がアジアやアフリカの諸国を支配してきた歴史そのものが「まちがい」なのだし、西洋諸国の尻馬に乗って似たような振る舞いをした後進の近代国家日本などは、もっと「けしからん」ということになる。
その「けしからん」という思いの中には微妙に華夷秩序意識というものが働いている。
ところが、近代西洋諸国が、アジアを侵すようになると、小国日本は勇躍華夷秩序を脱し,アジア諸国の中でいち早く近代化を遂げた。東夷の国と思われていた日本は、いつの間にか西洋諸国を模倣するようになり、ついには近代化された軍隊を以て韓国を支配下に治め、中国にも筒先を向けるようになった。未だ近代に目覚めきれなかった、19世紀末期の中国、韓国の人々は、日本を夷狄と見下している内に、華夷秩序を破壊されて立場が逆転し、今度は近代化した日本という存在に脅かされるようになってしまった。
日本も、中国も、韓国も19世紀西洋列強のアジア進出に脅かされた。それらの国の青年達は、皆、自らも近代国家とならねば、独立を保てぬ事を思った。だが、どこまで自らを近代化するか、どの程度西洋に近くなるかについて、同じ国の中でも、一人一人の思いは異なるものがあった。最も異議の少なかったのは、軍事技術の近代化である。軍艦、鉄砲、近代的軍隊がなければ侵略されてしまう。だが、その軍事技術さえ、刀槍や拳法で代替できると称える者も居た。経済の仕組みの近代化には強い反発があった。工業化、資本主義化とは新たな支配と被支配の関係をつくることであったし、農村的秩序や服装、生活から学問、芸術に至る東アジア的文化の破壊につながるものでもあった。さらに政治における近代化は最も異議が多かった。自由、平等、博愛、議会制民主主義は東アジアの伝統に馴染みにくかったし、第一、西洋の理想主義的政治思想も、西洋人の野獣のような振る舞いの前では説得力に乏しかった。アジアの青年達は、この200年ほどの間、なんとか西洋的近代主義に対置しうるアジア的価値観を模索しようとした。が、結局その試みはあまり成功せずに終わったと言えるのではないか。~この項続く。
2016年2月1日
