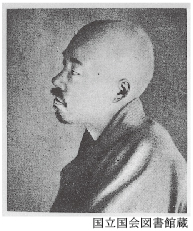江戸時代のこと。士農工商と言った身分から、やや離れたところに、現代で言えば自由業にあたる一連の芸事の師匠という職種があった。
それらの中で比較的安定していたのは、武士に必要な芸を教授する職で、剣術、槍術、弓術などの師範、漢学塾の先生などがこれに該当する。和歌、料理などはこの時代既に古典芸能で、冷泉家、四条家などと言う京都の皇室由来のお公卿さんが家元になって印可という名の権威を与えることになっていた。かわったところでは、相撲もこの皇室由来の芸の一つで、吉田司家というお公卿さんが日の下開山横綱を許すというタテマエになっていた。
次いで、お茶、お花、踊り、三味線など戦国期以降発達した芸事の場合も、江戸期の間に家元制度が確立して、家元が芸名を与え、あるいは師匠として活動することを許可すれば、その人はそれなりに芸事を職業として食べていくことが出来た。
そうした中で、最も貧乏で不安定だった職種の一つが、俳句の宗匠である。松尾芭蕉、小林一茶などの伝記を読めば、この人達が殆ど一生地方を放浪して、江戸の大商人や地方の豪族をスポンサーに句会を開いて貰い、僅かな謝礼と一宿一飯の恩義を得て暮らしていたのがよく分かる。有名な「奥の細道」は、芭蕉の地方巡業の記録を句集にまとめたものであるし、辞世の句「旅に病んで夢は枯れ野を駆け巡る」も、旅の途中で客死した芭蕉の境涯をよく表している。関西系の井原西鶴の場合は俳句の他に読み物作家、与謝蕪村の場合は画家という生業があったので、なんとか俳諧師を続けることが出来たと言える。
俳句は、もともと連歌の発句から発達したもので、連歌師というものは戦国期、各地の大名を訪問しては連歌の会を開いて貰い、一宿一飯の振る舞いにあずかり、謝礼を得て逗留し、各地の噂話や情報を提供するのが職業であった。だから、連歌師はスパイの一種として考えられる場合も多く、それが後の芭蕉忍者説の根拠にもなっている。
さて、近世末期俳句はやや衰退の傾向にあったが、明治に入って正岡子規が出るに及んで、近代芸術として蘇生した。子規は新聞記者であったが、早くに結核の病に倒れ、闘病しながら俳句の業を成したので、終生俳句を職業とすることはなかった。近代俳句を職業として完成させたのは、子規の弟子であった高浜虚子である。虚子の方法論はきわめて明快で、俳句にお茶、お花、踊りと同じ家元制度を導入しようとするものであった。俳句雑誌の同人を組織することによって、主宰という名の指導者の下に階級を設け、各地の句会を同人に主催させ、上納金によって主宰が飯を食う道を得るという、いわばヤクザと同じ組織論をもって虚子は周到に子規から受け継いだ「ホトトギス」を運用し、俳句独特の家元制度である「俳壇」を確立した。だが「俳壇」は、第二次世界大戦中には新興俳句弾圧事件を引き起こす。それは要約すれば家元制度、上納金制度による俳句の職業化が、子規の創始した近代芸術としての俳句に馴染まなかった故に引き起こされた悲劇といえる。
「俳壇」は今日もなお衰えてはいない。が、自由な表現としての俳句を職業としても成り立たせる試みとして、現在、同人誌ではなくインターネットの利用が始まっている。この稿の筆者としては、その動きに強く期待している。